@gon_gitsune まさにそうなのですが、ただ国内事情的な問題として、いわゆるブロックバスター展という問題があり、つまりある程度観客にウケないといけない。そのなかでマティスという作家は日本人観客にとって口当りがよい作家なのですよね(だからブロックバスター展の対象にえらばれる)。しかし、ブロックバスターだからといっても、もうちょっとなんとかなりそうかなという印象があったので記事にしたところでした。

@gon_gitsune まさにそうなのですが、ただ国内事情的な問題として、いわゆるブロックバスター展という問題があり、つまりある程度観客にウケないといけない。そのなかでマティスという作家は日本人観客にとって口当りがよい作家なのですよね(だからブロックバスター展の対象にえらばれる)。しかし、ブロックバスターだからといっても、もうちょっとなんとかなりそうかなという印象があったので記事にしたところでした。

@gofujita @tomooda
美術館には美術の啓蒙活動という側面があり、おっしゃるとおり、そこが研究と社会を繋ぐ活動になっているとおもいます。
日本の場合、西洋芸術の紹介というのがなかなか厄介な問題があり、というのも、借り物で構成されることが多いためお金がかかってしまい、集客できる人気作家に偏ってしまう(印象主義など)。マスにアプローチする都合上、観客の知識レベルも想定しづらく、レンジをひろくとって、かなり初歩的な説明も必要となってきます。
これをしばらく続けることにはとくに問題ないとおもうのですが、今回見に行った展示が20年前にも同じ作家の回顧展をやっていて、説明のあり方にあまり進歩がなかったように感じられました。アカデミックな領域では20年のあいだにあきらかに進んでいるはずなのですが、それが啓蒙レベルにはおちてこないのだとすると、やはり美術館としては観客を育てることに失敗したのではないか、ということを感じています。つまり、集客はするがなかなか教育を回路に組み込めない、というのが現状なのかなと感じました。
このあたりは美術館によっても状況が違っており、たとえば国立近代美術館では、常設展は所蔵作品でいろいろできるので、学術的な研究を反映した内容の展示を展開して、行く度に新鮮な発見があったりします。これは集客しなくてもよいからでもあるとおもいます。
担当学芸員の方が、わたしの記事を読んでだとおもいますが、今後の課題とおっしゃっていたので、たぶんここで述べたような課題感(集客と啓蒙の課題)があるのだろうなとおもいました。
https://twitter.com/ton0415/status/1652704133835800576

マティスの記事、まさか600もRTされるとおもわなかった。
じぶんとしてはある程度ギョーカイ人に対する批判のつもりだったから、読まれるとしても美術業界インナーサークルで記事が回覧されるものだとおもっていたのだけど、意外だったのは、RTの連鎖が始まる当初はぜんぜん業界の人ではなく、一般のアートファンっぽい人たちだった。というかたぶんメインで読んでくれたのがアートファンっぽい。
アート受容層、自分がおもっていたよりも遥かに裾野が広いんだなっておもったのと、若干ややこしいテキストでもいがいと読んでくれる。そうすると、綺麗事ならべてヨイショヨイショする美術メディアじゃなくてもぜんぜん成立するぞって気がしてきた。
https://twitter.com/tenjuu99/status/1652306560260128770

@gofujita @tomooda 恐竜展で、専門家が見ても刺激があり、子供の探究心を誘うような仕掛けをつくるというのは、とても興味深いです。まさしくそういう課題が美術館にもあるとおもっていますが、美術の学芸員もサイエンスコミュニケーターのかたたちと展示技法やアプローチについていろいろ議論していくとよいのかもしれないとおもいました。
> 人気作家の企画展でも、集まった人たちがつぎのステップへ進むきっかけになるような展示構成をつくるのも可能な気がする
こちらはまさにそのとおりだと感じています。わたしの印象としてはやっぱり美術館側がまだ観客をなめているという気がしていまして、観客もバカじゃないからこんな展示じゃ満足しないぞって突き上げをしていく必要があるのかなとおもっています。
> 作品が生まれる背景にこれほど強烈な議論があることに触れることができ、本当によかった
この感想はたいへんうれしいです。わたしは美術をつうじて社会を理解してきたというところがかなりあり、それは科学によって自然を理解するということとやはり似ているのだとおもいますが、それも芸術を見るおもしろさの一つだということがもっと広まるとよいなとおもっています。

展示を企画する側は、客にきてもらう必要があるから批判的な構成なんてしない。マティスを好きになってもらう努力をする。それでいろいろ脱臭していくことになる。美術はいいものだという態度をまず崩すことができないから、アカデミーで研究が進んでみても、たぶん美術館で止まってしまう。美術館が語る言語に問題があるんだけど、これはどうやって言語化され批評されるべきなんだろうか。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@gofujita @tomooda
美術館には美術の啓蒙活動という側面があり、おっしゃるとおり、そこが研究と社会を繋ぐ活動になっているとおもいます。
日本の場合、西洋芸術の紹介というのがなかなか厄介な問題があり、というのも、借り物で構成されることが多いためお金がかかってしまい、集客できる人気作家に偏ってしまう(印象主義など)。マスにアプローチする都合上、観客の知識レベルも想定しづらく、レンジをひろくとって、かなり初歩的な説明も必要となってきます。
これをしばらく続けることにはとくに問題ないとおもうのですが、今回見に行った展示が20年前にも同じ作家の回顧展をやっていて、説明のあり方にあまり進歩がなかったように感じられました。アカデミックな領域では20年のあいだにあきらかに進んでいるはずなのですが、それが啓蒙レベルにはおちてこないのだとすると、やはり美術館としては観客を育てることに失敗したのではないか、ということを感じています。つまり、集客はするがなかなか教育を回路に組み込めない、というのが現状なのかなと感じました。
このあたりは美術館によっても状況が違っており、たとえば国立近代美術館では、常設展は所蔵作品でいろいろできるので、学術的な研究を反映した内容の展示を展開して、行く度に新鮮な発見があったりします。これは集客しなくてもよいからでもあるとおもいます。
担当学芸員の方が、わたしの記事を読んでだとおもいますが、今後の課題とおっしゃっていたので、たぶんここで述べたような課題感(集客と啓蒙の課題)があるのだろうなとおもいました。
https://twitter.com/ton0415/status/1652704133835800576
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

自分は日本の美術館が観客なめてるなとおもうけど、今回のマティス展のはポンピドゥー側がめちゃくちゃ日本の観客なめてるとおもっている。記事に引用したマティスの「赤いキュロットのオダリスク」のカタログ記載、あれたぶんポンピドゥー側が差配した人だから(アンヌ・テリという人で、アンリ・マティス資料館というところにいるらしい)。カタログの構成もかなりポンピドゥーが口出ししているっぽいし。

フランスからすると日本はいい市場なんだろう。アメリカは自国でヨーロッパ近代のマスターピースもっているし、自国のアーティストを取り上げていけばいい。日本は「近代がない」という欠如意識というか、裏返すとヨーロッパへの憧れをいまだに捨ててないから、いくらでもイデオロギー注入できるとおもわれている。

フランスとしては、マティスの作品を通じてヴァンスの礼拝堂とか宣伝できれば観光産業がもうかるってわけで、よりフランスへの憧れをかきたてさせなければいけない。だからニースとかヴァンスとか固有名使う。オリジナルを見ないとわからないことがたくさんあるよねっていうような余白をもたせる。そういう構成をいつまでも続けさせるのは美術館人の怠慢だとおもう。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

藪前さんツイート消してたけど、補足でたしかにキャンセルカルチャーが云々とか言っていて、はっ?どういうこと??とはなったな。あの記事を読んでキャンセルカルチャーの文脈読むのは訳がわからない。キャンセルしてないし、読んでくれた人もキャンセルしようなんて人はみなかった。自分はマティス好きなんだけど、フォーマリズム解釈はもう飽きてるからもっと新しいマティス像を提示してよって思う。フォーマリズムっぽくないとマティスを見る楽しみがないなんてわけがない。

マティスのオダリスクに新鮮な造形的アイデアがあるからオリエンタリズムではないっていう理屈も意味がわからないけど、そもそもその理屈はレオ・スタインバーグの時点(1968)で批判されてた古典的なフォーマリズムでしかない。ぶっちゃけ20年前のマティス展のほうがその文脈踏まえた上で、マティスの性的な眼差しについて言及している。キュレーションという点で言えば後退というよりほかない。

ちゃんと書いてみるとバカみたいな議論になる一方で、すごく厄介でめんどくさい議論にも踏み込んでしまう...。
でもポリコレどうこうまじで関係ないんだが、そう受けとられるんだなとおもった。
https://twitter.com/tenjuu99/status/1653110836318339072?s=20

これ、自分の意図どおりに読めている人とそうでない人がいるのはどういう訳なんだろう...。自分の文章はわかりやすいわけではないとおもうのだけど。

植民地主義時代における表象システムの分析が必要というのが根本にはあって、それはフーコー的な議論をしているつもりなんだけど、芸術家の内在的な諸問題の解決・発展みたいな枠組みで語りだしてしまうと、そういうことができなくなっちゃう(まあそんなこと記事に書いていないんだけど...)。芸術家は社会的な制約から自由にいろいろ選択できる、とかそんなことありえないのに、マティスの選択だけにフォーカスしてしまう、それを可能にするために彼が何を描いたかという研究を捨てる。キュレーションもそこに結託する。それらが全体として機能してマティスという像を作りあげる。
そんなめんどくさい議論をしているつもりだったので、短絡したメッセージを受けとられるだろうなとおもっていたけど、どうもそれが意外と伝わっている印象がある。
キャンプ、結局楽しみの大きな一つが「ギアを集める」「選定する」で、ここの部分でぶっちゃけただの産業資本主義なんだよな。youtube見てるとみんなギアもきれいで使った形跡ないし、まあ使ってたり、撮影用にもう一つ用意してるんだろうけど、所有欲を持たそうとしてきてるだけだったりする。だから矢口高雄の漫画の名台詞「こんなもん買うバカがあるか「おらたちは物を買うなんてアホなことはしねえ!!」「たいていのもんは自分で作っちまう」を思い出す。本当に大事なのは「こちら側に残ること/もの」なんだよね。自律性を取り戻す。そのために「道具の力を借りる」イメージ。
道具って道具を呼ぶんですよね。焚き火がしたい。じゃあ焚き火台がいる。だとするとつかみもいるしトングもいる。焚き火シートもいるし、着火剤も....みたいに増えていく。「やらない」。「もたない」。この一択だけですべての道具がいらなくなる。
で、道具って「うるさい」んですよね。道具を呼ぶから。「使って!」とこちらに情報を送信し続けてくるから。

「われわれは帝国主義についての知識が足りないし、美術館もその知識の欠如をよしとする展示をしている」って主張したら、ポリコレだとか「マティスは植民地主義的なんてずっといわれている」とか「現代はもう違う」とか言われる世界なんだなー。勉強してくれとしか言えない...。
いや自分も最近まで知らんかったから言いづらい話なんだけど、無知に開きなおるのはバカか恥知らずなんよ。

ナショナリズムがどう機能するかということがわからなくても、植民地主義時代のフランス芸術の分析が分析できると信じているのはおめでたい人なんだっていうことがわからない。それだけフォーマリズムの毒は強い。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@on1000mark いやほんとにごく一部の反応で、批判ならいいけど揶揄だけされてましても...という感じです。論証っぽい見た目を持たされているだけに反応せざるを得なかった...。インターネット圧力に負けてしまった。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

リンダ・ノックリンいま読みはじめてて(いまさら)、おもしろいというか、自分の関心とめっちゃ近いやんっておもっているけど、リンダ・ノックリンを通じてしか植民地主義について語れない、あるいはリンダ・ノックリンについて語っていれば植民地主義について語ったことになる、という勘違いが業界にある。自分自身がどういう位置に配置されているのか、そういうことが問えていない。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
Twitterをやめたエンジニアが開発環境なんてなかったと証言していたけど、開発環境作られたという証明になった。良かった。

こういう感想がわりとあるっぽいのがよかった。めんどくさがらずに説明すればいいだけのことで、それも美術のおもしろさなので。
https://twitter.com/tarushirazu/status/1653350756932800514
ソクラテスの死 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AD%BB
これ論理学の学習者がつけたタイトル (?)

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

日本の美術史業界、近代美術やるひとがイコノロジーやっていないパターンがおおいのがめちゃくちゃ痛くて、サロンなり批評なりメディアなり表象の流通システムのなかでの芸術という存在者の記述ができないのも、イコノロジーの概念装置群が輸入されていないためだとおもう。絵解きみたいなものとして理解されてしまった。イコノロジーはフォーマリズムを存在論的に問いなおすことから始まっていて、いろいろな概念装置を作っているけど、そのへんがたぶん学術的に輸入されていないんだろうとおもっている。たぶん、これがキュレーション上でも芸術作品の社会性記述の欠如という欠陥を生みだしているようにおもう。

サロンとかメディアとか、中間的な社会(国家とかそういう大きな単位ではなく)における芸術作品という記述装置がないと、鑑賞行為が「作品-鑑賞者」という直接的で単純なモデルになってしまう。それで色とか形とか、直接的な要素の説明になってしまう。今回のマティスが「The Path to Color」、来年が「自由なフォルム」。こういう鑑賞モデルが想定されてしまっている。
もっとも、こういうのが、インスタグラム的なものやグッズ開発とめちゃくちゃ相性がよい、というのも背景にあるんだとおもうけど。

やっぱりSNSで人を気軽に揶揄するの怖いな〜気をつけようってなった。
揶揄って自分のほうが賢いとおもってるからやっているんで、ゴメンナサイっていいづらくなる。自分もそういうのがなくはない。



そういえば芸術における秩序の問題、創発っていう観点から考えたことあまりないな
https://scrapbox.io/tenjuu99/%E5%89%B5%E7%99%BA

自分の記事を読みなおしておもったけど、マティスの政治的な表象(ポリティカルなこと)について書いているんじゃなくて、具体的なポリティクスについて書いているんだな。だから、結局フランスの美術行政とか日本のブロックバスター展とかの結託のなかであるイデオロギーが再生産されている、ということがやはり問題になる。そのイデオロギーが超歴史主義的で、戦争とか知らんみたいな顔をして、マティスも戦争は悲しんだ、以上。みたいなことをやっている。
これは、結局フランスや日本の文化政策や教育だったりから生成する政治過程で、この政治過程の分析が必要なはずだっていうのがまあ引きだされる結論なはずで、つまりじつは芸術なんてなんの関係もない。ようするに芸術はいかに総力戦体制において存在してきたかということであるし、現在においても実は総力戦体制の麾下にある。こういうのに芸術家がいやな顔するのは仕方ない。芸術のはなしなんて一切していなくてポリティクスの話してるんだから。
自分の記事は、マティスの政治的性格を分析することでよりマティスについての理解が深まる、とかが結局どうでもよくて、そうではなくて、マティスを分析することで植民地主義や実際のポリティクスについての分析ができるはずだ、ということに関心がある、というようなものになっている。ここで分析対象となるマティスという存在は、すでに過去にあった実在の芸術家とか現に存在する芸術作品群とかではなくて、「マティスとして知られているもの」「マティスとして我々が考えているもの」の総体を指す。この「マティスとして知られているものの総体」は、例えば、美術史学上での研究、美術館での展示、批評や一般記事や宣伝などなどによって形成され、歴史的なものである。つまり、フーコー的な考古学が可能な領域である。この考古学的な作業によって得られるであろうものは、マティスのナショナリスティックな性格が排除されてきたという経緯を追うことで、現代日本の表象システムがどのように機能するか、ということが分析可能になるであろう。なんか書き方までフーコーっぽくなってきた気がするのでこのへんでやめるし自分はこんな考古学はたぶんめんどくさすぎてしない。

自分、ポストコロニアルの問題ぜんぜん詳しくないのに触れてるの意味がわからないな。

x SNSでは議論ができない
o SNSでは安易に人を揶揄するやつらがたくさんいるから議論なんてしたくない

でもこっち(fediverse)のほうがかなり安心感あって、わりかしテキトーな放言できる感じはやっぱりかなりある。

マティスは1931年の時点ですでに国際化していたのか。1931年にMoMAで回顧展がおこなわれている。
https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E5%9B%9E%E9%A1%A7%E5%B1%95

左翼方面からこんなんでてるのやばいな...
いまのウクライナを大日本帝国に重ねるのはさすがに意味がわからない。当時の日本と似ているのはどこからどうみてもロシアのほうだよ。敗戦の事実は覚えていても侵略の事実は忘れる。
https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/04/29/news-135/


けっきょくTwitterって噂話でしかないから、見えないところで噂話がおこなわれている(見えていないことが見えている)というのは、わりと気になる

「1912年から13年にかけて2度モロッコに滞在した結果、(略)旅が重要であることを実感した」とか、なんの注釈もないんよね。マティス展のカタログ。いや、いままでモダンアートの記述で、アーティストが旅に行って変わったとかの記述があるときに、その旅先は植民地だけどねって書いてあるのを見たことがない気がするけど...。
それが悪いとは言えないかもしれないけど、やっぱりいろいろ思うわけです。

「日本による外国の支配」という単純な事実を忘れるから、「フランスによる外国の支配」というものが歴史を見るパースペクティブから外れる。それで、帝国主義と芸術といえば、国内芸術家が、国家による支配・強制を受けていたという謎のパースペクティブが生産される。これは一時期のアヴァンギャルドとアナーキズムの近さだけから歴史を遡って照射する欺瞞に過ぎないが、まさにこの国家対個人の支配関係しか見えないのが、日本の戦争にたいする被害者意識に由来するものだろう。それで、自身は対象としての芸術家を理解しているつもりになっているから、対象を構成する自身のパースペクティブは不可視になる。

きのう、某氏の話を聞いて思ったけど、じつのところ現在の日本のパースペクティブはナショナリズムかグローバリズムのどちらかでしかなくなっている。後者について本人はアナーキズムだと感じているだろうが実際にはグローバリズムで、グローバリズムもナショナリズムもともに歴史理解を歪める。

あ、いろいろ言っているけど、ZINEおかけんは買いにいきます!
https://c.bunfree.net/c/tokyo36/h2f/%E3%81%8D/71
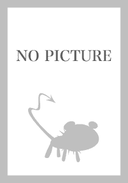

ニューアートヒストリーはもう当然前提とされていると気軽に言えてしまう人はともかく、20年前のマティス展のカタログを見ると、まさにニューアートヒストリーを踏まえつつマティス展を実施するという困難に、田中さんや天野さんが四苦八苦している様が伺える。彼らの試みは結局、フォーマリズムとニューアートヒストリーの同時輸入とでも言えるもので、性格上かなり難解な仕事にならざるを得ない。それはうまくいっているとも失敗しているともいえるが、日本特有の問題になっている。これはかなり奇妙な混合物だとおもう。「当然前提として織り込まれている」ような前提は、いまだに存在していない。


陰翳礼讃のときに春琴抄とかの盲目について書いてて、視覚の否定と主体の否定が結びついている、みたいな話聞いてる。

松林図屏風、どこからみても絵として成立しているのが西洋の遠近法と違う、という話、もうちょっと別な局面に展開できそう

アーツ・アンド・クラフツ→家
バウハウス→建築
ウルム造形大→環境
という同心円状の展開

柳宗悦
Culture/Civilization
文化/文明
下村寅太郎もこの対比使ってたな。