美術業界にいる人、他人の見解を公然と批判するわけでもはなく、揶揄する人が多いというか目立っちゃうんだよな。しかも、自分の記事を業界っぽい人間が揶揄するのとか、こっちはただの一般観客なわけでさ。業界の人間が、一般観客が書いた感想記事にたいして無知だねってマウントしてくる、そういう修羅の国。
もちろんそうじゃない人がたくさんいるのは知っているけど、そういう人が悪い意味で目立つ。

美術業界にいる人、他人の見解を公然と批判するわけでもはなく、揶揄する人が多いというか目立っちゃうんだよな。しかも、自分の記事を業界っぽい人間が揶揄するのとか、こっちはただの一般観客なわけでさ。業界の人間が、一般観客が書いた感想記事にたいして無知だねってマウントしてくる、そういう修羅の国。
もちろんそうじゃない人がたくさんいるのは知っているけど、そういう人が悪い意味で目立つ。

まあでもこういう人はどこにでもいるのか。業界的な課題を整理して共有できていればこんなことにはならないんだけど、よくもわるくも広さがありつつ、メディアは足りていない。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

昨日行ってきたこれも、岡倉天心、漱石、谷崎、柳宋悦、和辻、岡本太郎、鈴木大拙とざーっと統合的な視点で見て、戦争への視点がゼロだったからなぁ。逆にびっくりしてしまった。和辻のモンスーンとか大東亜共栄圏やん。鈴木大拙もいろいろ言われているわけだし。
https://pleroma.tenjuu.net/notice/AVNIuHwXKy9ai0FXrU
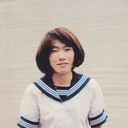


日本美術史の脱構築も必要っぽいけど、他方で世界美術史みたいなパースペクティブも必要で、結局いろんな意味で京都学派を読む必要があることになる
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ああ、藪前さんの一連のツイートで疑問だったの、ニューアートヒストリーをフェミニズムや植民地主義的な反省とみなしていて、美術史の脱構築とみなしていないからだな

美術史を語る語り口がどうなっているかというメタ意識がすごく弱くて、自分が展示の仕方もっとあるでしょって思ったのまさにこれだ。脱構築以前みたいに感じる。

西洋美術館でやってるブルターニュ展、そんなに期待してなかったんだけど、ふつうにいろんな視点を盛り込んでいておもしろかった。

「絵画の政治学」にのっている「ドガとドレフュス事件」、「ネトウヨの誕生」っていうタイトルになっていても違和感なく読める
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。