血の轍、介護が主題になるとはおもわなかったな。

あるアクティヴィストの活動をなんとなく眺めることになったんだけど、具体的なアクションが具体的な効果をもつためには適切な批評が必要で、排他的な態度になると価値をあまりもたないなという感想になった。そのアクティヴィストは、他人のインナーサークル感を批判というか揶揄していたけど、そのひとの活動そのものがインナーサークル内での活動を出られていない印象をもってしまった。

ゴッホのトマトスープとかは、アクティヴィズム的な活動としてはそれなりに効果あるんじゃないか。ただ、実際に提起したい問題にたいする理解がどれくらい伝わるかは、また方法を工夫する必要があるのかもしれない。

メディウムとは、個々の作品の形式が発生するための「可能性の空間」なのだ。 https://www.artresearchonline.com/issue-3a
おもしろいけど、これは古典的な意味での様式論になるんじゃないだろうか。グリーンバーグがヴェルフリンから引き継いでいるものの言い換えというか。それじたいが悪いわけではない。


難しくて半分もわからなかったな。結論は理解したけど。
部分部分ではかなりおもしろいことを言っているけど、全体でどういう繋がりのなかに配置されているかよくわからなかったのと、「存在論的」とか「現象学的」とかの述語がなに由来なのかわからなかった。「その人ごとに異なる居場所つまり現象学的な空間」って現象学関係なくない?「存在論的」という述語もわからなかった。

モノに対する見えとしての「現象学的」、そのモノの定義的な差としての「存在論的」みたいな区別があるように見えるんだけど、それだとけっこう素朴実在論ではないか


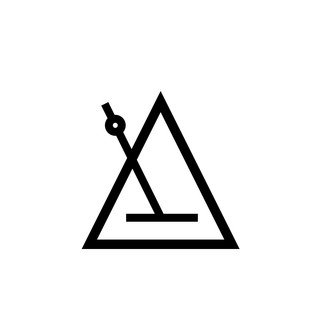

「パサブルとポシブル」(福尾)という概念を使って「インスタレーションはダンスホールであることもできる」と主張するが、芸術と非芸術の境界はある意味自明に存在しつづけているように見え、その自明性の由来が「現象学的」と「存在論的」という、このテキスト内に定義をもたない区別に由来するように見える。このテキスト内では、「存在論的」に区別されているものは乗り越え不可能な区別で、「芸術」と「モノ」はそういう「存在論的」次元の区別であるように暗示されているように読める。フリードの議論はまさにこの芸術と非芸術的物体との区別を問うものだったが、大岩さんの議論はこれをスポイルするものとも読める。気がする。
精読していないからまだなんとも言えないけど。

「インスタレーションはダンスホールであることもできる」と嘯きながら、(でもインスタレーションが芸術であることは自明だが)と暗黙の注釈が入っているような印象。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

記事の本題とは関係ないのだけど、この手のUIデザインのカタログ化って、ユーザーの操作面を交換可能な変数と捉える発想が根底にあり、ABテストなんかもそこからきている。こういう性格は、モダンデザインのユニタリーな性格とは対立するものだとおもっていて、これが現代のウェブなりなんなりの「デザイン」を対象化することを困難にしているとおもう。ユニタリーでもないし常に変化しているから固有の境界がなく、分析しづらい。
https://note.com/itoh4126/n/nc991fd486030


でもこういうカタログ化はちゃくちゃくしと進行していて、ここ数年ではこのカタログ及びその結合原則について語ったものはデザインシステムと呼ばれるようになった。デザイナーの役割はあきらかに変わっており、統合的なモノを作ることではなく、生成的なシステムを形成することになってきている。

バウハウス的なモダンデザインのなかでは、やはりアートをプロトタイプにしているから、作家性というものがまとわりつくし、最終的に構成された「形=デザイン」が解体不可能な統合性を持っている必要がある。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。


大手新聞とかが6月の電通法改正を「クッキー規制」みたいに言ってしまうから、「Cookieを利用しないIDソリューション」であれば分析に使っていいみたいなデマを吐くやつがでてくる。
https://twitter.com/XadAqr/status/1662815523871285249

ニューヨーク近代美術館の元館長アルフレッド・バー・ジュニアのカタログは、1930年代には早くもアヴァンギャルドの年代記でありいわば教理集のごときものとなっていた。「美術家にとっては(略)伝統を歴史意識で置き換えることは、多様な可能性を絶えず選択しなければならないということである。あれではなくこの美学的仮説に従うとの決心は、芸術家としての死活問題である。過去の一方通行路からの美術の解放は、絶えざる不安と一体である。(略)」独自にこのことを予知したピカソ以来、美術は「個人が能力の限りそこから引き出すことを許された共有財産」なのである。そして個人はその共有財産に注釈を加えることも、したがって占有することもできる。つまり引用は新しい芸術的表明の伝達手段となる。
1987年の美術史家の本だけど、美術館にあるものや美術史上のイメージは引用可能なデータベースとして構成され、だれでも利用可能なコモンズである、というのはずいぶんシミュレーショニズムっぽい話で、80年代っぽい。この芸術的な方法としてのアプロプリエーションが、ピカソを起点に話を展開しているのは象徴的だとおもう。ピカソが利用したイメージにはトロカデロ民族博物館に入っていたようなモノがたくさんあった(たぶんベルティングはあまり意識していないとおもう)。 「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」が84年で、ウィリアム・ルービンは「部族芸術」を近代美術のカタログのなかに編入しようとしていたと言える、それによってピカソのアプロプリエーションを肯定的に把握しようとしていた。 ベルティングがシミュレーショニズムの理論家だとはおもえないけど、80年代がこういう時代だったようにはおもえる。モダニズム美術の歴史的な活力といったん距離ができ、美術史を引用可能なデータベースとして再構成しようとしていた、というように見える。 ルービンやベルティングにはポストコロニアリズム的なパースペクティブはないわけだけど、 cultural appropriation の話なども、この80年代的な意識の裏面を見ているような印象がある。