テスト用にあの手のLCDパネルを一つ二つ押さえとくかなあ…?
OpenBSD(uaa@), Ham(JG1UAA), Ingress(Lv14, RES), Japanese(Sagamihara-city, Kanagawa)
Another side: https://social.tchncs.de/@uaa
npub1rarr265r9f9j6ewp960hcm7cvz9zskc7l2ykwul57e7xa60r8css7uf890
Messages from this Mastodon account can read via mostr.pub with npub1j3un8843rpuk4rvwnd7plaknf2lce58yl6qmpkqrwt3tr5k60vfqxmlq0w
ん?このJYC024ってパネル、以前触ったSurenoo TFTのコマンド体系と似てるような…?(同じではなさそうだけど) https://ja.aliexpress.com/item/32908782846.html

やっぱあっちの液晶なのでGB2312が基本っすよねーそうですよねー https://www.aliexpress.com/item/1005004663713156.html

UARTでつながって、Shift-JISないしUTF-8な文字列を流し込むとイイ感じに表示してくれるLCDデバイスがあると良いなあ。
v3でもGB2312は通るので、フォントデータはGB2312ということになっているけどコードはShift-JISを投げつけるとかそういう芸当はできるのかもしれない(気持ち悪いけど)。 https://github.com/hagronnestad/nextion-font-editor/blob/master/Docs/Nextion%20Font%20Format%20Specification%20ZI%20version%203.md
あー、Nextion Displayのフォントファイル(.ZI)ってShift-JIS/UTF-8対応はFormat v6以降か。自分の持ってるコードはv3向けなのでASCIIのみ(ということにしておく)なんだよなあ。 https://github.com/hagronnestad/nextion-font-editor/blob/master/Docs/Nextion%20Font%20Format%20Specification%20ZI%20version%206.md
ブラウザの中にこういうのがブックマークされていたから、出しておきますね。
娯楽用アプリケーションの異機種間データ共有の試み (archive.org)
https://web.archive.org/web/20011214025714/http://chig.vis.ne.jp/m/misc01.html
これが、俺の、インターネット老人会だ!!!!
https://mzp.hatenablog.com/entry/2023/12/23/110149
原典がOpenBSD上でビルドできるなら、仮想マシン用意しなくてもテストできるのでは…?という気がしなくもないけど。
ってことは、原典との互換性はあるのかな。sampleはFUJIMI版から抜かれているから、Vine2.5仮想機(原典)→OpenBSD7.4機(FUJIMI)とかそういうテストを考えないといけないか。
ok、うまくいった。
uaa@framboise:~/z/sj3$ ./sj3stat 192.168.0.88
version : 2.08C%, times-stamp : Mon Mar 23 16:42:59 JST 1998%, 1 users.
(USER) (HOST) (FD) (CLIENT)
uaa framboise.uaa.org.uk 1 14192.sj3stat
uaa@framboise:~/z/sj3$
原典(今後、特に断らない限りはsj3-2.0.1.20を指します)がこうなので
include/Const.h:#define PortNumber 3000
google code版で3086へ修正したとかそんな感じですかね。
Vine機の/etc/servicesを直してみましょうか。
ん-、原典のsj3に対してFUJIMI-IM/sj3のsj3serv <IP>で状況を取ろうとするとserver deadになってる。さてどう問題を解いたもんかねえ…(まさかsj3statを動かすマシンの/etc/servicesを見てるんじゃないだろうな…?)
rv1103/1106って、既にrv1107/1108があってそれに類似している気がするから(根拠ないです)その延長線で考えていくと何か見えてくるものがあるんだろうか。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
idbloader.imgって、結局u-boot-spl.binに対応するモノという理解で良いんだろうか。なので、ディスク上のどこに配置したu-boot.binを読むか、というのもここを追うのが適当なのかなあ。
RHEL9.xだとTPM1.2サポートが切られるとか、Windows11も要件厳しいけどRHELも意外に厳しくないですか…?(エンプラ向けなのでそういうものなのかもしれないけど)
Red Hat Enterprise Linux 9.x と 8.x の違いまとめ (2022.1.9) https://takumi9942.net/blog/?p=2313
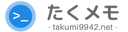
Luckfox Pico SDKはすんなりビルドが通ってる。build.shでenv, uboot, kernel. rootfsを構築した後にfirmwareを試しただけなんだけど。 https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico

ああいう場所で使うLinuxなので、好き勝手にいじれない(むしろいじってはいけない)というのがなあ…まあnot for meな環境なので近寄らないのが吉ってやつかねえ。
Enterprise向けなので、勝手にsshd止めてdropbearに挿げ替える訳にもいかんのか(別に最新版のsshdでも良いんだけど)。
対応している暗号化アルゴリズムが違うから、セキュリティを適切に弱めるなり新しいクライアントを入れるしかない。はい
RHEL8から変わった暗号化ポリシーの設定方法 https://blog.future.ad.jp/crypto-policies

発掘はしてないですよ…?(多分)
何か必要があった時のために確保しておいただけで…(多分)
VJE-Delta 2.5 Linux/BSDの動作要件、
Linux: Kernel 2.0.0以上、libc5 2.18以上ってあるんだけど…Vine 2.5のldd 2.2.4は流石に条件を満たしていないのでは。
これのためだけにまた仮想マシン増やすの…(地味に嫌がってみる)
@hadsn パッチを持っている人にとっては遺物なんでしょうけど…なんにもない(そして手に入れる術も断たれている)今となってはちょっとしたトラップな気がします。歴史的な資料にはなるのでしょうけど、完全な資料とは言いづらい。
FUJIMI-IM/sj3のsj3stat他各種ツールって、原典(sj3-2.0.1.20)と互換性ありましたっけ?あるならとりあえずVine 2.5上のsj3serv相手に色々テストできるなーって考えちゃうんですが。
VJE-Penのソースもあるし、と自分を納得させるも確かアレも公開されてましたよね…
VJE-Delta 2.5 Linux/BSD、オークションで実は落としてしまったんだけど…VACSのサイトにあった各種パッチが入手できない今となっては特級まではいかないけど呪物なのかもこれ。(だから誰も入札しないのか、それを知ってるから…)
[uaa@localhost uaa]$ nslookup localhost
Server: 203-165-31-152.rev.home.ne.jp
Address: 203.165.31.152
Non-authoritative answer:
Name: localhost
Address: 127.0.0.1
[uaa@localhost uaa]$
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
でもsj3 -H localhostはエラーなんだよなあ。sj3 -H 127.0.0.1は接続できる(!)のは何故…
sampleは動いてるけど、sample -H localhostとホスト名を指定しないと動かない。単にsampleとすると、Can't connect localhost:sj3servというメッセージが出る。
SJ3SERV=localhostで、sj3statは生きてるって返事してくれるけどsj3自体はまだサーバを見つけ出せない。とりあえず原典たるsj3-2.0.1.20をまずは動かしてみないと分からないことだらけなのだが…(昔使ってたはずなんだけど)
過去のメモだと/etc/servicesにsj3とポート番号を書けってあったけど…どうもgetservbyname()で/etc/servicesを見てるみたい。level1.c, comuni.cに書いてある。
Vine 2.5環境に入れたsj3、sj3servとsj3との通信がうまくいかないのかsj3を起動すると「Warning サーバーへの接続に失敗しました。」と怒られる。
一体どうやってsj3を使っていたんだっけ…?sj3serv他一式のインストール方法および使用方法を思い出す必要がありそうなんだけど。
Windows10の動くマシンもピンキリなんだろうけど、ゴミになったWindows10機に適当なLinux distro突っ込んでパソコン代わりにするのと、Raspberry Pi4辺りをパソコン代わりに使うのとどっちが良いんだろう。
RAM 4GBくらいのは捨てるとしても(まあこれくらいのスペックでも用途によっては使えるだろうけど)、8GBならまだ活かせるんじゃないのという気がして。
自然災害?
ウィンドウズ10サポート終了でパソコン2.4億台廃棄も=調査 | ロイター
https://jp.reuters.com/world/environment/53Y7LNRV6VOFVL7B2J44DOYF3I-2023-12-22/
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/KUAYBY2PX5P7LFKR7ZRUXK4P4Q.jpg)
マルミーニャみたいな12x12pxなフォント、ESP32な工作とかでの需要がありそうな気がする。
(単にTTFの皮をかぶっただけという可能性もあるからデータをよく見ないと分からないというのはあるんだけど)この手のビットマップな雰囲気のフォント、結構ベクトル化してたりするのでもにゃる。
TTFじゃなくてbdfとかfontx2形式など、生のビットマップ形式で配布してくれればより利用の幅が広がると思うんだけど…

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
Linuxでもopenpty()使えるなら、いっそのことこれだけ(posix_openpt()すら要らない)にばっさり整理しちゃうのはどうなんだろう
(とはいえ、FreeBSDはposix側に寄せようとしてる https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=pty&sektion=4 )
先人たちの通ったここを辿るのが良いのかなあ、uumでopenpty()対応してるってことは、sj3とか他でも(考え方が)使えるはずだし。
uumで/dev/ptsを使う http://www15.big.or.jp/~yamamori/sun/misc/
Mass patch to enable uum on FreeWnn-1.10-pl020 (2003/7/5) https://groups.google.com/g/fj.comp.input-method.wnn/c/xR2shXAxRJQ
