排除アートをSM用具に誤用する、とかは、この手の話とかなり繋がっているとおもっている。
https://pleroma.tenjuu.net/notice/AWdl9Pz4RvD52nrDSS
デザイナーが込めた意図とは無関係に、モノは開かれた存在だけど、排除アートが排除しようとするものは、「デザインの意図」の外部そのもの。排除アートというのは進めていくと、意図に満ちた空間ができあがるはずだとおもう。

排除アートをSM用具に誤用する、とかは、この手の話とかなり繋がっているとおもっている。
https://pleroma.tenjuu.net/notice/AWdl9Pz4RvD52nrDSS
デザイナーが込めた意図とは無関係に、モノは開かれた存在だけど、排除アートが排除しようとするものは、「デザインの意図」の外部そのもの。排除アートというのは進めていくと、意図に満ちた空間ができあがるはずだとおもう。
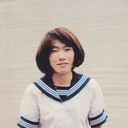

排除アートは、ホームレスの住処やスケートボーダーの遊び場を奪うという意味だけで問題なのではなく、ふつうの人がモノを誤用しなくなるような認知体制を作りだす、そういうデザインのトレンドだという点でかなりの問題がある。つまり、モノにはなにかの意図があり決まった用途があると認知するようになる。
道路は「移動するための場所」だから、地べたに座り込むのは誤用だ、という認知を生みだすこと。そのように、誤用を無くすようにデザインされていくこと。

文化盗用の話。
資本主義的な過程のなかで、モノの文脈が抜けおちていくこと自体に違和感があるってことなんだろうなーとおもいながら聞いている。
https://www.youtube.com/watch?v=vBpevpJNlDE


「アイヌ文化」という形で、境界付けられた「文化」というものも、資本主義の発達過程で生じるものという感じもある。マユンさんがもやもやしているのも、なんかそういう認知の枠組みのなかの「アイヌ」という問題な気はする。

「アイヌ」という名でもって客体化される仕組みが存在する、ということなんじゃないかと思ったり。これはアイヌに限ったことではないだろうけど。「和人/アイヌ」という区別は関係のなかで生じるけど、こういう関係を離脱した「アイヌ」という概念というかイメージというかが成立している、というような。

マイノリティを実在的な対象をもったカテゴリーだとする操作が、いろいろ問題をひきおこしているんじゃないかという気がする...
This account is not set to public on notestock.