棚単位で別々のお店が雑貨とか売るのは聞いたことあるけど,それの書籍版か.
棚一つ分の小さな“本屋”が78軒集まったお店 シェアする本屋「ブックマンション」に行ってきた - ねとらぼ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1908/09/news014.html
棚単位で別々のお店が雑貨とか売るのは聞いたことあるけど,それの書籍版か.
棚一つ分の小さな“本屋”が78軒集まったお店 シェアする本屋「ブックマンション」に行ってきた - ねとらぼ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1908/09/news014.html

中国著名芸術家、ドイツ離れる意向=「開かれた社会でない」、差別も:時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080901198&g=int
映画とアカデミック・ライティングがどう繋がるのか気になる
「アメリカの大学生が映画について論文やレポートといった「アカデミック・ライティング」を実践する場合に実際に使用している教科書です。①書くための準備→②どのように書くのか、とステップアップして実践できるように構成。③図解による映画用語の解説付き! 本書を読めば、学術的な論文・レポートが書けるようになります。指導者にも推奨」
映画で実践! アカデミック・ライティング - 小鳥遊書房 本が本を産む。 http://tkns-shobou.co.jp/smp/book/b432484.html
「作品と作者の人格は別」というのも何とも手垢のついた表現というか,それでなくとも結構ナイーブな見解の気もするけどどうなんだろう.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
@ncrt035
メナンドロスの現実描写(あるいはリアリズム)についてはこの本の第1章がよさそうだ.
Petrides, A.K.(2014), Menander, New Comedy and the Visual, Cambridge University Press.
https://books.google.co.jp/books?id=l1jeBAAAQBAJ
Notepad++で字数算えるの,TextFXプラグインなしでも[表示]->[概要]で簡単なのは計算できた.

じぇいさんと打ち上げで話した内容が普通に本にできそうな内容だった。盗聴しとけばよかった。(?)
大筋はいくつかあったけど、「もはやサーバー単位でのコミュニティはブレが出ている」というのが面白かったテーマ。たとえば、jpのLTLや空気感みたいなのが嫌いだけどjpで知り合った人たちは好きだから、jpのアカウントをべスフレに移してフォローインポートしてすべての投稿をunlistedないしprivateにしてやり取りするという話。べスフレはフレニコ同様LTL文化が強烈だけどサーバーは安定しているため、unlisted以下の可視性によりべスフレに波を立てることなくjpとイチャコラできるという寸法。
こういうサーバーを超えた人間関係(コミュニティ)がそれなりに普及してきているだろうというじぇい氏の見立て。さすがのフォロー大魔神
「ことによると~かもしれない」の意味で「~まである」っていうの何時頃から言うようになったんだろう,特に最近よく目にする.
「まとめサイト」っていうと少し前までは旧2ちゃんねるの任意のスレッドからレスを切り貼りしたアフィリエイト広告まみれのアレを指していたところ,最近では「○○について調べてみました……いかがでしたか?」定型文の無内容な検索汚染記事群を指して使うことが多い気がするが,その辺の指示対象の推移とか定義がよくわからんというのが若干引っかかっている.まぁ何にせよそれ以上分別の必要がないゴミであるには違いないが…
https://gnosia.info/@ncrt035/102604206042693099
いかがでしたか系業者ブログは、無意味に写真画像を使ってるのが特徴的かも?
日本語Wikipediaの「まとめサイト」の項(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 )がめちょ長い… ドイツ語WikipediaのAristotelesの項(https://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles )くらい長い…


おもしろそう
「義務教育って無償じゃなかったの? 学校や地域によって金額も項目も異なる保護者が学校に支払うお金の現状と、そこに至る歴史や法的根拠を一望し、納得できるあり方へ転換する道を提起する」
隠れ教育費|太郎次郎社エディタス http://www.tarojiro.co.jp/product/5935/
古典受容を専門に扱う雑誌Classical Receptions Journalの最新号.
Volume 11 Issue 3 | Classical Receptions Journal | Oxford Academic https://academic.oup.com/crj/issue/11/3
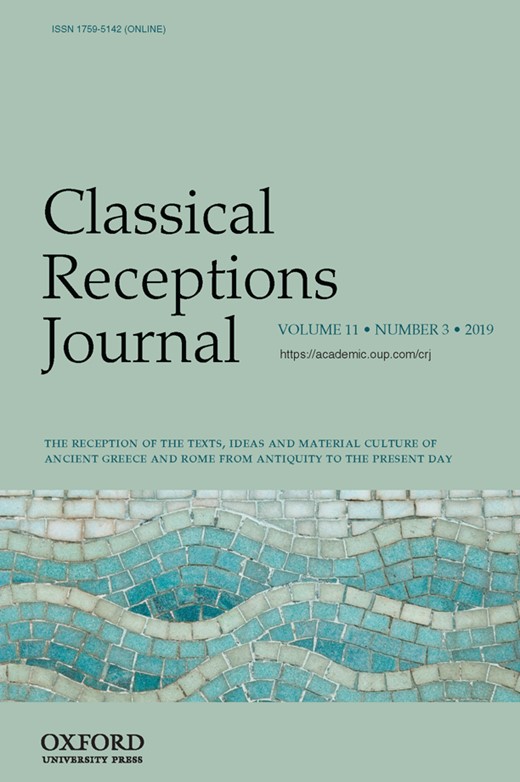
これの第2部が語源論に関するものなのでできれば読んでおきたい
Studies in Greek Lexicography https://www.degruyter.com/view/product/510601
良い文章は情理を尽くして展開されるのでそもそも論理国語と文学国語のような範疇自体に無理があるのかもしれない
面白かった「今、こうした是非善悪・理非曲直を有耶無耶にした対応をとると、組織へのロイヤリティを失くした部下が離れて行ってしまうのはまだいい方で、悪ければパワーハラスメントで訴えられるリスクが生じます」
クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/08/11/221232

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
2期制作決定!プロデューサーに聞く、アニメ『ゾンビランドサガ』誕生秘話! | Cygames Magazine | Cygames https://magazine.cygames.co.jp/archives/1714

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
Lucr.DRN 5.65でOとQがmihiとnihilという割れ方をしている
むっ「カフカの作品『田舎の婚礼準備』の3種類の草稿や、カフカがヘブライ語の学習に使用したノート、親友のマックス・ブロート氏ほかの友人との間の書簡、スケッチ、旅行記等が含まれます」
イスラエル国立図書館、カフカの手稿類の入手を発表:デジタル化して公開予定 | カレントアウェアネス・ポータル http://current.ndl.go.jp/node/38788
データ活用社会創成シンポジウム(9月2日) | 東京大学 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0310_00015.html

古典語教育が哲学科にアウトソーシングされてきた(https://twitter.com/camomille0206/status/1160328736727638016 )という話は,ギリシア語をやる人はわんさかいても,ラテン語をやる人・やれる場所が極端に少ないという現実をよく説明できる.
今週の朝日の読書面に安田さんの『役に立つ古典』(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064072452019.html )が載るらしい
次回の読書面|好書好日 https://book.asahi.com/reviews/nextweek/

何度となく言っているが,労働に対価が欲しいのではなく生存に対価が欲しいので,金を取って何かしようというインセンティブが発生しにくい.
翻訳作業が原文解釈のフェーズから和文の推敲へと移ると,「何故その変更を加えたか」が次第にわからなくなって堂々巡りに陥ることがままある.
たとえば,はじめ段落の終わりを少し強調的に「~なのである」と結んだが,読み返すと浮いて感じるので「~である」に改めたものの,その修正の意図を忘れて後日再び「~なのである」に戻してしまうなど.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
要は加えた修正処理とその意図・目的をセットにしてログを残せればいいので,自分しか使わない文書ならgitで管理して適当なコミットメッセージつけとけばいいのではだが,他の人間が噛んでくる場合そうもいかなくてあわわになる.
γεとτεは小文字だとそうでもないが大文字だとΓΕとΤΕで非常に混乱しやすく,一方を他方に誤記したり,またそのような誤記を想定して修正を提案したりすることが非常に多い.
若い人がメールを使わなくなった,とは思わないけど,今アドレス帳を見たら年齢問わず相当数がGmailだった.
これ(https://github.com/ncrt035/Orbis )を自鯖で動かすのにGoogleマップのAPIキーが要るのでアカウント作れと言われたから一応Gmailも開通しているが全く使ってないな…

日本語Wikipediaへの壊れたリンクを踏んだら異次元に飛ばされた
Å…¬æ£ä¸–ç• - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%C3%85%E2%80%A6%C2%AC%C3%A6%C2%AD%C2%A3%C3%A4%C2%B8%E2%80%93%C3%A7%E2%80%A2

オチが秀逸だった
もしも総理が玉音放送を現代語訳したら - ナナオクプリーズ http://7oku.hatenablog.com/entry/2019/08/15/115916
《母の花を食む見張り所》ματέρος ἀνθονόμους ἐπωπάς (Aeschyl. Suppl.539)で《花を食む母が(アルゴスから)見張られていた場所》を表すのは,ふーむという感じ.
買い物に行けなかったので鯖の水煮缶に玉ねぎとマヨネーズ、レモンを混ぜてパンに挟んで食べた.
5月にウァッロー『ラテン語考』の注釈・翻訳付きテクストを出したDe Melo氏が,この仕事にかかっているときの紹介記事.
学生時代にはラテン文法家たちの著作をあまり価値あるものとは思えなかったという告白から始まり,そのため『ラテン語考』をやらないかとオックスフォード大学出版局から話があった際も返答に時間を要したこと,しかしこの作品に取り組むうち印象は変わったことが述べられていて,『ラテン語考』そのものと著者ウァッローの簡単な紹介も含まれている.
Varro's 'De lingua Latina' ('On the Latin language') https://blog.philsoc.org.uk/2016/12/03/varros-de-lingua-latina-on-the-latin-language/
9月刊行予定らしい
勝又基編『古典は本当に必要なのか、否定論者と議論して本気で考えてみた。』(文学通信) - 文学通信 https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-16-6.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
『荘子』の翻訳はうちには岩波文庫のしかないから他のも入手したい.ちくま学芸文庫から興膳先生の訳も出ているのだね.
勝手気ままな訳書紹介―『荘子』 - 達而録 https://chutetsu.hateblo.jp/entry/2019/06/04/120000
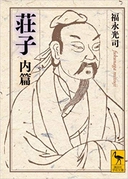
興膳先生というと,私が学部生の頃に,吉川幸次郎先生が途中まで刊行していた『杜甫詩注』を編集補筆して岩波書店から再スタートさせるというのを始められていて,「これはすごいものが出るなぁ」と驚いた記憶がある.

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
「1923年から1963年の間に出版された書籍の著作権状況を分析……調査対象となった書籍のうち実に80%がパブリックドメインとなっていることが判明し、人々が思う以上に多くの書籍がひっそりと無料で入手可能となっていたそうです」
でひょえーとなった後,
「ロサンゼルスのブロガー兼プログラマーであるレナード・リチャードソン氏は、新たにネット上にアップロードされたパブリックドメイン書籍の情報を発信するマストドン(ミニブログ)アカウント「Secretly Public Domain」を作成しました」
でまさかのMastodonが出てきて椅子から転げ落ちた.
https://gigazine.net/news/20190808-download-free-public-domain-ebooks/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
これは無知なのですが液タブってゆーのはPCに繋いでお絵描きするものなのですか
@ryecroft
なるほど,基本的にマルチモニター環境を作るような感じなのですね.iPadのようなタブレット端末の利用と混同していました(いずれにせよ熱くなるのはつらそう…)
@ryecroft なるほど.少し前に中華製液タブで廉価で良さげなのがあると仄聞ましたのでそれも気にはなっていますが,私も当面板タブですね(ペン先問題も慣れてしまうとそれほど不都合を感じませんですし…).
イタリア語で《タイプライタを打つ》をdattilografareというが,これはギリシア語のδάκτυλος《指》とγράφω《書く》から作られている語だ.
こんなん英語では言わんよなぁと思って辞書を引いたがdactylographyは《指紋学》という意味なのだそうだ.へぇ.
一応,現代ギリシア語でもδακτυλογραφώという動詞があるらしい.
https://en.wiktionary.org/wiki/δακτυλογραφώ

δακτυλογράφωないしδακτυλογραφέωで《指で書く》という意味に読ませて,フリック入力することの新造語として用いたい気持ちがある(ない).
「減速主義」,そういうのもあるのか…
スローライフが、むしろ資本主義を「加速」させるという皮肉な現実 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66544

大事な指摘ですね.こういうところに目を瞑り続けているから「左派的なもの」に対する反感はいつまでもなくならない.
「左派的な「啓蒙」主義は多くの場合、〈減速のオアシス〉が、異なる社会的階級にとって異なる開かれ方をしていることに目を向けることなく、「良心的な市民」の倫理観を振りかざす。減速のオアシスは、経済的余裕のない人間にとってはアクセスすることが極めて難しく、ますます「持てる者」の特権になりつつあるという構造的問題にはしばしば目が瞑られる。その代わりに、減速こそが望ましく、個々人が各自の責任において達成すべき規範として提示される」
「右派と言われる加速主義も左派と言われる加速主義も,資本主義の経済システムがこれから終わるだろうという歴史目的論を土台にしているところがあります.その共通理解の上で,資本主義は時代錯誤だから早く技術シンギュラリティに行こうだとか,もしくは共産主義的な民主主義に行こうだとか,話が枝分かれしていきます……右派加速主義はただスピードと強度を追求し,最終的には技術文明がシンギュラリティに回収されて終わります.それに対し,左派加速主義はスピードにベクトルがないといけないと考えるのが特徴的なのではないかと思います」(『現代思想』2019年6月号「加速主義の政治的可能性と哲学的射程」からブロイ氏の発言 p.18)
加速主義の右派と左派について
https://gnosia.info/@ncrt035/102216931386984506
「優秀な学生が大学院に進まなくなった」とお嘆きになるのは結構だが,度が過ぎると「今大学院にいる人間は大して優秀ではない」を含意するようになるので程々にしませう…
「優秀な人には大学院に進学してほしい」と「大学院には優秀な人に進学してほしい」では意味が全然違うので日本語はむつかしいね(すっとぼけ
オウムと同じ流れなんだろうが何も学ばない人々が面白がって報道し面白がって支持するんだろうな
「立花氏のパフォーマンスは、ある種の”怖い物見たさ”を誘い、格好のネタになるらしい……”N国コメディーショー”を、やはり面白がって、またはNHKにお灸を据えるいい機会だととらえて眺めている人々がいる」
メディアはN国の取り上げ方をよく考えて(江川紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190816-00138652/

畑中さんの新刊が6月に出ていた
「20世紀初めのほぼ同じ時期に、イギリス人作家チェスタトンと、当時はまだ官僚だった民俗学者の柳田国男は、ほぼ同じことを主張した。それが「死者の民主主義」である。
「その意味するところは、世の中のあり方を決める選挙への投票権を生きている者だけが独占するべきではない、すなわち「死者にも選挙権を与えよ」ということである」
死者の民主主義 - 株式会社トランスビュー http://www.transview.co.jp/smp/book/b458232.html
投資家の滝本哲史さん死去 47歳 京大客員准教授 「僕は君たちに武器を配りたい」 - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20190816/k00/00m/060/203000c
AWOL - The Ancient World Online: Heidelberger Dokumentserver: Hellenic Languages and Classical Greek http://ancientworldonline.blogspot.com/2019/08/heidelberger-dokumentserverhellenic.html
劇の中のギリシア語の小辞への新しいアプローチとのこと
Language on stage. Particles in ancient Greek drama - heiDOK http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/23002/
(ひもとく)本棚の常備薬:3 古典で社会を考える 木庭顕:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S14142182.html

これが文科相の座右の書というからお察しなんだよなぁ…
https://twitter.com/shiba_masa/status/1162493060254597121
文部科学相 柴山昌彦氏: 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO48632590W9A810C1MY5000/
下記人格脆弱性のためVtuber界隈からははなれてしまったというのがある
https://gnosia.info/@ncrt035/102053220480014916
プリーニウスの叙述順序について,すでにカルヴィーノが重要な指摘をしている.
「陸に住む動物を一望する巻八の冒頭をかざるのはゾウで,プリニウスはこの動物にもっとも長い章をあてている.いったいどういう理由でゾウが優先されるのか.それはゾウが最も大きい生物だからだ(プリニウスの論述は重要なものから順次,述べられるのがふつうだが,それがしばしば物理的に大きいことと合致している)」(カルヴィーノ(須賀訳)『なぜ古典を読むのか』「天,人間,ゾウ」p.77-78)
絵も文章もずっと直してると感覚が麻痺してきて論理が飛んでてもわからなくなってくる