マラソン,人のいない深夜とかにやってほしい
ギリシア語はアクセント記号や気息記号など文字の上部に色々な印がつくので,引用符に“ ”や‘ ’を使われると読みにくくなるのだが,結構見かける.« »を用いる方が望ましいと思う.
左はこの前出たM.L.West校訂『オデュッセイア』で“ ”の中でのさらなる引用に‘ ’を使っている.気息記号やelisionが起きた時の記号とよく似ている.右はAlberti校訂のトゥーキューディデース『歴史』で« »が使われている例.


関係のある学・研究会で「ご連絡はFacebookまで!!!」のようにあって「なるほど信仰上無理だな」とスルーすることが一度ならずあって,それで結構な機会を損失している気もするけど無理なものは無理というのがあります.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
届いてた崇文荘のカタログを見ている.キューナーのギリシア語文法4巻揃いで35000円は買いかもしれない.高い.
ヴァルデ・ホフマンのラテン語語源辞典が10000円の方がお買い得かもしれない
quamvisは接続法,quamquamは直説法と用いるのが基本で,ただしその逆の例も珍しくはなく,時代が下ると両者の混用が進む,というザックリした認識だったけれども,もう少し詳しく見るとquamvisと直説法の用法は韻文だとルクレーティウス以来結構見られるのに対して古典期の散文では稀という分布になっているらしい (Hofmann-Szantyr 604).
「何かこういうのを作りたい」というのがあると無い時間を絞って日曜プログラミングをする動機付けにはなる反面,「まぁ動いているし……」に流れそうになる誘惑が生じる.もっと「artとしてのプログラミング」をちゃんと理解していきたい感がある.
自分でどんな記事を書いたか思い出せなかったので検索したらπαραγραφήの説明が途中で切れている.当初はもっとシンプルな記述を想定していたので,データベースの方で許容する文字列の長さをあまり大きく設定していなかったのが原因と思われるので今度直しとこう.
https://lggi.stromateis.info/search.php?opt=start&fld=Word&kw=paragrafh&page=0
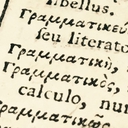
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
少し以前に大学の資料の配架場所についての嘆きを見た記憶があるが,教員や特定研究室配架になっている場合,学外はもちろんとして同一学部内でも他の研究室では閲覧しに行けないし,ことによるとその研究室構成員でも利用にはばかりがあることも少なくない.「研究資料の軟禁」が進んでいる感じ.
言ってたら早速この案件にぶち当たって頭抱えてる
https://gnosia.info/@ncrt035/101255220669750810
政治的発言が問題なのではなく,どのように個人情報を抜かれ監視されているかもわからない媒体で政治的発言を行うリスクの方を考えるべき.
「今年も残り1週間を切ったなどというフェイクニュースが流れてきてリテラシーが試されている」今年も同じ事態に遭遇
https://twitter.com/ncrt035/status/945500441818800131
「研究と勉強は違う」というありがたいお説教を耳にすることがあるけれども,まさか「よく勉強なさいましたね,もう免許皆伝ですから後は研究だけおやりなさい」とはならないので,「研究は絶えざる勉強に支えられて成り立つ」というのが実際ではという印象がある.
古典詩の無理誇張(adynaton)を扱った文献にDutoit, E.(1936), Le Theme de l'adynaton dans la poesie antique, Parisというのがあるらしいことがわかった.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ある事柄の不可能性を強調するために,他の不可能な事柄を比較に持ち出すのが「無理誇張adynaton」なので,持ち出される事象にどんな発想を仕込めるかが腕の見せ所である反面,文脈を共有しない読者には下手をすると話が明後日の方へ飛んでいったように聞こえてしまいかねない.
https://gnosia.info/@ncrt035/100297617122669295
イタリア語原書裏表紙の紹介文を訳してみた.
「ギリシア・ラテンの古典は,パピルスの巻物から羊皮紙写本へ,印刷本からデジタルライブラリへと時代により異なる書記媒体を介して長い道筋を経由してきた.写字生たちの時代には,文献学者や読者はめいめいの必要にしたがって古代のテクストの複製や抜粋,翻案といった仕事に絶えず従事した.こうした継承作業は喪失や分散をもたらしこそしたが,しかしまた思想や科学,文学や芸術を育むことでヨーロッパの文化に本質的な貢献を果たしもした.
本書は,古代後期から「新旧論争」へ,そしてインターネットにより火蓋を切られた画期的な変容に至るまでの古典作家の受容を最大限幅広く描き出すことにより,テクストの継承ならびにそれを可能にした物質的媒体の歴史を視野に収め西洋の歴史における古典伝承の変遷をたどりなおしたものである」
(出版社のページにも同じもの有 http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843065325)

英語版はなんかウェブサイトまでできてるぞ
Classics from Papyrus to Internet
http://sites.baylor.edu/papyrustointernet/
どうも英語版はイタリア語の単なる翻訳ということではないらしい.
目次を見ていると特に第1章,第2章,第6章のタイトルの違いが目にとまる.
1. La conservazione dei testi > Writing and Literature in Antiquity
2. La trasmisione manoscritta > Grammar, Scholarship, and Scribal Practice from Antiquity to the Middle Ages
6. I classici nell'età della modernità > Tools for the Modern Scholar
やはり英語版も買うかーという気持になっている(はよ買え)
結局そのプロジェクトに contribution できるかどうかってそのプロジェクトのプロダクトをめっちゃ使ってて出てきた問題(ドキュメントが……とかバグが……とか)を issue 上げたり修正したりできるかどうかって感じがある
なるほど「今のプログラマが育つ環境のリアルは、親方が弟子に伝授するという中世のギルド制度に近いのではないか、というのが界隈を見渡した際の予想としてある」
プログラマという現代の傭兵 - mizchi's blog
https://mizchi.hatenablog.com/entry/2018/12/26/103000

Tootdonからの通知が正しく飛んでない.pawooの方からはちゃんと飛んでくるので自鯖の問題と思われるがはたして
めっちゃいいですね…
「当初の目論見では他人の遺したゲーム攻略メモを見て、そのゲームを攻略し追体験するつもりだった……驚きの勘違いをしていたわたしは、この試みが『ゲームの攻略メモを見てゲームを攻略する』ではなく、『ゲームを攻略してからゲームの攻略メモを見返す』という振り返りの作業なのだとようやく理解した」
|とある女性が投稿した「亡き父親のゲーム攻略メモ」を見てゲームを攻略するということ。彼はなにを解き、わたしはなにを辿ったか http://news.denfaminicogamer.jp/kikakuthetower/181226
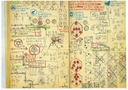
「誰かに見せるために書かれたわけではないもの」は却って無限の興味を引きつける
Ornella Volta編集によるエリック・サティ著作集の第1部が「他人のために書かれたもの」なのに対して第2部が「自分自身のために書かれたもの」だった.
外国語のテキストもCD付とかよりパスワード入力して音声データ落とせる方が便利ではと思う
日本名は9割9分9厘覚えてもらえない上に間違えられる(先日もそこそこ長い付き合いのところから間違った宛名書きのものが郵送されてきてげんなりした)ので,今後はギリシア名で通すかという気持ちがある(ない
今年は「どうも,私がニーケーラトスです」という挨拶をする破目になったことが何度かありました
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
interpolationの訳語は毎回悩む.色々な訳例を見たことがあるが,「テクストに後から手が入って真正でない要素が入り込む」という事態を言い表したいから,《改竄》が落としどころではないかしらんと思う.
本来的には「差し挟んで手を加えること」なのだろうけれども《改変,挿入》あたりだと適切な操作による場合も含んでしまう感じなので.
ウェルギリウス『アエネーイス』のトイプナー版の第2版が出るようですね
https://www.degruyter.com/view/product/525036
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
スウィフトの『書物合戦』について.面白い.
「『書物合戦』には蜂と蜘蛛(くも)との争いというアレゴリー(寓話(ぐうわ))が描かれている。蜂は古代人のように自然のなかから養分をとり,それを美しい翅(はね)音に変える。いっぽう蜘蛛は近代人のように,汚れた餌を食い散らかし,自分の排せつ物から伽藍(がらん)のようなウェブ(web: 蜘蛛の巣)を作る」| 『情報管理』60巻11号から
https://doi.org/10.1241/johokanri.60.819
『書物合戦』は翻訳もあるんだね.
山本和平訳『書物合戦・ドレイピア書簡 : ほか3編』(現代思潮社,1968)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I000362334-00

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ご専門は何ですかと尋ねられて社交辞令にもかかわらず真面目に答えると空気の読めない早口オタクになってしまうので,(1)同業者向け,(2)分野は違うが研究的な事柄に理解のある人向け,(3)それ以外の3パターンくらい回答を用意しておくといいかもしれない.
一件全く納まる気配のないものが残ったが他は大体年内にしておくべき仕事は終わったのでよしとしようじゃないか
そういえば,古代の地名をGoogleMaps上に表示するというやつを作りました.数はあんまりないけどよければ使ってみてね.
https://stromateis.info/orbis/index.html

クセノポーン『アナバシス』7.5.14では黒海西岸のサルミュデーッソスに到着したところで,「ここで多数の寝台や箱や書物,その他船主たちが木製の容器に詰めて運んでいたさまざまな品物が見付かった」(松平訳)と報告されていて,このあたりにも書物が流通していたことがわかる.
もしかすると古典文学の中に一定の役割を持って描かれる虫類は,人間の文明的活動と何らかの類推が成り立つ生態をもっているのかもしれない(蝉=詩人,蜜蜂=社会の形成,蜘蛛=織物).
前バス停でバス待ってる時に『オトッペ』のシーナちゃん大人版みたいな感じの人がいてめちょかっこよかったのを思い出した
上手い人の絵は急所のみ描き込んであって他は観察してみると驚くほど簡単に済ませてあることが少なくない.
作業の効率化と労力の削減という以上に,全体の情報量の適切な管理が行われている.
論文についても同じことが言えそう.
明晰な叙述が行われているものは,詳しい引証の類は全体の主張にとって枢要な部分に限り,それ以外は思い切って刈り込んであったりする.さりとてそれで調べを怠っているわけではないので,その枝葉の部分をつかまえて「ここの記述が詳しくない」と因縁をつけたところで,何が重要かを理解していない人間の所業となってしまう.
もちろん,「わかったことは全て書く」方針のものも資料として独自の揺るぎない価値を持つものであることは確かなのだけれどもね.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。