豚トロのスモークがあったので赤ワインと食べてる
「氾濫や、またシケリア、アイオロス諸島並びにピテクーッサイで起きたとされるような災害の原因として我々は異変を述べたが、そのような異変に対して動揺しない心を持つために、それ以外の地域に在るもしくは生じた、これらと似た事柄を他にもなお併記するのは価値のあることである。というのもそうした事例が集まり目の前に示されれば驚嘆の念は静まるだろうから。今なお、尋常ならざる事柄に遭うと人々は感覚を乱され,自然に生じる事柄と生全般についての無経験を晒すことになるのである……」ストラボーン『地誌』1,3,16.
πρὸς δὲ τὴν ἀθαυμαστίαν τῶν τοιούτων μεταβολῶν, οἵας ἔφαμεν αἰτίας εἶναι τῶν ἐπικλύσεων καὶ τῶν τοιούτων παθῶν, οἷα εἴρηται τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν καὶ τὰς Αἰόλου νήσους καὶ Πιθηκούσσας, ἄξιον παραθεῖναι καὶ ἄλλα πλείω τῶν ἐν ἑτέροις τόποις ὄντων ἢ γενομένων ὁμοίων τούτοις. ἀθρόα γὰρ τὰ τοιαῦτα παραδείγματα πρὸ ὀφθαλμῶν τεθέντα παύσει τὴν ἔκπληξιν. νυνὶ δὲ τὸ ἄηθες ταράττει τὴν αἴσθησιν καὶ δείκνυσιν ἀπειρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων καὶ τοῦ βίου παντός…
Lexicon Grammaticum Graeco-Iaponicum ギリシア語文法用語辞典
β版(微修正済)公開しました.
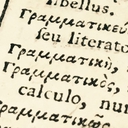
幾つか語彙の追加と,勘違いして間違った記述になっていたところを修正した.決してスナネコしていたわけではない…
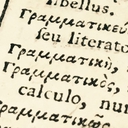
これ,検索オプションを「部分一致」「語義」に指定すると日本語→ギリシア語辞典的にも引けるように軽い気持ちで作ったけれども,そのようになっていると,どんな日本語を当てるかということに限らず,同系列の語にはなるべく一貫して同じ語を当てようとか,括弧類で語をぶった切らないようにしようとか普段しない気遣いが生まれる.
キログラム原器の話聞いてて思い出した.
度量衡関係の古代文献というと,プリスキアーヌス作と伝えられるが恐らくはレミウス(あるいはレンミウス)・ファウィヌスの手になる『重さと計量についての詩 Carmen de ponderibus et mensuris』という,ギリシア・ローマの計量単位について綴った詩が200行ちょっと残されている.あれも面白そうなのでいずれ読みたい.
あんまり他人のミスをどうこう言いたくない方ですが,今読んでいる本のギリシア語・ラテン語の引用文の間違い率が非常に高く,原本が入手できない文献からの引用の意味がどうしてもとれず誤字を疑って確認したところ案の定だった.照合できたからよかったもののGoogle Booksなかったら詰みかけてたかもしれない.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
眼球(白目)の色は肌色に寄せるのが最近の流行の気がするのとそれはそれでイケてる感じではあるがくっきりしているのも好きなので悩む🤔

さっきドイツ語の本で数字の誤りを見つけて,正しくは「91」であるものが「17」になってしまっていたのだけれども,「何故?」と考えた結果,手書きのメモかなにかの段階でこういう取り違えが起きたのか知らん.

邢東風「仏典に見られる「大地震動」」『桃山学院大学総合研究所紀要』36, 2010: 179 - 194.
https://ci.nii.ac.jp/naid/110007651438
仏典の中での地震の原因記述の一つに風があるのは面白い.西洋古代においても地震の原因を地中の風(気息)に求める説が有力だった.尤も,仏典の場合は強い風が火,水,大地と連動的に動かすことによるもののようだ.
地震はそれ自体が一つの災害であるため多くの場合凶兆として取り扱われるが,仏典においては吉兆とされる解釈が目立つのは興味深い.そういえば仏語の六種震動も仏が説法するときの瑞相(吉兆)とされる.
「地震は一種の自然現象であって,良いものとか悪いものとかと言うことはできない.しかし,地震はしばしば人類に多大な危害をもたらしたため,地震を一種の厄災とすることが一般的である.少なくとも,地震を吉祥とみなすことはないであろう.しかしながら,仏教においてはその一般的地震観と違い,地震は必ずしも災難とはみない.もちろん,厄災とみなす地震記録もみえるが,ある種の吉祥とみなす地震の方が多い」(p.189)
Kenneyの注釈に教えられて気づいたけどvivatusという単語はルクレーティウスとフェストゥスにしか見えず,Oxford Latin Dictionaryには採録漏れしている単語だ(Lewis & Short, Georges, Forcelliniには入っている).
というか英語でantonymは《対義語》を意味することになっているけれどもギリシア語のἀντωνυμίαとかἀντώνυμονは《代名詞》だものな… ἀντι-が《対立》ではなく《代替》の意味でὄνομαが《名詞・形容詞》なのでそれはそうという感じ(pronounの元のラテン語pronomenのpro-も《代わりに》という意味だから対応している)
#gloss_gramm
1867年にSmithという人が出したSynonyms and Antonymsという本(OEDが拾っているantonymの最初の用例)の序文では,antonymという語がギリシア語由来で本来「代名詞」を意味したけれども,文法的な術語としてすでにラテン語由来のpronounが通用している以上,ギリシア語の用語を同じ意味で採り直すのは無駄だから,ここでは文法的な意味ではなしに用いていると述べている.
https://catalog.hathitrust.org/Record/008675648
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ギリシア哲学30講 人類の原初の思索から(上) - 株式会社 明石書店
http://www.akashi.co.jp/smp/book/b379622.html
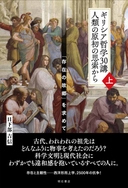
DNS, よくわかりたさがあるので気になる
SBクリエイティブ:DNSがよくわかる教科書
https://www.sbcr.jp/products/4797394481.html?sku=4797394481
同じ本の異なる版を文献表でどのように表示したいか自分でもいい感じのイメージが形成できないので手が止まるなどしている
文献表を幾つかのジャンルごとに分けて出力したいとき\printbibliographyのオプションに[keyword={hoge}]とかするわけですが,.bibファイルに書くときのデータ項目はkeywordsで複数形なの割と罠じゃないですか…
LaTeXで文書を書いてみよう/Introduction to LaTeX - Speaker Deck
https://speakerdeck.com/gnutar/introduction-to-latex

コッコくん役の県庁職員の人,北海道の出身だったんだ「実は近野さんは北海道釧路市出身で、東京の広告関係の会社から佐賀県庁に転職しました」| 佐賀県の自虐、ついにゾンビまで…県の担当者がケロッとしている理由 - withnews(ウィズニュース)
https://withnews.jp/article/f0181122000qq000000000000000G00110601qq000018363A

植物園にいったら今日は入園料無料だったので温室料金だけで全部見られた.ソーセージの木に実がなっていた.

ソーセージノキ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8E%E3%82%AD

よくいくパン屋のカレーパンが常に売り切れているのですでに幻の存在となりつつある
帰納的アプローチと演繹的アプローチ,その長短の説明などとてもわかりやすく面白い記事だった | Google最新技術「BERT」と「東ロボ」との比較から見えてくるAIの課題 « ハーバービジネスオンライン
https://hbol.jp/179474

いいないいなー | 執筆活動を支える技術 #ruby超入門 - Qiita
https://qiita.com/machu/items/4a133e83f58f82459e56

朝から10回くらい「今日は土曜日」って言い聞かせてるんだけど脳が日曜と認識する
オリンピックと万博で疲弊した東京・大阪を蹴散らして佐賀が首都になるところを見たい
最近ようやくDeufertの新しいルクレーティウス校訂版への註釈を見始めた.さしあたり3巻444行の†incohibescit†は1977年のEdenのincohibentistがよいのではないかというコメントがしてある.
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/366359

学術書の索引部分を見ていると,事項索引や一次資料の引用索引くらいまで分かれているのは割と普通として,たまに学者名索引が付いていることがあって,読んでいる本の偏りもあるかもしれないけど割とイタリア語の本に多いと思う.
「ある学者の所説について著者がどう考えているかを確認したい」という,どちらかというとかなり専門的な需要に限られるが,これがついていると助かる場面も少なくない.
引用時の著者名をsmall capsにするため\cite命令を再定義しようとガチャガチャしてたらスタイルファイルにすでにscauthorsという便利なオプションが用意されていたときの顔をしています