恩讐,構成としては dvandva だ.
1章6節「隠遁者から革命家へ――『意味の論理学』におけるストア派哲学と賢者像の変貌」をちょっと読んでみたいね
ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/smp/book/b496851.html

これは大学にいて強く感じるところだ RT
「今は「トップとツーカーで情報が真っ先に入ってくる」というのがウリになる時代だしな。何かを作りだす人間よりも、「トップとつながっている」という方が偉くなるし、評価される」
https://twitter.com/desean97/status/1233142315591454720
カミュの小説「ペスト」在庫切れ相次ぐ 伝染病の脅威、後手に回る行政 現状と重ねてか - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200227/k00/00m/040/366000c

時代は違うけど,マンゾーニ『汚名柱の記』も読んでほしい
https://gnosia.info/@ncrt035/99931307201862537
This account is not set to public on notestock.
This account is not set to public on notestock.
1200人以上の全社員がリモートワーク。GitLabが公開する「リモートワークマニフェスト」は何を教えているか? - Publickey https://www.publickey1.jp/blog/20/120066gitlab.html
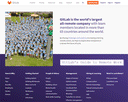
「鬼才」に比べて「奇才」は,「奇」とついているのに,「まぁ精々人間的なレベルね」という感じになってしまう残念さがある.
鬼才というと李賀を思い浮かべる.
「「李賀は鬼才と呼ばれた。この言葉は、かれの為にできた。他の文学者をさすことは、中国においては、ない。鬼は日本語のオニとはちがい、死者、すなわち亡霊を意味する。鬼才とは、幽霊や妖怪など超自然の事物によって、鬼気せまる神秘な雰囲気をかもしだす異常感覚者をさす。鬼才の語は、かれの死後200年を経て、宋代の随筆集『南部新書』に、「李白を天才絶(最高の天才)となす、白居易を人才絶となす。李賀を鬼才絶となす。」とはじめて記される」」
二十にして心朽ちたり… http://hon-bako.com/bookbox/bookbox_majo/%e4%ba%8c%e5%8d%81%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e5%bf%83%e6%9c%bd%e3%81%a1%e3%81%9f%e3%82%8a/
「鬼籍」というし,鬼はまず死者や亡霊のことを意味するから,「鬼才」「鬼工」とかの「人のものとは思えない,人力を超えた」の意味は δαίμων 的なものに通じるとは言えるかもしれないが,やはり並べるのはおかしいな.
This account is not set to public on notestock.
あれ,でも δαίμων を字引でひくと一応「死者の魂」の意味になることもあるらしい.LSJ には後代用法として departed souls や δαίμοσιν εὐσεβέσιν, = Dis Manibus, パウサニアース(Paus.6.6.8)の用例には ghost の訳語を振っている.
性格のはっきりした「神」としての θεός に対して δαίμων はもっと漠然とした捉えどころのない人知を超えた存在を意味しうるので,時に「(どう転ぶか分からない)運」として δαίμων ≒ τύχη にすらなる場合がある(cf. εὐτυχής, εὐδαίμων いずれも「幸運な」という形容詞).
なのでギリシア語の εὐδαίμων「運がよい,巡り合わせがよい」は,「つき〔=憑き〕が良い」と捉えるとイメージしやすいのではとかねてより思っている(むしろ日本語の「(幸)運」と言う意味での「つき」の語源がよくわからない).
「運がよい」というのは精々その瞬間に順境にあるに過ぎず,盲目的な人間の側から見た評価であって,その後にどんな転落があるかもわからない不確かなものだから,「幸運である」ことと「幸福である」こととは違う.
https://gnosia.info/@ncrt035/103158667513918868
「人間死ぬまでは,幸運な人とは呼んでも幸福な人と申すのは差控えねばなりません」(松平訳)というヘーロドトス(『歴史』1.32.7)の言葉を思い出したが,「幸福な」はὄλβιοςで「幸運な」はεὐτυχήςなんだね.
ὄλβιοςは「幸せ,富(物質的・現世的な幸福)」(ὄλβος)から来るのに対して,εὐτυχήςは偶々その時に「巡り合わせ」(τύχη)が良いというに過ぎず,運は絶えず動くものだから一時的・流動的な幸運を意味している.
「(どう転ぶか分からない)運」が τύχη であるのに対して,割り当てられた「定め」としての「運命」ないし「宿命」は μοῖρα と言うが,これも考えようによっては,同じ対象を盲目的で有限な人間の目から見るかすべてを見通す神の目から見るかという視点の違いとも言える.
このギリシア語の τύχη / μοῖρα 関係と――全く同じではないが――似た構造が,ラテン語の場合は fortuna と fatum の間に認められると思う.「運の女神」として神格化した場合の Τύχη は Fortuna に対応している.
「ウィルスは某国の陰謀である」というような風説すら出ている中で,「マスクもせずに動き回るとは怪しからん」と私刑が横行すれば,いよいよもって「ペスト塗り」なる架空の罪状で無実の人を拷問にかけ処刑した『汚名柱の記』の世界そのままになってしまう.
https://gnosia.info/@ncrt035/99931350811429896
イタリアの小説家アレッサンドロ・マンゾーニ(1785-1873)の『婚約者』(I promessi sposi, 現行の邦題は『いいなづけ』)決定版には,『汚名柱の記』(Storia della colonna infame)という作品が付加されている.
これはペストの流行する1630年のミラノで,毒物を使って疫病を流行させた「ペスト塗り」の嫌疑をかけられ無実の人々が処刑された事件を,当時の裁判記録を駆使しながら描いた歴史作品.方言が交じった一筋縄でいかないイタリア語の会話文や引用される当時のラテン語資料などなかなかの難物なのだけれども,自白の強要と冤罪という(残念ながら)今なおアクチュアルな主題を扱っていておそらく多くの人の関心を集めうると思われるので翻訳が出てほしいところ(最近刊行された霜田洋祐『歴史小説のレトリック
マンゾーニの〈語り〉』(https://gnosia.info/@ncrt035/99799486934744098 )に収められている記事と自分自身で読んだことのある範囲での感想に基づきます).
この事件当時はまだ制度としての拷問が存在していて,作中には法学者たちの拷問に関する見解や後の啓蒙思想家ピエトロ・ヴェッリ(1728-1797)のこの事件に対する考え方の批判的検討などほとんど論文風の箇所もある.冤罪の原因を拷問に見出したヴェッリに対して,マンゾーニは,たとえ制度上の拷問が存在したとしても,供述の矛盾などから当時の判事たちには正しい判決を下すことができたはずなのに,彼らが責任を放棄して「ペスト塗り」というスケープゴートを求める風潮に呑まれてしまったことを明らかにしていく.
ちなみにタイトルの「汚名柱」というのは,実際に「ペスト塗り」の嫌疑をかけられ処刑されたジャンジャコモ・モーラという人の家が取り壊された跡にその罪を記録するため建てられた柱で,それが後には逆に当時の判事たちの不名誉を伝える皮肉なものとなった.
困窮の末、57歳母と24歳長男死亡 ガス・水道止まり食料もなく 大阪・八尾の集合住宅 - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200227/k00/00m/040/341000c
ほぅ
「近年、龍谷大学理工学部教授の岡田至弘を中心とする龍谷大学の「古典籍デジタルアーカイブ研究プロジェクト」によって、デジタル工学に基づく地名の鮮明化や色素・素材分析などによる復元方法が開発され、作製時代の原型が忠実に復元され、これにより原図の文字の解読が可能となった」
最古の世界地図を読む 村岡 倫(編集) - 法藏館 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784831863850

転売の話題で「せどり」のことを思い出したが,辞書を引くと「競取り・糶取り」として「同業者の中間に立って品物を取り次ぎ,その手数料を取ること.また,それを業とする人」とある.
私は古書用語としてこの言葉を知ったので,本の背を見て転売で競うかを判断して抜いていくから「背取り」として記憶していたが,もっとひろい意味で使われるようだ.
梶山季之『せどり男爵数奇譚』がこれを題材にした小説.
「“せどり”(背取、競取)とは、古書業界の用語で、掘り出し物を探しては、安く買ったその本を他の古書店に高く転売することを業とする人を言う。せどり男爵こと笠井菊哉氏が出会う事件の数々。古書の世界に魅入られた人間たちを描く傑作ミステリー」
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480035677/
term of abuse のリストを作るだけでも大変そうだが,そういうのが出てくるたびにニュアンスを掴みあぐねるので,一定の需要は見込めそう.
サブネットマスクでコロナウイルスをシャットアウトしような (適当)
This account is not set to public on notestock.
AIきりたん,あまり調整を加えなくてもハイクオリティな歌を生成してくれる衝撃が広がっているフェーズを経て,やがてその高い出発点から更に入念な推敲を通して次のステージに達した傑作が陸続と現れてくる様子が予見できる(既にもうそうなりかけているか)
「○○に詳しい専門家」というのが一回3万円程度でテレビに出演しお気持ちを表明する仕事だということを知ってからはうんうんそれもまたタレカツ(タレント活動)だねとしか思わなくなった
蔑称として「~博士」「~のプロ」と使うのも「反用」や「風刺的転用」の一例と考えてよいものか
https://gnosia.info/@ncrt035/102523163659133081
タレカツは既に本当に存在するのか.不明を恥じます.
タレカツ京都本店がオープンしました | 新潟カツ丼 タレカツ(たれかつ) http://tarekatsu.jp/2018/07/14/180713/

これから出る本(4月24日発売)
「大乗仏教の起源について,伝承の媒体変化による発生という新説を提起する意欲作.デリダ,リクールらのテクスト理解,オングらの口頭伝承の研究,キッペンベルクらの教典研究――近年の西洋人文学の方法論をとり入れ,アジアに成立した仏教の知を思想史・社会史の観点から解明する」
仏教とエクリチュール 大乗仏教の起源と形成|東京大学出版会
http://www.utp.or.jp/book/b498522.html
「時間がないと勉強できないのだから大学教員の仕事は増やさないほうがよい」という発言は,「大学教員の」ではなく「人間の」の間違い.
たのしい
思想家・哲学者の文体――暇つぶしのためのクイズ|山口尚|note https://note.com/free_will/n/naf0d27d6a097
