全くの正論だ「今からカリキュラムをいじったところで2030年くらいにならないとAIネイティブな新入社員は入ってこないし、その頃まで深層学習が流行っているのか、NVidiaが残ってるのか、PythonやTensorFlowが広く使われているのか、GAFAがどうなっているかなんてさっぱり見当がつかない」
AI時代へ向けて育成すべきはAI人材か?|masanork|note https://note.mu/masanork/n/n83f98245712e
全くの正論だ「今からカリキュラムをいじったところで2030年くらいにならないとAIネイティブな新入社員は入ってこないし、その頃まで深層学習が流行っているのか、NVidiaが残ってるのか、PythonやTensorFlowが広く使われているのか、GAFAがどうなっているかなんてさっぱり見当がつかない」
AI時代へ向けて育成すべきはAI人材か?|masanork|note https://note.mu/masanork/n/n83f98245712e

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
だんだん暑くなってきたし「この時期にアカウント名をカール・レーフラーにしている人間」を見にいくことで気温調整するか
作文は,その言語の能動的な運用能力を高める目的の他に,特に古典語に関しては,本文上の難所で修正案・補綴案を出したり反対に他の人が出したそれらを評価したりする際の言語的・文体的判断力を高めるという学術的な目的もあると思う.
とすると,教科書の練習問題のような和文羅訳・希訳とは別の傾向の,たとえば原典の和訳ないし大意を示した和文から元の文を復元するトレーニングは効果的かもしれない(し,骨格部分だけなら割と簡単にツールを実装できるかもしれない)
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
書誌も示さずテクストとして描き起こすこともせずスクショを貼り付けるだけの投稿の多さはその方が「伸びる」からなのだろうが,現に「伸びて」からこそこそと出典を貼り足す醜悪さも含めて知性の敗北以外の何物でもないな……
ふむっ
「生循環学 -Biocyclology-
生命科学と人文・社会科学の研究者が出合い、新しい学問を構築していくための議論を進めています」
http://biocyclology.wpblog.jp/
読んでる
過去の表紙を一挙に紹介!「AIに興味を持つきっかけに!」人工知能学会誌『人工知能』表紙を手がけた二人の想い http://ainow.ai/2018/10/24/149359/

ほう
「三宅さん:実は人工知能の研究者は子供の頃に鉄腕アトムやガンダムを見て研究者になったっていう人が多いんです。ビジュアルから入ってきているんですよ……少し上の世代は鉄腕アトムで、少し下になるとマクロスとかガンダムとか、2000年以降だとエヴァンゲリオンとか攻殻機動隊。もっと若い人だと別のアニメかもしれません。だからこそ、人工知能に興味を持ってくれるきっかけになってくれればいいなと思っています」
2015年からの大澤さん担当期間のコンセプトは「親の本棚から子供がうっかり手にとるような表紙」とのことですが見事にそれが実現されているし,見比べても2015-2016年の表紙が一番好きですね.石黒正数さんの絵が素敵なのもあるけど画面に文字がたくさんあっていい.
表紙デザインが変わった時の「この騒動」(https://www.huffingtonpost.jp/2013/12/27/artificial-intelligence_n_4506691.html )がはるか昔のことのように思われるが,今にしても何とまぁ非道い言いがかりであったことよという感じだ.

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
テーラーメイド文芸なるほど「これまでの大量生産大量消費では確実に掴むことができなかった客層に対し、明確に対象読者とその需要を把握しながら個人で販売戦略を行うことは、まさにテーラーメイド文芸を体現していると言っても過言ではなく、確実に次の時代におけるモデルケースとして見るべきところがある」
縮小する業界で生き残る「ネット小説家」の超合理的生存戦略(津田 彷徨) | 現代ビジネス | 講談社(4/4) https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64710?page=4

Improve your English pronunciation using Youtube https://youglish.com/

🤔 「国際学会でレジュメを配らないのは、成果を人に盗まれないためでもありますよね」 https://twitter.com/jun_naibzade/status/1129995980756008960
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
日本学術会議 公開シンポジウム「新しい国際単位系(SI)重さ、電気、温度、そして時間の計測と私たちの暮らし」 https://www.nmij.jp/public/event/2018/scj-symposium_2018/
昨年開催されたシンポジウム
この前の紀要アクセス制限論しかり,人社系で知識や成果の公開とその促進に否定的な態度をとることに何とか理屈をこじつけようとする気配がちらほら見えて🤔にならざるを得ない場面が多い
もちろんそれと反対方向に心強い話を聞くこともあるわけでちゃんと未来のある方へ進むべきだが
今日はこれに行きます
京都大学図書館機構 - 【図書館機構】2019年度京都大学図書館機構講演会「オープン・サイテーションと機関リポジトリの展開」 https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1381711
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ただまぁ4桁5桁のフォロワーに大して面白くもない駄言を見せることで得られる承認というのもあるのかもしれない(適当
さすがに実況する余裕はなかったのでご飯食べながら振り返り.
挨拶・趣旨説明で触れられていたこととして,論文等成果物のオープンアクセス化は進められているけれども,その中での引用情報をはじめとしたデータの公開は世界的にもまだ比較的新しい試みであり,国内では機関リポジトリが整備されてきた一方,そうした引用データが持つ研究上の価値については十分に認識されていないのではないかという現状があって,開催動機のひとつとなっているとのこと.
西岡さんの発表は,国内の研究文献のオープンアクセス及びオープンサイテーションの状況紹介.
「オープン」といっても単にpdfが公開されているというような状況では不十分で,最低でも(excelではなくcsvのように)プロプライエタリでない形での公開を目指すべきこと,分野ごとの公開状況として(やはりというべきか)歴史・地理,哲学・宗教といった人文科学分野で引用データのオープン化に遅れが見られること(もちろん全体的に見ても海外と比べてまだ進んでいないというのはある).
ペローニさんの発表.
まずcitationをa conceptual directional link from a citing entity to a cited entityと定義した上で,オープン・サイテーションの原則を(1)機械可読に構造化されていること(JSON, RDF),(2)文献そのものから引用データが独立して切り離されていること,(3)パブリック・ドメインないしCC0下でオープンであること,DOIのような識別子を介して(4)特定及び(5)利用可能であることの5点を挙げる.
2017年4月時点でCrossrefに登録されているもののうち1%に過ぎなかった公開引用データが,Initiative for Open Citations (I4OC)の要求を通して2018年9月で55%まで伸びた経緯,公開引用データを用いた研究の実例と現在進行中のプロジェクトについての紹介.
佐藤さんの話としては,(1)オープン・サイテーションが進むことで考えられる展開と(2)日本でOCを促進するにはどうするかという二点.
前者についてはさらに(a)OCを使ったサービス開発,(b)OCに基づく評価指標構築,(c)引用ネットワーク研究の拡大の三点に分かれる.
引用ネットワーク研究についてはペローニさんの話の中にも少しあったけれども,文献同士の引用を介したつながりを図示することで学問分野間の連絡や学際的研究(e.g.数学系の学術誌に掲載された哲学や論理学の論文とか)が可視化されるとか,OCを使ったサービスではcitation gecko (https://citationgecko.com )のように関連のある文献探索などが可能.
佐藤さんの二点目に関して.
日本の学術出版プラットフォームとしてはJ-STAGEと機関リポジトリがあって,OCを進めるにあたり,前者についてはCrossRef DOIがあれば基本的に公開するだけなので学会側に了承を取れば問題ないが,後者については(データの無料公開自体には意義は出ないだろうが)論文がpdfで公開されているだけでそもそも公開可能な構造化されたデータが整備されていない場合が多そうという問題がある.
「有るものをオープンに」なら話が早いが「ないものを用意」だと大変.
そういえば日本の紀要の特異性のひとつとして,「フルテキストがほぼオープン」つまりデジタル化されてるもので有料というのはほとんどなく,逆にオープンでない場合はそもそも紙しかないという状況があるらしい.
部分的に少し言及があるのみだったけれども,IFの誤用ないし過信が示すように,引用数を業績評価指数として過剰に重視する潮流がある中で,引用データをオープン化してそれに基づく評価指標を構築する場合,人文社会系の研究評価が不当に低くなったり不正確になったりする惧れはあるので,そこをどう回避するかというのは考えなくてはならない.この辺は2月の筑波のシンポジウムで多少議論があったところ(https://gnosia.info/@ncrt035/101595624907482362 )
人文系の研究文献の引用数に見える特徴として「引用のピークを迎えるまでの期間が長い」というのがあって,2月にはその例として「70年経っても引用されている」というケースを引いていた記憶があるけれども,「70年前普通に新しいのでは……?」と内心なってしまった.
今日のスライドでも本文中での文献への言及で名前+刊行年の下二桁というケースがあったけれども我々の場合「81」だったら1981年なのか1881年なのか(それとも1781年!)わからないし「18」だったら2018年なのか1918年なのかわからんとなる…
そいえばペローニさんはコンピュータ・サイエンスが専門だけれども現所属としてはボローニャ大学古典文献学・イタリア研究学部(Università di Bologna, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica)だった.
写真は3年前に撮ったやつ.

むっ「担当者は「うわ、これはひどいですね」と調査を約束してくれましたが、放映直前に連絡があって「すいません、かなりちがう方向のものになってしまいまして」とのこと。上司からの圧力でしょうか」
https://twitter.com/jumping5555/status/1128818907869921281
https://twitter.com/jumping5555/status/1128819181879668737
何か描こうと思って座って結局なんも描けんなとなると「何で生きてる?」という自問が始まるので気分転換としてリスキー過ぎるな
よくできる人ほど個々の事態に対してあらゆる可能性が脳裏をよぎるので断言口調を避け物言いの歯切れが悪くなるため,素人や非専門家の目にはかえって頼りなく見えるみたいなことがある気がする.
面接とかは「とっさの即応力で下駄を履くやつ許すまじ」という気持ちがあったが,知識が血肉になっていると関係のあるものは諳んじられるようになるし,口頭で臨機応変に答えられるかどうかがよく習熟している指標になるのかなという気持ちに最近はなってきた.
ところでイタリアは口頭試験の文化の国であることを思い出した.
http://www.kyoto.zaq.jp/italomania/camera/kunishi/5.html#NM3_9
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
o tempora, o mores!はキケロ―『カティリーナ弾劾』1.2ですね
ちゃんと力量のほどを考査する目的ならいいんですが(試験官も取って食うつもりではないのだし……)ある種の「通過儀礼」と思って圧をかけてくる人たちもまだ残っているので判断が難しい.
これ見たいね「トランプ大統領が大相撲観戦時に土俵に上がるらしいが、上から奥さんを手招きして「お前も来い」と土俵にあげる」
https://twitter.com/kentaro666/status/1130605788823605248
昼ごはん後にパウンドケーキ食べたのにこれから珈琲淹れてお菓子を食べようという誘惑に駆られている
100年超分の論文引用データを機械的に抽出・整形 BMJとScholarcyの取り組み | カレントアウェアネス・ポータル http://current.ndl.go.jp/node/38198
「世界各地の抵抗の営みを巨大な射程で見つめ、「3.11」後を生き抜く民衆の力を析出する。気鋭の歴史学者 待望の単著!」とのこと
黙示のエチュード 歴史的理性の復活のために(仮題) | 新評論 http://www.shinhyoron.co.jp/978-4-7948-1113-4.html
こんなんやってるんだ(6月23日まで)
日本ポーランド国交樹立100周年記念 ポーランド芸術祭2019 in Japan 「セレブレーション-日本ポーランド現代美術展-」|イベントスケジュール|京都芸術センター http://www.kac.or.jp/events/25636/
数学から創るジェネラティブアート ―Processingで学ぶかたちのデザイン:書籍案内|技術評論社 https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-10463-4

「くずし字」をAIで解読する研究がますます盛んに:機械学習と人文系の分野横断的研究も|Marvin(マーヴィン)人工知能・AIと機械学習の事例メディア https://marvin.news/6464

新型「MacBook Pro」発表 最大8コア5GHzで動作 - ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1905/22/news064.html


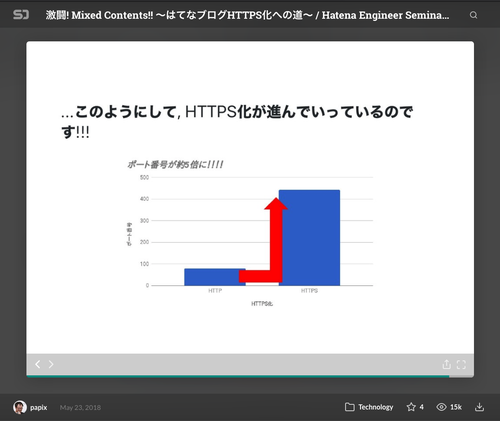
以前,何の本だったか,「『古典的』というと悪く聞こえるかもしれませんが〜」という記述を見て🤔になったことがある.
大英博物館のマンガ展,1枚目のpanpanyaさんのキャプションを拡大して読んでいた.
panpanya began drawing around 2006 and was active in dojinshi circles, publishing work through pixiv, an online community of manga and anime artists and fans. panpanya’s detailed townscapes are often drawn from memory, depicting Kawasaki where the artist grew up. panpanya draws figures in pencil and backgrounds in ballpoint pen, digitally combining them into one page.
月組公演 『チェ・ゲバラ』 | 宝塚歌劇公式ホームページ https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2019/cheguevara/index.html

これ,今読み直してみるとむしろ逆で,人文系の引用データのオープン化がちゃんと進んでいない現状でオープンデータに基づく研究評価を行うと,人文学系分野が過小評価される惧れがある,ということなので,オープン・サイテーションの促進により公正かつ適正な新しい研究評価指標の構築につながるということを周知していかないといけない.
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
コンピュータ・サイエンスやりたくなって1年ちょっとコツコツやってる/やったことたち - でこてっくろぐ ねお https://dekotech.dekokun.info/entry/2019/05/22/135330

ところでCSの有学位者をどのようにしてギリシア語学・ラテン語学の世界に迷い込ませるかという課題がございます
良さそう
クラウド型の無料の楽譜作成ツール、Flatがサービススタート。充実した機能で、多目的に活用でき、作成した譜面の共有も可能 | | 藤本健の "DTMステーション" https://www.dtmstation.com/archives/25059.html

「令」「月」のそれぞれに「今」「日」の異表記を持つ本があると.へー.
https://twitter.com/nijlkokubunken/status/1131051693783650304
日本や中国の古典の伝承や本文の変容についてconciseな読み物があったら読みたい.
この池田亀鑑『古典学入門』が王道ですが,新しく何か類書が出ているか調べていない
https://twitter.com/ncrt035/status/1017737070523977728
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
実務セミナー「資料管理の現場でデジタルアーカイブを位置づける」
セミナー - 社会・労働関係資料センター連絡協議会 https://sites.google.com/site/rodoshiryokyo/sokai/semina
指小辞の中には形態としてはそうでも意味としては原級のものと変わりないタイプのものもあって,ラテン語やギリシア語,ロマンス諸語における用例をレオパルディが『雑録』(Zibaldone)のいろいろな個所で集めていたらしくそれを研究した論文があった.
Piras Apa, T.(1997), `Sui diminutivi positivati latini e greci nello Zibaldone di penzieri di Giacomo Leopardi', in Sconocchia, S., Toneatto, L.(a cura di), Lingue tecniche del greco e del latino II, pp.79-91.
ルクレーティウスの第3巻後半の方は,エピクーロス派による死を恐れる必要がないことの理屈「我々が生きている間死は関係がないし,死が訪れたとき我々はもう存在しないから」をベースに,死の悲惨さを嘆く人々の考えを論駁しているが,その際の表現には喜劇やエピグラム(墓碑銘的なものや酒宴詩)を踏まえているらしい言い回しが見られるのでこの辺をもう少し調べたい.
Mastodon, TLがダバダバ流れるので誤タップ・誤クリックによる誤BTを防ぐためにBT前確認ダイアログの設定がおすすめ
なおこのアカウントはBT確認設定を行っていなかったことによりたいぷはてな先生の新刊情報をシェアした実績があります
Mastodonはカードを取りに行った後行進しないから昔のTwitterの投稿にリンク貼ってると古いプロフィール画像を見ることができる(このときはニアだった)
https://gnosia.info/@ncrt035/99918418459095730
今読んでるフランス書がちょうどp.を二度書きしない流儀だったのでこれは今度確認してみよう
https://twitter.com/oyabai/status/1131454294241234945
3単語タイトルの本はかっこいい - 浴槽で発見された手記 http://logiko.hatenablog.com/entry/2015/09/15/164522
3単語書名がたくさん載っている

フランス語の本しか引かないとかドイツ語の本しか引かない分野ならそこに合わせればいいけども,うちはそういうところでもないので,どのように考えるのが一番筋が通るかな(普段は〈著者名〉〈出版年〉:〈ページ数〉でp.とかS.とかは入れない)
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
MacGregor, A. (2005), `Was Manilius really a Stoic?' ICS, 41-65.が『アストロノミカ』の中に見られる数のモチーフ(一種の折句的な仕方で織り込まれたものも含む)を取り上げているのは事実としては重要に思われるけれども,あまり他から顧みられていないようなのは,そのことをピュータゴラース派の思想と関連づけようとしていることによるのかもしれない.
これについてはもう少し別の観点からアプローチできるかもしれない.
ギリシア語韻文,ギリシア語散文,ラテン語韻文,ラテン語散文で2×2の表を作ると,隣り合う分野の文献は読む機会が自然とできても,斜向かいの分野は意識して作らないとおろそかになりがち.
逆にいつまででも生きて居れるなら却って楽しみも少なくなるのかもしれないな(不死になったことがないのでわからないが)
食堂,最近高くなったという気がしてたが,若鶏醤油揚げ,ライスSS,味噌汁,ブロッコリーのピーナッツ和えで400円以内なので組み合わせようだなとなった
とはいえ勉強会やったり Qiita みたいなの建てて商売までやるぐらいなんだから情報系の情報共有にかける情熱は他の界隈に比べて尋常ではない気がする。OSS もだけど,こう,原始共産主義的な部分あるもんな。
これは私がいつもこの界隈を羨ましく思っていることで,我々の業界は割とそういうのとは対極にあるので厳しさがある.
「情報系の情報共有にかける情熱は他の界隈に比べて尋常ではない気がする」
https://mstdn.maud.io/@orumin/102150229564216632
京都薬科大学はどの辺にあるんだったかなと思って調べたら山科の方だった
https://www.kyoto-phu.ac.jp/compendium/access_map/
綾部バラ園 2019春のバラまつり
5月18日(土)~6月23日(日)
http://www.ayabe-gunze-square.com/info/2019/03/25/1223/
ちょっと待って,ユウェナーリスのスコリア(古スコリアではなくscholia recentioraの方)のエディション(しかもeditio princepsらしい)が出てたなんて知らんかったぞ.2巻本で,第1巻が2011年,第2巻が去年(2018年)に出て完結している.
Scholia in Iuuenalem recentiora, a cura di Stefano Grazzini (con la collaborazione di Francesca Artemisio e Frédéric Duplessis).
https://edizioni.sns.it/it/scholia-in-iuuenalem-recentiora-secundum-recensiones-f-et-c-tomus-i-satt-1-6.html
https://edizioni.sns.it/it/scholia-in-iuuenalem-recentiora-secundum-recensiones-f-et-c-tomus-i-satt-1-6-370.html


G.Cavalloのこういう本が出ているのを見つけたので興味がある.
Libri e lettori di Ovidio. Dall’antichità al medioevo, Bardi Edizioni, 2019.
https://www.bardiedizioni.it/shop/libri-e-lettori-di-ovidio-dallantichita-al-medioevo/
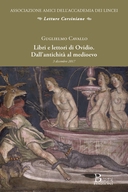
そういえばOlschki社からポリツィアーノのedizione nazionaleがStrumenti(https://www.olschki.it/catalogo/collana/enps )とTesti(https://www.olschki.it/catalogo/collana/enpt )に分けて進められている.
Strumentiの方の既刊,Viti, P.(a cura di)(2016), Cultura e filologia di Angelo Poliziano. Traduzioni e commenti. Atti del Convegno di Studi (Firenze, 27-29 novembre 2014) を見ていると, Guida, A., Poliziano e Leopardi: un incontro non riconosciutoというポリツィアーノとレオパルディに関する論文が入っていて面白そう.
🤔「学部卒や修士卒で日本人学生が就職した日本の会社が、ある日突然外資に買収され「博士号のない人は全員、研究職から外します」って言われる日がくるんじゃないか」- Quora https://jp.quora.com/%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%BF%91%E5%B9%B4-%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9B%BD%EF%BC%97%E3%83%B6%E5%9B%BD%E3%81%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A0%E3%81%91%E4%BF%AE%E5%A3%AB-%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%8F%B7%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%80%85

別にどうでもいいわと思ってたが前にTLで見たこれ(https://twitter.com/esumii/status/1126097779623845888 )を思い出したのでわざわざ視てみたけど「やみません」とは聞こえんな…
関連動画(https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201904/30taiirei.html )の10:55らへん.

Bompianiのデーモクリトスは本当に何で見かけたときに買っておかなかったのか悔やんでも悔やみきれない
葛粉一袋が2回分,練りゴマ一瓶が3回分なので,6の倍数でやめないと葛粉と練りゴマのどちらかが余ることになる.