これ「ニュースの誕生」という本の内容っぽいな
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1999news/contents.html




いま明治版画史という本を読んでいるけど、めちゃくちゃおもしろいです。
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b34608.html


原版から刷版をつくる、刷版は輪転機の形に合わせてカーブしているとか、こういう具体的な印刷技術の説明おもしろい。
https://www.kotobuki-print.co.jp/?p=737

この記事にあるような、刷版としてつくられた鉛版のことを stereotype っていうですね(知らなかった)
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
Hi! 👋 Here's our #introduction .
We're BBC Research & Development; we explore and test new technology to discover how the BBC can best make use of it in the future.
For 100 years our engineers have been at the forefront of developments in broadcasting.
We're now researching how everyone could get TV & radio via the internet – along with all the flexibility and creativity that brings.
5G, AI, next-gen audio, UHD, personal data… we are investigating all these – and more!
https://www.youtube.com/watch?v=rzztGFXYR1Y

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ネット上の絵文字文化、確実に日本語圏固有というかmastodon.socialの絵文字の少なさを見るとローカルな文化なのだなという印象なので、その辺の歴史が知りたいなと思い始めた。
そもそも「Emoji」で通っているとおり、絵文字自体も日本人がつくったものなのだけれど、既に他の言語圏にも伝播したのだからもっと盛り上がってもおかしくないところやはり日本語圏でのバリエーションが圧倒的に多いのだよな……そこが不思議でたまらない。
「漢字があるから少ない文字数でより多く情報を詰められる」ということだけでは明らかに説明しきれない部分があると思う。識者の方がいらっしゃいましたらご教示願います……(自分で調べなさい!)
絵文字というか、特にFediverse上での文字を含む絵文字( 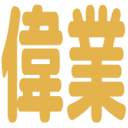 など)は他の言語圏ではほとんど見ないので、なんでだろう……と思っています。
など)は他の言語圏ではほとんど見ないので、なんでだろう……と思っています。
ミーム文化自体は英語圏などでも散見されるのでますます不思議……(gifなどビジュアル寄りのものが多い印象ですが)
「言葉をミームにする」ということが日本語圏特有な気もしています。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
8月1日、今日この日だけでもツイートするのをやめませんか?と言う呼びかけが行われていて、「ツイートしない」ことが、イーロン、マスクへの嫌がらせ、抵抗になると言う発想になってきてるのに、イーロンマスクが何を言おうが、ここTwitterに居座るぞ! ツイートし続けるぞ!と言うのは、一見抵抗のように見えて、もうただの依存仕草でしかないんだよなぁ。
あと、Twitterが「今でも一番使えるインフラ」だとは自分の使用ケースでは思わないかな。むしろ「もうほぼ使う意味のないインフラ」になってる。まあ、これは人によって求めてる情報が違うから断定はできないけれど。
でも、その「ここでしか得られない」「一番使える」という思い込みを突いて、イーロンは好き勝手やってるので......。そこは「SNS以前のインターネットが持っていた可能性」という、想像力の部分から奪われてきてる。何度も言っているけれど。

左翼を自認する人が、Twitterを使いつづけて、道具としては透明であるかのように主張しているのは、けっこう見ていられない。そう言うのなら、原発も軍隊も道具として見れば透明で使い方しだいだって話になる。

ベンヤミンの複製技術時代とかでは映画資本を市民が接収することを考えられていたとおもうけど、資本が資本家の手にあることが自明なまま、道具としてはあたかも自律的かのように見たてて使い方を変えていこうというのは、左翼的にダメでしょ

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
要するに、これでは、自分が単に資本主義的に都合の良い主体になっていくことですら、「これはそうした資本主義に対する抵抗だ」と言って、自己の振る舞いや現状、もっと言えば、資本家側プラットフォーム側のやっていることを肯定することにもなりかねない。 それは単に体制側にとって大変都合の良いことでしかない。

@pokarim 文脈としては、たとえばなのですが、「Twitter とは言葉の拡声装置として喉を延長するものだ」といったときに、もう一方においては、その拡声器を通して語られる言葉は質に取られている状況であり、言葉が自分のものでなくなっている=疎外されている、という状況になっています。「コンピュータとは知能の増幅装置だ」というのもおなじ状況におちいるとおもいます。そこで増幅されたとされる知能は、コンピュータの生産企業への依存を強め、自分以外の知能を自分の知能の一部として利用することを自分の知能の拡張だと認知することになる。
現代的な技術の多くが、身体的な能力の拡張として現れ、そのように喧伝することで、疎外を生みだしているのではないかとおもうようになりました。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「ブラックボックス」という概念じたいが、コンピュータにかぎらないけど一般に内部状態や動作原理が開示されていない機械のことを指し、そこから転じて「雑誌における写真の掲載可否の選考過程」を「ブラックボックス」だと呼ぶことは、「雑誌における写真の掲載可否の選考過程」への理解についてのなにかしらの変化があるようにおもわれます。

資本としては、機械のなかにはブラックボックスを作り出すことで、ユーザーには祈ることしかできないようにしたい。そうすると技術に対する態度は信仰になる。
伽藍とバザールでも読み直すか。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
https://fedibird.com/@zpitschi/110814633440767433
これは逆の言い方もできて、市民が「営利組織による私有地であることを理性では了解しているにも拘らず、そのリスクを見て見ぬふりして無責任に公共財扱いしている」という面もあるのではないですかね。
むしろ私からすると「公共財というラベルを付けておけばコストも労力も全く負担なく言いたい放題できる」という悪徳が蔓延しているように見えている。
本当に公共財とせざるを得ないようなもの、たとえば電波割り当てとか通信回線とか、そういうものってやっぱり法的にちゃんとそういう扱いを受けてるんですよ。 Twitter とかを同列に扱うのはちょっと違う。
べつに税金と行政でどうにかするだけが道ではなくて、それこそ自由ソフトウェアみたいなのもひとつの手なわけですよね (当然相応のコストはかかるけど……)

公共性というか、誰のものでもない空間になるかどうかなんだよな。
自分のこのサーバーは自分が管理しているからコンテンツの削除も編集も自分の権限にあるけど、他のサーバーにとどいた自分のメッセージはそうではない。あるサーバーは自分のサーバーをブロックしているかもしれないけど、それによって誰かの自由がなくなるわけではないし、コンテンツが閉じたものになるわけでもない。
 の投稿
rino@mstdn.jp
の投稿
rino@mstdn.jpこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

ActivityPub の世界にあっては、コンテンツは誰のものでもない場所に置かれている。コンテンツは常に開かれていて、だれもそれを独占できない。それがすごく良いとおもっている。