おもしろかった
近代日本出版業確立期における大倉書店
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeigakushi1969/1986/18/1986_18_101/_article/-char/ja/

おもしろかった
近代日本出版業確立期における大倉書店
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeigakushi1969/1986/18/1986_18_101/_article/-char/ja/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

美術手帖とかもゼロ年代あたりからずいぶん広告っぽくなってたのと、主要メディアに対すうるオルタナティブな同人誌とか2010年代にいくつかあったけどそっちはそっちでアカデミズムへの目配せが強すぎて、なんだかなーと。
売文で食える世界ではなくなっているからだけど...。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

出力の問題というより担い手の問題ですかね。アカデミシャン崩れが批評をやるのは常道な気がするけど、アカデミシャンが「批評」をやっていて、かなり権威主義的だったとおもう。ArtTraceのことなんですが...。

すげー悪い言い方しますが、自分には同世代の批評っぽい言説は就職活動にみえてましたよ
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

へぇー、こんなのあるんだ
バウハウスの写真 「写真の発見」(by Google Arts & Culture) – bauhaus100 japan https://www.bauhaus.ac/bauhaus100/topics/post-882.html


@pokarim さん Florence Henri 好きそうかなとおもったのでオススメしておきます
https://www.moma.org/artists/2595


美大の油絵科にいたけど、自分が版画の技法や歴史についての知識がほとんどないのにびっくりするな...。美術史の本でもまともに触れられていたかどうかわからない。自分が興味なかっただけなのかほとんど記述されてこなかったのか。
アマゾン、欧州の新IT規制に異議 米企業で初 他のテクノロジー大手も追随か?║JBpress
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/76040

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ブログにせよマイクにせよ、ことばを広める道具が物珍しい頃はその道具を使ってその道具の話をしたがる、みたいなことをJoel Spolskyが昔書いていたような記憶がある。

最終日に行ってきた、良かった。カタログないっぽいの残念だ。
出来事との距離 -描かれたニュース・戦争・日常 | 展覧会 | 町田市立国際版画美術館 http://hanga-museum.jp/exhibition/index/2023-537





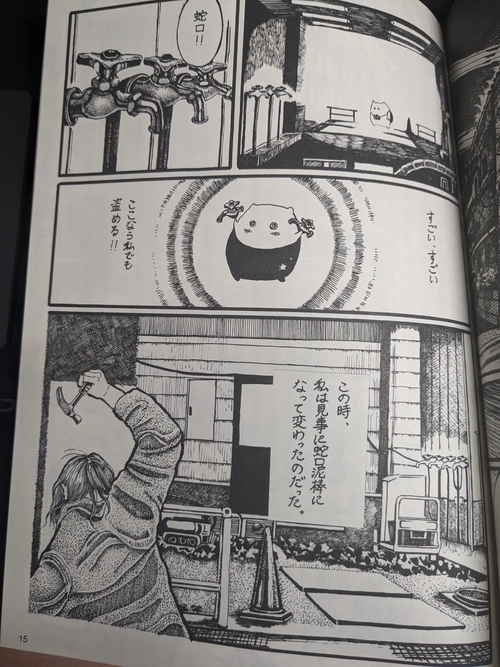
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

The Computer for the 21st Century 読みなおすとやっぱりおもしろいな
https://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/Weiser-Computer21stCentury-SciAm.pdf

アラン・ケイの1972年のもそうだけど、まだ実現されていない技術について考えるのにSFっぽい語りをするのはPARCの伝統かなにかなのか

フラットデザインはいくつか問題あるけど、マリオのブロックも、ぶつかったらキノコでてくるとか壊せるとかは絵面でわかるわけではなかったとおもう。最初のほうに、なんとなく行為が促され、その行為へのリアクションがあり、行為-反応というセットが見えればあとはパターンによって学習する、というようになっているはずで、フラットかどうかが問題ではないはず。

行為を制約するのがディスプレイという平面なので「フラット」なデザインには意味がある
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

現実世界との類似性がコンピュータ操作にとって意味があるわけではなくて、まずマウスの行為可能性としてマウスごと動かす、マウスのボタンをクリックするみたいなものが試され、その操作が画面上で対応づけられる、という形で操作を覚えるはずだ。対応物がボタンのようなものである必要はない。
フラットデザインも同じで、まず物理的な行為可能性があって(フリックとかタップとか)、それと画面上のなにかを対応づける、という形でしか覚えない。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

この図たしかにすごいけど、それよりコミュニティノートのほうがやばい。参考がwikipediaとか実名で恥ずかしくてできない(wikipediaがわるいわけではない)。
https://twitter.com/unwomenjapan/status/1680396835268231170

これベン図みたいなものを使ってしまっているから言いたいことは失敗しているけど、好意的に解釈して「フェミニズムはすべての差別に反対する」と言いたいのだろう。それを匿名ユーザーが公平を装って「フェミニズムは性差に起因する平等を求めるものであってすべての差別に反対するものではない(ソースはWikipedia)」と限定を勝手につけるの悪意しかない。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

Medium第2号に掲載されている『細胞への配慮(ケア)』(鈴木和歌奈)、iPS細胞の研究室のエスノグラフィーやっていて、めちゃくちゃおもしろい。iPSソムリエというものがいるらしい。
「iPS細胞は非常に敏感であり、多能性を容易に失い他の体細胞のような「非多能性」の細胞になってしまいかねないので、その培養はこの研究室においても特に難しい。(…)研究室の中で、一部のテクニシャンや研究者はiPS細胞をとりわけ上手に扱う技能を持っていることで知られている。そうした研究者たちは、ワインの目利きになぞらえて「iPSソムリエ」と呼ばれている。」
…
「ナナミは後に、「細胞がカワイイと感じられない人とは一緒に働けません。採用面接では必ず、細胞をカワイイと思うかどうか質問します」と語った。」

版画芸術買って読んでるけど、関西のほうが版画表現をベースにした作家多いとかあるんかな
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

もの派くらいの時期って「版」的な表現ってかなりあった印象があって、一部は問題意識や表現の方向性として継承されているのは知っている

版画芸術はじめて買って読んで、けっこうおもしろかった。雑誌そのものが、作品販売のプラットフォームになってるのにびびったけど、考えてみるとふつうなんだよな。

https://togetter.com/li/2187796
元ツイートがたいしたこと言ってるとも思えないけど、表現の性的な読みをこれだけ強く否認してしまうのってなんなんだろうな。


これちょっとおもしろそうだな。読めるかどうか不明だけど...。
https://amzn.asia/d/atWEm9E

たまの「さよなら人類」って2001年宇宙の旅のパロディだったのか。言われてみればたしかにだけど。

1991年の現代思想を読んでいるけど、「インターフェイスする」という動詞がひんぱんに出てくる。90年代にはそういう語彙だったの?日本語に取り込まれたカタカナ語としての「インターフェイス」、動詞的用法はすでにみなくなっているけど。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

@wakalicht 版画芸術195号を読んでいたのですが、インタビューを受けている7人中6人が関西の美大出身で、これはずいぶんハッキリしているなと思いました。
マキシグラフィカやPATinKyotoの流れもいままでしらず、版画芸術同号で知ったのですが、関東の美大やシーンからは見えづらい流れな気がします。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

現代思想のキットラー「数と数字」を整理しながら読んでいるけど難解で、かつ、あれっそこまで興味持てないな?となっている

トランスジェンダーであることをカミングアウトして活動している方すごいとおもう。