印刷物の経験について語るのってめちゃくちゃ難しいな

印刷物の媒体の特性をスキップしてコンテンツについて語ってしまうか、印刷物を取り巻く制度について語ってしまうか、そういうものになりがちで、印刷物の経験についての記述は難しい
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
そもそも EU 自体がサーバ持ってるし (https://social.network.europa.eu/@EU_Commission/108220439624357877)
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
ついでに言うと「誰が見ても公式とわかるアカウント」の作成がめちゃくちゃ楽というのがある (政府ドメインは一般人は取れないため)

広報としては弱いようにみえても、プラットフォーム依存じゃないからコンテンツが消えたり操作されたりする心配がないのは重要だよなぁ。消えるかどうかは管理しだいだけど、トランプのアカウントがBANされるみたいなことはありえない。

AT Protocol って分散されたPDSなるものを誰がコスト払って運用すんのっていう気持があって、技術者の考えがちな絵に描いた餅っていう印象があるんだよなぁ
アカウントが自由に移転できるのなら、個人がコストを払ってPDSなるものを運用するメリットがないように思う

https://qiita.com/gpsnmeajp/items/eb665d639f088b85454e
これ見てて、PDSってほとんど単一システム内の分散DBくらいの位置付けでは?みたいな気がしており、つまりこれは twitter の内部的なアーキテクチャに過ぎないのでは?それが正しい理解かどうかわからないけど。
さんざん悪くいわれてきたLTLだけど、これはこれでコミュニティみたいな単位を形成するもので、運用するメリットはまあまあある。ネットワークから分断された場を形成するのは、安全性っていう観点から重要なので。
開かれていることと閉じていることの両面あることが、ネットワークを全体として発展させるんじゃないかという気がするけど、まあそれはともかくとして、ATPまわりからは技術的詳細ばかり聞こえてきて、どんなネットワークを作っていきたいか言っている人があんまりいないんじゃないかな。
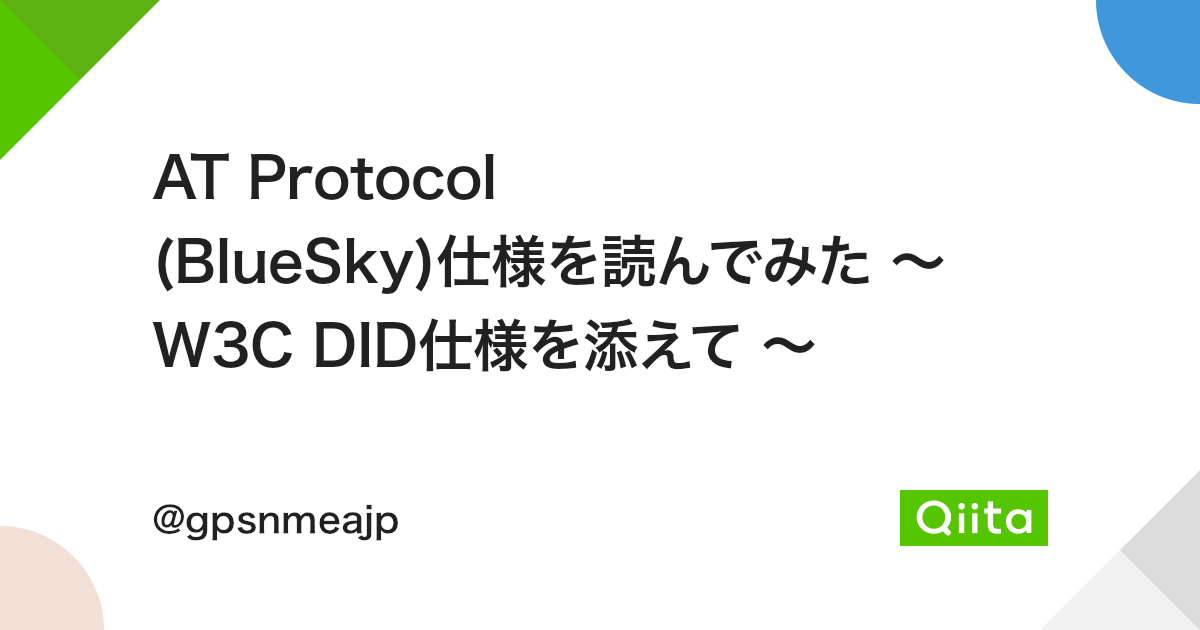

LTL、misskey.io とか vivaldi.net とか jp とか見てると、良かれ悪しかれミームを生んでいて、それってコンテンツが健全に発達するための鍵でもあるとおもうんですよね。過剰に内輪になると不健全になるけど。AT Protocol にはそういうのがあるように見えないなと思う。アカウント移転できるわけだからどこでやっても同じって気持ちになるし、そうすると文化的多様性は生じないんじゃないか。文化的な多様性がないのであれば、サーバーを独自に運用する意味あるのかと。


AT Protocol、サーバー運用の分散性が絵に描いた餅に見えてしまうんだよなぁ。分散する動機が見つけられなそうというか。
Fediverse のサーバー運用ってめちゃくちゃグラデーションで、一人サーバーから少数、大規模まであって、現状それらが適当な距離感を保ちながら相互に会話している。この距離感みたいなのがわりと絶妙に感じる。あそこのサーバーはノリがあわないな、みたいな。サーバー単位でやっぱり文化があって、そういう特色を出したいから運用しているし、アカウントもそのなかに所属する心地良さみたいなものがある。
投稿って PDS に保存されていて API で取得するのよね?
ということは PDS を握っていると API での応答に広告を混ぜることができるってことだ (???)

現実的にはそういうことになるんじゃないかなーとおもう。分散サーバーを運用するメリットが金銭的な価値以外になさそうで、今のところそれもないもんだから、ジャック・ドーシーが暗号通貨とか言いだしてるんじゃないかという気が。人を繋ぐものがお金になると、最終的には広告プラットフォームになる以外にないのでは。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
Misskeyに限らず分散SNSは規模の大小はあれど管理者の独裁なんすよ。
住民を第一に考える独裁者もいれば、強権を行使しまくる独裁者もいる。
misskeyの某鯖で管理側に居たが、リーダーのせいで内部から分裂した話 https://anond.hatelabo.jp/20230713050627
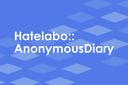
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
久しぶりにTwitterのぞいたら、まあ元からその傾向はあったアカウントが言うことますますおかしくなってたんですよね。そういうのもすぐ「元からそれだけおかしいやつだったんだ!」ってリベラルはよく言うでしょう?でも、自分から見たら「問題も元からないわけじゃないけど、明らかに差別者差別者罵られてから、【そっち】に行ってしまったな】と思うことが多々あって。SNSという場自体がよくないのかな、と最近だんだんそのように思うようになってきました。
そりゃあ私だって人権は大事だと思ってるし、いろんな事件や事故に対し、一体この国はなんなんだと日常からイライラしてるのだけれども、でもそんなリベラルや左翼の論理に納得できないことは実は多々ある。基本は賛同なんだけど、疑問もあると疑問を呈したら「はい、差別者!」みたいな人も少なくなくて。それって、本当に問題の改善になってるんでしょうか。理解深まってるんでしょうか。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

聞いてる。
bluesky への見解まったく同意で、けっきょく twitter のやりなおしで、根本のデザイン変わっていなくて、分散っていっても技術的な話でしかないとおもう。技術的な分散より、管理の分散がポイントで、それはモデレーションについても言える。AT Protocol には twitter が抱えた問題にたいして何のアプローチもないように見える。
Fediverse の独裁のほうが意味があるデザインになっているとおもう。
https://www.youtube.com/watch?v=qguUtS_eUQE

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「Threadsはそれに伴う危険性を示している。公共の広場を模したメタ・プラットフォームズのサービスは、救命艇の提供に関して独自の約束をしている。まだ決まっていないいつの日か、マストドンを支えるプロトコルであるActivity Pubと連携すると主張しているのだ。」って、Blueskyもまだ連合動いてないとおもうけど...。
Threadsの危険性がなにかくらい書いてほしい。
https://wired.jp/article/plaintext-twitter-alternatives-enshittification-trap/


あと、やっぱり当初の想定が、駄目になるtwitterを救うために脱出口を作るというくらいで、ネットワークが発展するビジョンあんまりなさそう
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「炎上で利益を上げてきた」はどうなんだろうな。炎上で利益を上げてきたユーザーはいくらでもいるとおもうけど、プラットフォームにとって炎上というものに経済的な価値があったかどうかはよくわからない。