これ,うまい表現だ.「関西ネイティブは一見感情豊かに見えるが,それはあくまでロールを演じる意味においてでしかない」| 日本版「文化の盗用」議論
https://anond.hatelabo.jp/20181012094032
これ,うまい表現だ.「関西ネイティブは一見感情豊かに見えるが,それはあくまでロールを演じる意味においてでしかない」| 日本版「文化の盗用」議論
https://anond.hatelabo.jp/20181012094032
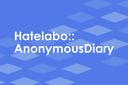
国際高等教育院の略称の「KKK」への変更について
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/cli/mail/documents/2017/a0167.pdf
京大のこういうところ好き(不謹慎)
cladesの意味がよく判らなくなったのでErnout-Meilletの語源辞典を引くと,例外はあるものの一般的に言ってcaedesが能動的な意味なのに対してcladesは受動的であるように書いてあった(généralment au sens passif, tandis que caedēs a le sens actif; toutefois, quelques exceptions, surtout poétiques).
なるほど.
ところで何の気なしに見てたけどもこのタキトゥスのcladesの用例はここに見たcaedesとの違いをつかむのに良いかもしれない.cladesの「災害」という意味はその受動性をよく表している.
https://gnosia.info/@ncrt035/28271
sakura demo https://oxal.org/projects/sakura/demo/
雑にHTML書いて1行当てるだけでいい感じになるsakuracssをよく使ってるよ
当日の質疑の要点:
(Q1)exstillatとin astraの動作方向の関係について
(Q2)ペルセウスの誕生譚との関連
(Q3)オウィディウス『変身物語』との関係
(Q4)exstillatと「結果のin」の相性
(A1)従来の解釈はin astraを物理的な方向と考えたためexstillatに通常とは逆の「下から上へ」の運動を認めることになった.in+acc.を結果と捉えるとその必要はなくなる.
(A2)ゼウスが黄金の雨と化してダナエーと交わり生まれたペルセウス誕生のイメージとの関わりは念頭になかったが,詩的効果という点では意識されている可能性はある.
(A3)この箇所でマーニーリウスの参照先の一つがオウィディウスであるのは間違いない(cf. Flores, E.(1966), Contributi di filologia maniliana, Napoli).語彙表現面でどのくらい類似ないし相違があるかはなお検討を要する.
(A4)文法書への指示はしたがコロケーションとして妥当か問う余地はある.Man.内なら専用辞典があるので近い例を調べるのは不可能ではなさそう.
「日本イタリア会館」ってウィトルーウィウスの翻訳者でもる森田慶一の作だったの知らなかった|
田路貴浩「構立てと生命 森田慶一の建築と思想」(所収:京都工芸繊維大学美術工芸資料館 建築アーカイヴ研究会『もうひとつの京都 ─モダニズム建築から見えてくるもの─ 展 カタログ』2011年) http://www.taji-lab.archi.kyoto-u.ac.jp/member/taji/column/2011_01.pdf
わかりやすいね
「研究者と一般の人との間には、ものを考える背景となる知識体系にかなりの『ずれ』がある,ということを意識しないといけません……
研究費はばら撒け>>研究者間の相互評価に任せろ
好きなことをやればよい>>研究者の『好きなこと』はイノベーション
役に立たなくてよい>>科学は総合力であり、幅の広さが力」
|「研究費をばら撒け、と言ってはいけない理由」 https://www.fbs-osaka-kondolabo.net/blog/baramaki