たとえば、本ってモノとして置かれていると、誰のものかなとかは意識するけど、とりあえず開いてみることができるもので、でも電子書籍にはそういうことはできない。本にだって所有者がいるんだから同じことでしょっていうのはぜんぜんそんなことなくて、むしろそこで「本を開くことができる」ということができなくなっている、そのようにして、モノから開かれ自体が奪われていく。排除アートだって、あれも場を閉じたものにするためのものだ。

たとえば、本ってモノとして置かれていると、誰のものかなとかは意識するけど、とりあえず開いてみることができるもので、でも電子書籍にはそういうことはできない。本にだって所有者がいるんだから同じことでしょっていうのはぜんぜんそんなことなくて、むしろそこで「本を開くことができる」ということができなくなっている、そのようにして、モノから開かれ自体が奪われていく。排除アートだって、あれも場を閉じたものにするためのものだ。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。


このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
生成AIの偽情報対策、デジタル発信者情報など新技術の活用をG7に提言へ║読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230802-OYT1T50298/


 の投稿
root@moth.zone
の投稿
root@moth.zone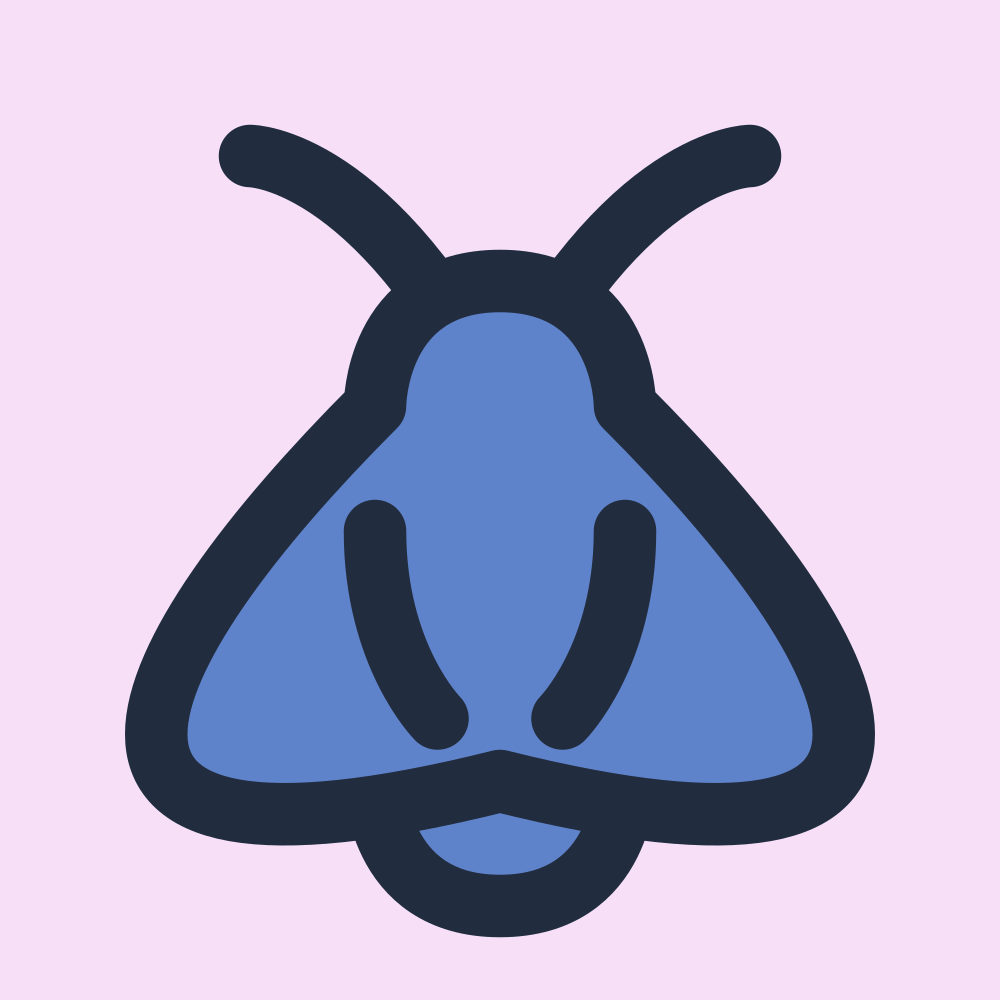
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

渡邉英徳氏がやっている戦前写真のカラー化って生理的な嫌悪感があるんだけど、批判している人けっこう少なそうだな...。これくらいしか見つけられていない。
https://chuokoron.jp/history/121375.html


映画のデジタルリマスターも問題としては似ているんだけど、渡邊氏のアレにたいする生理的な嫌悪感のようなものはない。この嫌悪感なんだろうなっておもっている。

デジタルリマスターやる人たちって、「作者のオリジナルの考えに近いもの」にしようといろいろ悩んでるとおもうけど、そういうのを全部すっとばして「当時の色を再現できるように努力する」って、そもそも写真をなんだと思ってるんだ。「それはかつてあった」なんてもうどうでもよくなっている。

最近、ヤフオクで明治時代の絵葉書とかを見ていて、実際に手紙として利用されたものがけっこう売られている。資料としてはおもしろそうとおもいつつ、怖くて買うには至らない。人が生きていたことの痕跡にたいする畏怖みたいなものが、自分のなかにはある。

Twitterで故人のアカウントをそのまま残しておいてほしい、とかそういうのもたぶん似ていて、それを破壊したり改竄したりすることに冒涜だという意識があり、素朴宗教的な感情で、不合理なものだとおもう。
https://twitter.com/lo48576/status/1426947900660060161
> https://twitter.com/Elvis_Trauss/status/1426857982931869705
>
> 白黒写真のカラー化の次の段階は「人工知能で動画化された静止画写真が、当時の記憶を鮮明に伝えます」になるのだろうと考えると、確かにそのとおりだなぁ
https://twitter.com/lo48576/status/1426949548094545921
> そういえば戦争について伝える文脈では「引用では原則として引用元を改変するな」という原則にも反しかねないわけか >戦時中の写真資料のカラー化

実際にその写真に撮られた風景を見た人の意見を反映してカラー化するのであれば価値はあるだろうけど、結局はニューラルネットワークによる自動色付けでありニセモノでしかないという気持ちが強い

この衣川太一氏は戦争期の写真についてのアーキビストなんだな。
https://twitter.com/Elvis_Trauss/status/1426857982931869705
この本おもしろそう。
https://www.iwanami.co.jp/book/b619887.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

西洋だと木版→銅版→石版という技術の変遷があり、西洋絵画の明暗表現もあって、版画表現も明暗の階調として作られていたけど、日本だとずっと錦絵が強くて、江戸後期から明治初期にかけてかなり色彩の強い表現が好まれていた。日本にも石版画の導入で木版画が次第に廃れていくけど、絵双紙屋では並べて売られている。そのときたぶんカラーじゃないとぱっと質が低く見えるので、着彩していたと思われる。

Facebook開いたらピンポイントに狙われていた


明治時代に銅版・石版と導入されて、活版と大量印刷のための刷版の登場で、平面や絵画面についての意識がどのように変わったのか、しばらく考えている

@polidog 当時はAdiumをつかっていて、ひとつのクライアントから全部見れたんですけどねぇ...。

ヤフオクで「明治 石版画」でいろいろ出てくる。おおくは手での着彩だけど、なかには多色刷りもある。多色刷りは紙面に収まって見えるけど、着彩はすごく異質なものがある。ていうか異質なシステムでつくられている。
https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?auccat=&tab_ex=commerce&ei=utf-8&aq=-1&oq=&sc_i=&fr=auc_top&p=%E6%98%8E%E6%B2%BB+%E7%9F%B3%E7%89%88%E7%94%BB&x=0&y=0

衣川氏のこのツイートに「カラー化した方が、より多くの情報が得られるだろうに。ネガティブな反応をする、意味がわからん。」というのがぶらさがっていてかなり興味深いんだけど、フィクションによってできあがった色から「情報」が得られると考えているんだな。

ChatGPTに「著名な美術史家を一人あげ、主要な論文について教えてください」って聞いたらデタラメを教えてくれたんだけど、そこで生成されたテキストに「情報」はあるんだろうか

これ、ロラン・バルトだったらなんていうんだろうっていうのが、まじで気になっている
Our vision: To achieve our vision to make the web work, for everyone, we uphold the following core values
The web is for all humanity
The web is designed for the good of its users
The web must be safe for its users
There is one interoperable world-wide web
https://www.w3.org/news/2023/draft-note-vision-for-w3c/


いまさら気付いたけど、Threads って会話中心に考えているからアイコンが @ マークで名前も "Threads" なのか