尊皇攘夷は明治維新期のものだとおもっていたけど、この座談会のなかでは、反文明開化論として提示されていてびっくりする。これは現代的な問題でもあると感じる。

尊皇攘夷は明治維新期のものだとおもっていたけど、この座談会のなかでは、反文明開化論として提示されていてびっくりする。これは現代的な問題でもあると感じる。

日中戦争、ズルズルと事実上の占拠みたいなことをしながら現地の抵抗にあい、結果的に泥沼にはまりこんでいきながら、明確な宣戦布告は数年経って英米に対しておこなう(1941年の真珠湾攻撃)という流れ、まじでいまの状況を想起させる...。宣戦布告をしてこなかったので「支那事変」なんて呼び方を閣議決定していたりとか。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日中戦争


戦争というか、その支那事変の目的も、後付けで大東亜共栄圏という概念が提示され、いやそれはたしかに満州の建国あたりからそのようなビジョンはあるていどあったものとはおもわれるが、しかし米国への宣戦布告によってようやく「反・欧米帝国主義」としての性格づけをおこなったわけで、「ヨーロッパによるアジアの植民地化からの解放が日中戦争なんだ」というストーリーがあとづけの合理化であることは疑う余地もない。あとから言い訳のように「思想」がつむぎだされて合理化されるらしい過程があるのも、似ている。

竹内好による「近代の超克」論考(1959年)は、大東亜戦争をどう捉えていくか、そのなかで文學界の座談会「近代の超克」をどのように位置付けるのか、戦争と思想の関係の理解としてかなり考えさせる、というかいまでも重要で未解決の問題をそのまま指摘しており、自分たちがたんに忘れているだけなんだということをあらためて考えさせられている。
https://www.amazon.co.jp/dp/4572001235

実態としての日中戦争は帝国主義であるにもかかわらず、英米への宣戦布告によって「反帝国主義」のストーリーが掲げられたとき、文学者や思想家たちはそのストーリーに、文明開化いらいの西洋文化消化の違和感を打ち砕くものを期待していた。こういうものは、いまも噴出しうるものとおもう。欧米へのコンプレックスと歪んだ自尊心の綱引きみたいなものは、いまでも無反省なまま存在するとおもっている。当時よりはましになっているというか、魔封波みたいなやつで封じこめられている。
https://pleroma.tenjuu.net/notice/AU53FLji17xmlX2Ray
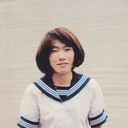
This account is not set to public on notestock.

インライン要素、ブロック要素という概念が残像として残っているのはわかるし、ぶっちゃけLivingStandardのモデル化は概念わかりづらすぎてインラインとブロックっていいたくなるのもわかるし、残像があるていどまで有意味に作用してしまうのもわからなくはない(この残像があるからCSSで display: block とかつくっているんだろうという気もする)。この残像を概念という語で呼ぶのはたんに議論を混乱させているだけっぽい(もと記事の書き手は残像ではなく実体だとおもっているんだろうけど)。