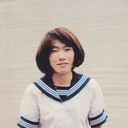メモ
https://blog.jxck.io/entries/2016-04-16/stale-while-revalidate.html



HTTPキャッシュ、完全に理解したってなっても意図と違う振る舞いになっていることがけっこうある



原稿用紙のように書くための場と読むための場が分かれているのと、WYSWYGのように書く場がそのまま読む場で、リアルタイムにプレビューされていくと、文体がめちゃくちゃ変わると思うんだよな

分散SNS、サーバーを超えてコミュニティ形成しづらいというのが現状の課題な気がするなぁ。コミュニティ形成するにはローカル使う以外にいまのところあんまり手段がなくて、そうするとコミュニティ的な活動したいときにそこにアカウント作らないといけない。複数アカウントの運用なんてめんどくさくてやらない。

連合内でコミュニティを形成するようなものがないと、分散SNS全体は発展しないんじゃないかな。HTLって個人のものだから、個人が楽しむというのは十分あるけど、それだと全体が発達するには弱い。

連合内でコミュニティを発展させるようなアイデアに欠いているから、特定のインスタンスに人が集中するっていう順番だよね。

どう読んだら自分が規制のないtwitterを求めていることになるのかぜんぜんわからなかったけど、スクショとかすごくtwitterっぽい。
https://pawoo.net/@mickeyhat/109973285715401103

結局コミュニティという「ひとつの場」を規定してしまうと、その管理は誰がやるの? という問題が発生して、これが割と本質的につらい #distsns
多数決にしたっていいんだけど (クソ面倒だろうけど技術的には可能なはず)、それはそれで、いちいち多数決の投票をしないとメンバーを追加できないようなコミュニティって果たしてカジュアルに使われるようになるだろうか?

連合上であるグループを作ったとして、作成者がモデレーターをやるようになればよさそうだけど、この場合グループ的な概念をActivityPubで扱えないと意味がない。具体的なソフトウェアの実装でしかないと、ソフトウェア同士の連合はでしかない(ほかのソフトウェアが追従する理由がない)。
結局のところ、分散型でいい感じにやっていくには「ひとつの正規の (誰から見ても同じになる) リソースを共有する」というスタイルを回避したくなるし、「クラスタ」ではなく「コミュニティ」 (?) という文脈ではだいたい暗黙に「共通のビューの共有」になってしまうので相性が悪い
フォローグラフの粗密によるクラスタという概念をぼんやりとなあなあで扱う方がたぶんうまくいくと思うんだよな
じゃあどうするかというと、たとえばフォローに “色” をつける (「技術系文脈でのフォロー」と「イラスト系文脈でのフォロー」を区別できるようにする) みたいなことは考えられるんだけど、それって結局リスト機能じゃない? という

自分のタイムラインを構築するという意味ではフォローでいいんだけど、リストは自分に見えるビューなんだよな。自分がコミュニティっていっているのは、自分の活動を帰属させるような場だけど、「所属」みたいな概念がいまのところ具体的なサーバーにしかない。

複雑さのはなし / morrita - Message Passing https://messagepassing.github.io/016-complexity/01-morrita/



これやっぱりこのへん言ってることわからないな。先日ioが閉じてたときに自分はなんの問題もなかったので、それはフォローしているネットワークによる。で、misskey.ioがローカル志向で連合とのコミュニケーションとらないユーザーが多いのなら、連合側から見るとたんに独立性の高いサーバーに見えるだけで、「肥大化したサーバーに小規模サーバーがぶら下がる」なんてことにはなっていない。
> 結果、肥大化したサーバに小規模サーバがぶら下がる形と相成り、それはなんだか民主的な分散型というよりは単にオーバーヘッドが大きいヘゲモニー政党制に見える。ひとたび前者が障害で停止すれば後者のユーザも大量のFFと断絶するため実用性は従来のSNSと大差ないか、むしろ低い。
https://riq0h.jp/2023/03/05/102540/
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これはやっぱりハッシュタグみたいなのをどう使うかになるんだろうか
https://pleroma.tenjuu.net/notice/ATJZsanDqEvFhcMTb6