ほかのサイトから無料版の論文を探してくれるブラウザ拡張機能「Unpaywall」 | ギズモード・ジャパン https://www.gizmodo.jp/2017/05/unpaywall-finding-a-paper-free-version.html
ほかのサイトから無料版の論文を探してくれるブラウザ拡張機能「Unpaywall」 | ギズモード・ジャパン https://www.gizmodo.jp/2017/05/unpaywall-finding-a-paper-free-version.html

オタクの方が現実世界でネットスラングを使うのを避けようとして,むしろ用いた方が常人的にはもはや自然な場面ですらそれを避けてしまった結果,却ってオタクであることを露呈してしまうの,社会言語学の過剰修正的な趣があって面白い.
三単現のsをつけない英語をしゃべっている人が,フォーマルな場で発言を強いられて,社会的に威信のある話し方をしようとした結果,つけなくていいところにまでsをつける,というような現象(あるいは日本語なら「ら抜き言葉」でも近いことが言える)を過剰修正(hypercorrection)という.
発言者の意図しない形で本人の社会階層や教養水準が露呈する場合がある点で,過剰修正の問題は結構sensitiveでもあるか……
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
西暦で書いた書類を全て元号に書き直しさせられるという,ぶっちぎりで今年最高のクソ・オブ・クソ案件が爆誕した.
「留学生は西暦でもいいですが……」とか抜かしている時点で統一する目的でもないし,まったくもって意味が不明.
加之,締切直前に書類の様式がしれっと変わってるのも,早めに行動している人間が馬鹿を見るあたり,ザ・大学事務って感じで最高(最悪).
等位接続詞によって直前のものを説明するepexegeticな用法(=単なるandではなくnamely, in other wordsに近い)は,ラテン語だとet (OLD s.v. 11)にそういうのがあるのははっきり認識していたけど,-queではどうだったかなと思ってOLDを引いたら,ちゃんと書いてあった(OLD s.v. -que¹ 6)し,何ならetよりも細かく割ってある.
そのまま続けてOLD -que¹の7を見たら,(linking alternative possibilities which cannnot simultaniously be true) 'Or'; -que .. -que, 'either .. or'とあって,つまり同時に真ではあり得ないものもラテン語ならand相当の-queで繋いでしまえる,というのが書いてあった.
英語圏の編集者が-queをor相当の-veに「修正」しようとするのを何度か目にしたことがあるが,上記のような同時に真ではあり得ない二つの事柄は英語ではandでは繋げないというのがあるのかもしれない.
否定辞の効果の継続についてという異なる文脈だが,-queと-veについては前にも見たことがあった.
https://gnosia.info/@ncrt035/101028395536517663
ラテン語の-queと-ueについてというのは大分マニアックな話にはなる.
否定文に対して-queで接続された要素にも否定の機能が継続することがあって,そういう場合にこのqueをueに修正しようとする人もいるけれどもハウスマンは『アストロノミカ』1.475の注釈で慎重な態度をとっている.
多くの箇所でこの用法があるため,その全てを写字生の誤りに由来するとはできないという.
que ad negationem continuandam adhibitum hic et passim Bentleius in ue mutauit. exempla particulae sic positae apud Manilium et alios poetas tam sunt frequentia ut omnia scribarum errore orta esse non possint: ergo retinenda sunt omnia, nisi alia accesserit offensio, ut III 15.
なおそれに続けて,もちろんそれらの箇所が破損している可能性はあると断り,写字生が内容を考えず盲目的にueという文字列をqueに書き換えてしまうことがあるという話をして面白い例を挙げている.
ac tamen ex toto numero nullus usus locus est qui corruptus esse nequeat; nam librarii quam caeco impetu que pro ue substituerint ostendit codex Palatinus in Verg. buc. III 60 ab Ioque principium exhibens.
ウェルギリウス『牧歌』3.60にある「ユッピテルから始めようab Iove principium」という有名な,およそ中身を考えて読んでいると間違えそうもない箇所を(しかもこの場合の-ueはIuppiterの奪格をなす一部で接続詞ではない)Ioqueという無意味な文字列に書き換えてしまっているという.
実際のVaticanus Palatinus lat. 1631( https://digi.vatlib.it/mss/detail/Pal.lat.1631 )の画像を見てみる.上から3行目が問題の箇所.ただこのキャピタル書体はIとLがとてもよく似ているのでややこしい(上の行のALTERNIS, 下の行のILLEと比べてみると微妙さがわかる).一応Qは消して修正しようとしたように見える.
#exerc_palaeogr_lat

バス「73系統」が2つ、外国人乗り間違え多発 観光地・嵐山行きと生活路線が隣で発着(京都新聞) - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191202-00186694-kyt-l26
キケローの受容に関する本が出ていた.ローマ帝政期を通じてキケローがどのように読まれ,研究され,伝承されながら,ラテン世界の教育における規範となっていったか,という内容らしい.
Cicero and Roman Education: The Reception of the Speeches and Ancient Scholarship
https://doi.org/10.1017/9781107705999
Bryn Mawrのレビュー
http://bmcr.brynmawr.edu/2019/2019-11-30.html
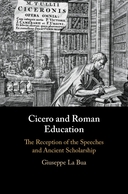

そういえば岩波の『書物誕生』シリーズ,刊行開始当初は実はラインナップにルクレーティウスが入っていたんですよね…
http://litterae.blog8.fc2.com/blog-entry-1650.html
よく「今日は〇〇字書く」とか「今週は〇〇字書いた!」という感じで進捗の話をしている人を見かけるのでふと思ったが,自分の場合にはあまり進捗を文字数で表さないことに気づいた.
たぶん,普段何か書く場合は,細かい目次立てと各section, subsection, paragraph単位で何が言われなくてはいけないかの一覧を作成してから,それをひとつずつ潰していく,というやり方なので,作業進捗はそういうparagraphをいくつチェックしたかで計るのであり,単純な文字数は指標にならないからと思われる.
なんかまた新しい本が出るらしい.来年1月発売予定.
「人類は文明の始まりに世界と魂をどう考えたのか。古代オリエント、旧約聖書世界、ギリシアから、中国、インドまで、世界哲学が立ち現れた場に多角的に迫る」
世界哲学史1――古代Ⅰ 知恵から愛知へ 伊藤 邦武(編集) - 筑摩書房 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784480072917

「世界哲学」というワードを聞きなれないのでggったらソヴィエト科学アカデミー編集の『世界哲学史』11巻本が出てきて笑ってる
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000096-I010156314-00
BIOSは起動時のOS読み込みや入出力制御を担うなどコンピュータの生命線とも言える大事な役割を果たしており,その重要性は古代ギリシア人もすでに認識していて,彼らは生命のことをβίοςと言います.
前のSciesaroさんの論文,ルクレーティウスにおける再生のモチーフに注目することで,この作品の悲観的な側面にばかりフォーカスするのではなくポジティブな面が見えてくる,という意味のことが含まれていたと記憶しているが,そもそも「解体」や「崩壊」がネガティブなものであるという前提的な価値観を疑った方がいいのかもしれない.