千葉成夫が、具体や反芸術、もの派を通して「日本の美術が美術未成の状況下で世界とのかかわりそれじたいを美術たらしめようとしてきたものである」というのは、「日本には近代がない」とか日本未成熟論と裏腹なんだよな。

千葉成夫が、具体や反芸術、もの派を通して「日本の美術が美術未成の状況下で世界とのかかわりそれじたいを美術たらしめようとしてきたものである」というのは、「日本には近代がない」とか日本未成熟論と裏腹なんだよな。

もの派、たぶん風景論と同時的に登場してきているし、1970年代の美術手帖で松田政男や中平卓馬がけっこう執筆しているから知らないはずないんだけど、まったく問題意識がまじわっているように見えない。

というかほぼ逆のことをやっているように見えるんだけど、これらを同時期に成立させるようなエピステーメーをなんか考えることができるんだろうか。いやできるんだろうけど全然予想がついていない。

具体→反芸術→もの派と、美術未成から美術の成立までを探るという歴史観が、そもそも成熟をモデルにした物語になっている。

武蔵美でやってる大辻清司の講演聞いてる
大辻清司が撮影した八木一夫の作品集と、奈良原一高が撮影した八木一夫の作品集があり、奈良原のは表紙にデカデカと奈良原の名前が記名されているが、大辻のにはない、そこに大辻という写真家の特徴がうかがえる、という話興味深い

筑波の学生だった大日方さん(講演している人)が、筑波の先生だった大辻清司に会いに行ったのが、「風景論」が気になっていたからだったとか。「略称・連続射殺魔」に興奮したという話がでてきた。1983年。

大辻清司は、 the new landscape in art and science (ジョージ・ケペシュ)とToward a social language(Nathan Lyons)の2冊を教えてくれた
https://iss.ndl.go.jp/sp/show/R100000039-I000767808-00/
https://archive.org/details/towardsocialland00lyon
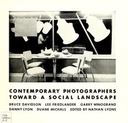

話を聞いていて、大辻清司の写真の特徴に以下の2点がある。
場があり、そこに人やモノが交錯する。人間と物質展の撮影でも、作家だけでなく作品の周りを子供が走っているさまなどを撮影している。
もう一つは、技術への関心。クロストーク/インターメディアでも技術者や回路などを積極的に撮影している。

「クロス・トーク/インターメディア」のこれを買って読んだけど、これはけっこう買ってよかった。複数のメディアの交差点として「インターメディア」が云々されていた時期があり、これはマクルーハン受容のひとつの側面なんだろうな。この翌年に大阪万博があり、この時期の技術楽観主義もよくうかがえる。
おそらく、この流れに抵抗するかたちで provoke や風景論がでてきたと考えることができそう。
https://mauml.musabi.ac.jp/museum/catalogs/20109/


流れの底流として実験工房があり(大辻も実験工房のメンバー)、「空間から環境へ」「クロス・トーク/インターメディア」、大阪万博という流れ。「クロス・トーク/インターメディア」の参加者に美術批評家の東野芳明がいて、ああなんとなくなるほどみたいなところがある。
https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2

東野芳明のこれもけっこう興味深いなとおもったけど、「虚像の時代」は手に入りそうにない。
https://bijutsutecho.com/magazine/series/s19/19748
