"合意案は法的拘束力はなく、実効性を持たせるための仕組み作りは各国に委ねられている。日本では、国際ルールに沿う形で国内向けの事業者ガイドラインを作成中で、年内の完成を目指している" https://digital.asahi.com/articles/ASRCZ74G3RCZULFA01G.html?ptoken=01HGHK3QQY1NE9BT8VXTCCR72H
"合意案は法的拘束力はなく、実効性を持たせるための仕組み作りは各国に委ねられている。日本では、国際ルールに沿う形で国内向けの事業者ガイドラインを作成中で、年内の完成を目指している" https://digital.asahi.com/articles/ASRCZ74G3RCZULFA01G.html?ptoken=01HGHK3QQY1NE9BT8VXTCCR72H

"このような「巨悪の陰謀を暴く」集団的な政治的ゲームは、米国に先行例がある。2014年のゲーマーゲート事件である。ゲームの女性表現を巡る対立を土台として、匿名掲示板のユーザーが集団化し、デマ、陰謀論、フェミニストへの嫌がらせを繰り返した。これは、オルタナ右翼やQアノンの前身と言われる" https://digital.asahi.com/articles/DA3S15534212.html?ptoken=01HGHK16X19K2VTAEAKFCTAJJ8

"演劇研究者の川崎賢子さんは、劇団員の「徹夜でなんとかした」といったエピソードが、劇団員やファンの間でも美談としてとらえられがちだと指摘する。近年は、劇団員のわずかなミスや未熟な部分もネットに書き込まれるようになり、完璧を求めてかえって萎縮する風潮が強くなってきたことなども背景にあるという" https://digital.asahi.com/articles/ASRCZ5Q1XRCSUCVL018.html?ptoken=01HGHQPB8TV5KT59R2H55PBB2N

"空自の元戦闘機パイロット(空将)は、「『いずも型』に10機程度のF35Bを載せたところで、早期警戒機を飛行させなければ艦隊防空なんておぼつかない。艦と戦闘機をどうやって守るのか」と指摘する。 次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのか、という部隊運用の根幹に関わる問題にも結論が出ていない" https://digital.asahi.com/articles/ASRC632WHR9WTOLB014.html?ptoken=01HGHQTV3MHC6KCAC4XK1SWRKG

"体育局体育官として、98年度の学習指導要領改訂を担当した石川哲也・神戸大学名誉教授も、規定ができたのは「だぶり」を避けるための「区分け」だったと認識する。92年から小学5、6年に保健の教科書が導入されたことが一つのきっかけとなり、「小中高の教科書が、どれも同じような内容になってしまう懸念があった」と話す" https://digital.asahi.com/articles/ASRCY6V39RCXUTIL03G.html?ptoken=01HGJ6QNVEF5696XRMHM0Q45Q4

"食い下がって質問を重ねる記者を、ある幹部はこう言って、にらんだ。「迷惑だ。こんなことをされたら信頼関係がなくなる」。疑惑に向きあわない姿勢こそが国民との信頼関係を失わせているという自覚がないのだ" https://digital.asahi.com/articles/ASRD15RCWRD1UTFK00H.html?ptoken=01HGJQA3VHRX6AFV5DPW04TBGC

"上智大の音好宏教授(メディア論)は「いま、取材情報のやりとりや管理は、ネット空間に依存しており、流出しやすい環境にある」と指摘。「報道は取材対象者との信頼関係で成り立っているが、報道目的以外で流出したことは、その信頼を損なう重大な失態である。流出の原因究明をし、関連会社の外部スタッフも含めて、メディアの社会的な責任やその役割を学ぶ場が必要だ」と話す" https://digital.asahi.com/articles/ASRD16WCGRD1UCVL04W.html?ptoken=01HGJSZTK763CNCMCPN3BQ3Y1Y

"元北里大特別研究員の三崎裕子さん(日本医史学会会員)は、宇良田について「時代の扉を開いた一人」と評価する。当時、日本はもちろんドイツでも女性に学位を認めない大学が多いなか、「常識にとらわれず、自分の可能性を信じて挑戦した野心的な女性」という" https://digital.asahi.com/articles/ASRCX6RSRR8YTLVB00F.html?ptoken=01HGKM5DPW3SJE4B5F7N9KM1C4

"上脇教授の開示請求に対し、法務省はほとんどの文書を「作成していない」などの理由で不開示とした。原告側は「公文書管理法などで作成が義務づけられており、不存在はありえない」などと主張している" https://digital.asahi.com/articles/ASRD16KKHRCYPTIL01S.html?ptoken=01HGKD14K161Y4WQDRW5HQYJTQ

"現在の「生活保護」という名称や「扶助」などの用語が、生活保護制度が恩恵であるとの誤解や、生活保護に対する偏見の原因になっていると指摘しています。そのため、生活保護法の名称を「生活保障法」に変更し、「扶助」を「給付」、「被保護者」を「利用者」と変えることなどを提言しています。これらの変更により、生活保護制度が私たちの「権利」であるということがよりわかりやすくなるというのが日弁連の主張です" https://digital.asahi.com/articles/ASRCY56J2RCXULLI001.html?ptoken=01HGJWTWDXSZSBCRV6YXQ5F4RE
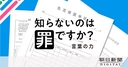
"とどのつまり、女性がより主体的に生きられるよう声をあげるや、目ざとく宗教右派の人がやって来て、地元の議員を抱き込み、右派メディアと恐るべき結束力で連携し、活動を潰してきた三十年の歴史だ" https://digital.asahi.com/articles/DA3S15807283.html?ptoken=01HGKZ2RFX6RFND97TB52KDP29

"新潟史学会の原直史会長(新潟大教授)は「世界遺産登録に前のめりになるあまり、県民と研究者の努力の結晶である県史を軽視するかのような知事の姿勢は問題です」という。県立文書館の対応も疑問視する。「元の所蔵者の許可なしに資料を公開できないのはまだ理解できます。しかし、資料の有無すら明らかにしないのはおかしい。なんらかの圧力に屈していると疑われて当然でしょう」" https://digital.asahi.com/articles/DA3S15807123.html?ptoken=01HGKZQW83GM399PQSBDDSFJTG

"安倍派関係者によると、購入者が議員事務所に入金する場合、ノルマを超えた分は議員側が派閥に納めずに裏金化し、派閥の収入として記載されないケースも多くあるという。安倍派関係者の一人は取材に「ノルマを超えた分は派閥に申告せず、全て事務所の裏金にした。この場合、派閥は実態を把握しようがない」と証言した" https://digital.asahi.com/articles/ASRD16FDRRD1UTIL02S.html?ptoken=01HGM06R13APPVTNY3PBF6YBRT

"文化のあり方に大きな影響を与えたのが、民族の言葉への圧力だ。アイヌ語を禁止・制約した法令はないが、開拓使は1871(明治4)年の布達で「言語ハ勿論文字モ相学候様可心懸事」と示し、アイヌ民族は日本国民として日本語を学ぶことが当たり前とされた" https://digital.asahi.com/articles/ASRCY5KKNRCXIIPE00M.html?ptoken=01HGM1AT9XJEFJTRWZSXQ7SE9H

"宮﨑は絵コンテを5つのパート(A、B、C、D、E)にわける。それらは芝居の幕のようなものではなく、各パートが映画のおよそ20%に相当していた。ある映画の制作が発表されるときには、宮﨑はすでに素晴らしいイメージとあらゆるディテールをもってパートAを仕上げていた。そしてパートBの大半が頭のなかに入っていた(中略)。映画の制作は、宮﨑がパートCを描きはじめた時点で始まった」 だが通常、パートDになると疑念が生じてきた。そして終わり方がわからぬまま、「制作の行程はスピードが落ち、滴がポタポタと落ちるほどになるのだった」。 さらに、突如としてパートEが現れる" https://courrier.jp/news/archives/344699/
