[宅地建物取引士(宅建士)勉強記録]2023年6月19日(勉強36日目、試験まで118日)0:21-0:39(18分)、累計51時間49分、基本テキスト第2編「宅建業法」(3周目)15-32頁。免許、事務所以外の場所の規制について。お風呂の中で。
免許のところからやり直し。お湯の温度が高めでのぼせてしまう。
ウェブサイト
https://mrmts.com
2025年断酒・ストレッチ記録
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i8IDRQNzp7hGpoYc1VZwCccrA5GHUimhU0sD_ejkZpA/edit?usp=sharing
この本で生殖補助医療の倫理学について書いています。https://amzn.to/3Z0JZfo
近年は小児の身体拘束について研究しています。
[宅地建物取引士(宅建士)勉強記録]2023年6月19日(勉強36日目、試験まで118日)0:21-0:39(18分)、累計51時間49分、基本テキスト第2編「宅建業法」(3周目)15-32頁。免許、事務所以外の場所の規制について。お風呂の中で。
免許のところからやり直し。お湯の温度が高めでのぼせてしまう。
火があれば真空パックのお餅ってなかなかの保存食だけど、電気やガスがないところではそのままでは食べられないので、残念な感じだよな。着火ができて炭火なんかが使えればまた別だけど、都市部の集合住宅なんかではそれもなかなか難しいよね。
(続き)まとめて推敲して書くだけの時間的精神的余裕がないので、また、こんなところでそんなものを公開したところで私にとってはほとんど何も利益がないので、断片的かつあまり読み返したりせずに書くけど、私が「哲学カフェのはじめ方」という文章を公開したのが2012年7月16日のこと。カフェフィロが『哲学カフェの開き方』(仮称)という本を出そうとしているとの情報に触れたのが同年9月23日(もちろん私はカフェフィロのメンバーではないし、むしろそれを痛烈に批判し続けていたので声すらかからず)、同書(書名は『哲学カフェのつくりかた』となっていた)を著者のひとりからご恵贈いただいたのが2014年7月8日のこと。
(続き)認定進行役構想については、2017年7月31日に園田地区会館(現在は廃館)で開催した第2回哲学カフェサミットで話したという公開の記録が残っている。
ちなみに、このときには赤井さんも呼んで登壇してもらったから、その場にいたんだよね。昨日、今回の件について教えてくれた神戸哲学カフェの藤本さんも呼んでいる。
少なくともあの場にいた人は、今回のような問題が起きないようにするために何が必要なのかということについて私が話したことを聞いているし、今回の問題は私が指摘したとおりのことが教科書どおりに行われて起こるべくして起こったということも答え合わせをすればわかるはず。
[宅地建物取引士(宅建士)勉強記録]2023年6月19日(勉強36日目、試験まで118日)11:36-12:21(45分)、累計52時間34分、厳選分野別過去問題集第2編「宅建業法」(1周目)22-45頁。事務所、免許について。歩きながらと電車の中で。
ノーミスだし大丈夫そう。まあ、これまで解いてきた問題もだいたいノーミスだけど。基本テキストで確認したあとだしね。時間はかかるけど、テキスト学習して、問題を解いて理解度を確かめて、理解が不十分なところは再度テキストで学習してからもう1回問題を解いてみてという進め方は、手堅いよね。
これには私もつい頷いてしまった。そうなんだよなあ。肝心なところでは必ず日和るだよなあ。
From: @zpitschi
https://fedibird.com/@zpitschi/110569063331689777
(続き)今回の件と絡めて哲学〔研究〕者、アカデミア、あるいは研究者を批判しているSNSの投稿が散見されますが、赤井さんは哲学〔研究〕者でもアカデミアでも研究者でもなければ、哲学の専門教育・訓練を受けてきた人でもありません。批判するなら批判するで、まずは最低限の事実を確かめる必要があり、事実に基づいて批判することが大切です。
仮に、赤井さんが以上のようなものに当てはまるとしても、そこから即座に全称的な判断として今回の件を哲学〔研究〕者、アカデミア、あるいは研究者の問題とするのは推論として飛躍があり、論理的に妥当な判断とは言えません。
これまでも、そしてこれからもそうだけど、私が誰かのことを特定せずにこの手のことを書くときには、誰か特定の個人の言動について直接言及するものではなく、ある一定のまとまりのあるSNSの投稿などを私が確認した場合であって、不特定多数の者によって一定の規模で語られていることについて言及しているものであり、外面的にも誰か特定の個人に対する言及にならないように書いているものです。
[宅地建物取引士(宅建士)勉強記録]2023年6月19日(勉強36日目、試験まで118日)18:52-19:04、19:39-19:54(27分)、累計53時間1分、基本テキスト第2編「宅建業法」(3周目)33-46頁。宅地建物取引士について。歩きながらと電車の中で。
繰り返しやっていると、それまであいまいだったところ、すなわち欠けてたピースが埋まって、理解というのか知識というのかが立体的になってくるのを感じる。
2年前に掲載許諾した著作物の使用料について通知が届いていたので、もう企画がボツになったのかなと思っていたけど無事に出版されたみたい(で、よかった)。
奥村清次・河田喜博・橋立誉史・松本孝子(共編著)『医系小論文 入試頻出17テーマ これからの医療をめぐる論点』駿台文庫、2023年
https://amzn.to/42MkbVu
計算してみたら、私に支払われる著作物使用料は3000円ほどで税金など引いたら3000円ないと思うけど、どんな本に仕上がったのかなと思って書店で実物を買ってきたので1540円の出費。実質1500円ぐらいの収入かな。ありがたや、ありがたや。
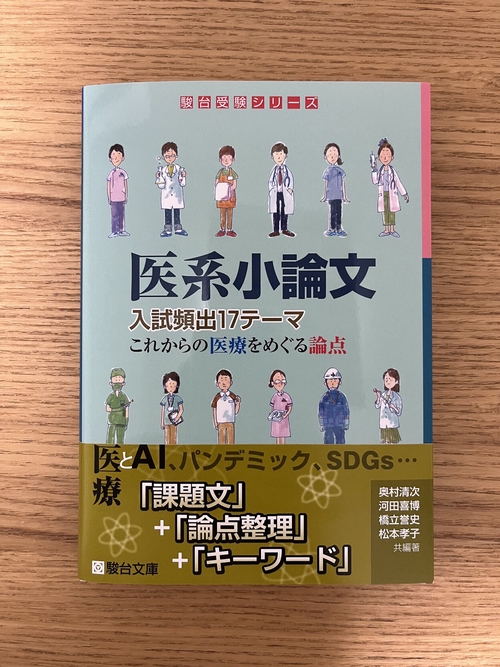
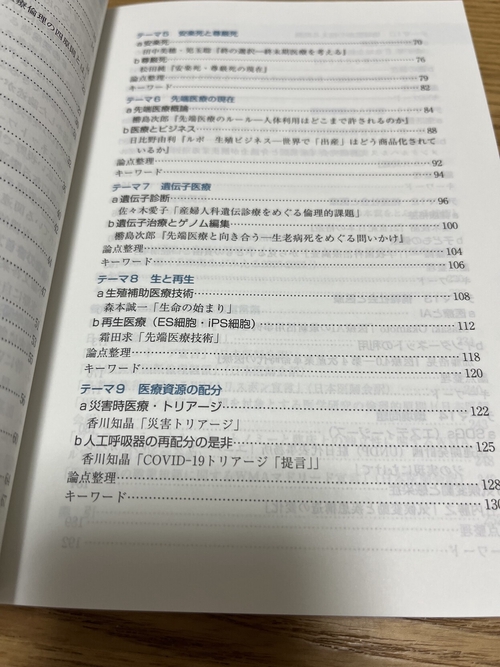
(続き)哲学カフェって登録標章でもなんでもないし、誰でも好き勝手に名乗れてしまうのよね。だから、みんながみんな好き勝手に自分の〈哲学カフェ〉を名乗って開催したりしている。中には自己啓発セミナーの勧誘(みたいなこと、と言うよりそのまんまのこと)をやっていて、それと知らずに参加してしまったという話を聞いたことがあるし、政治団体がやっているセミナーみたいなものに「哲学カフェ」という名称が使われているものも私は見たことがある。
だけど、こうした〈哲学カフェ〉はフランスでマルク・ソーテによって始められた(とされている)哲学カフェとは似て非なるものだし、その後に日本の哲学〔研究〕者や哲学の専門教育ないし訓練を受けた人たちがさまざまに実践してきた哲学カフェとも似て非なるものなのよね。
もちろん、私はマルク・ソーテの始めたカフェ・デ・ファールでの哲学カフェだけが哲学カフェのすべてだとは思っていないし、哲学〔研究〕者や哲学の専門教育ないし訓練を受けた人たちが実践する哲学カフェだけが哲学カフェのすべてだとも思っていない。哲学カフェはすべての人に開かれているし、ほんらい開かれているべきものだから。
(続き)とはいえ、すべての人に開かれているということと、それを誰しもが実践できるかどうかということとは別の話である。例えるなら、誰でも自由にけん玉を使える状態にあることと、けん玉を使って飛行機や灯台といった技ができることとは別なのである。
確かに、けん玉をどのように使うかは使う人の自由だし、けん玉を武器に使うとか肉たたきに使うとかいう人がいたとしても、「そんな使い方をしてはならない」と言う資格は誰にもない。しかしながら、少なくともそうした使い方は、けん玉を発明した人が意図したものではないだろうし、けん玉の一般的な使い方でもないはずである。
繰り返すけど、けん玉を一般的な使い方で使わなければならないなどという規則はないし、そのように言う資格を持った人もいない。けれども、けん玉を武器に使っている人がいたとして、それを見た人が「けん玉をする奴はけしからん」とか「けん玉をする奴はろくでもない」などと評したならば、それは不当な評価というべきだろう。
(続き)とても失礼な言い方になることは承知の上で書かせてもらうけど(そしてこのことは赤井さんには何度も伝えてきたことだけど)私は赤井さんが「哲学カフェ」という名のもとにおこなっているイベントを、上記の哲学カフェと同様のものとは思っていない。だから、私から言わせれば、赤井さんの〈哲学カフェ〉を引き合いに出して哲学カフェそのものを批判しているような言説は不当な評価と言うほかなく、そうした言説はまったく考慮に値しないものだと思っている。
また、仮にカフェ・デ・ファールで今でも続けられている哲学カフェを批判する人がいたとしても(私はそのうちのひとりであるが)、そのことをもって他の哲学カフェをひとくくりに批判できるものでもない。哲学カフェがあくまで個々の実践である以上、ゆるやかに共通の何かによってつながっていたとしても、究極的には個別的なものなのであるから。
(続き)ともかく、何かひとつ特殊なものの問題を見つけては、それが属しているように見える(つまり同じ「哲学カフェ」という名で呼ばれているだけの)ものをひとくくりに批判するのは筋がよくないし、仮に問題を見つけた対象物が実際に何らかのカテゴリーに属していたとしても(つまり、たんに同じ名前で呼ばれているだけでなく、同じカテゴリーに属するための条件を満たしていたとしても)そのカテゴリーに属している特定のものの問題点が、同じカテゴリーに属する別のものにも存在するかのように決めつけて評価することは、やはり不当なことである。