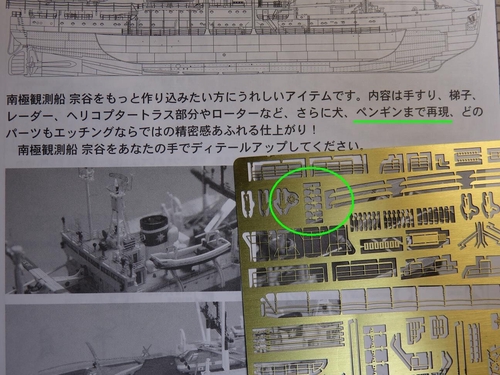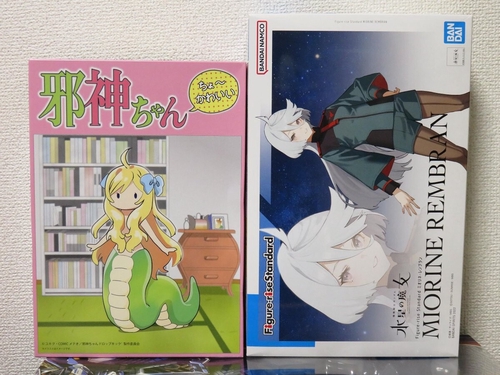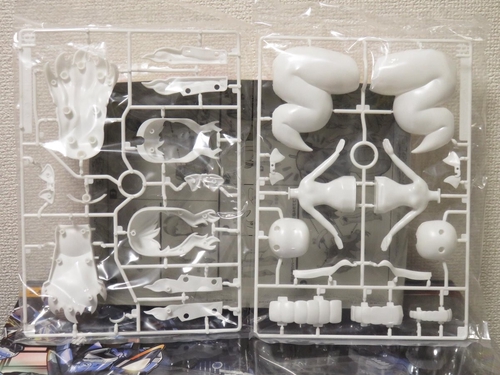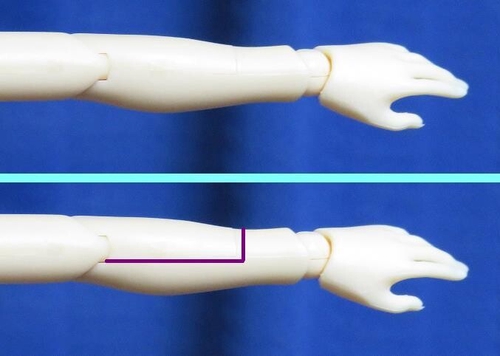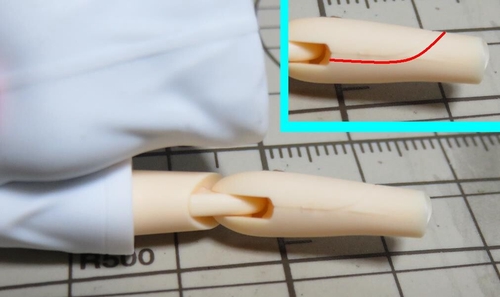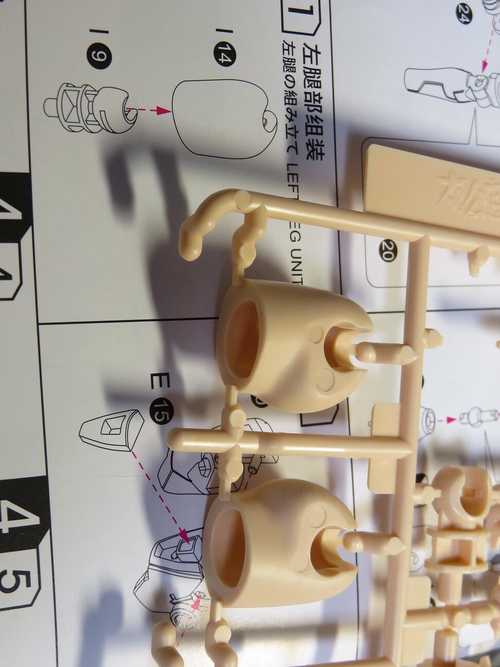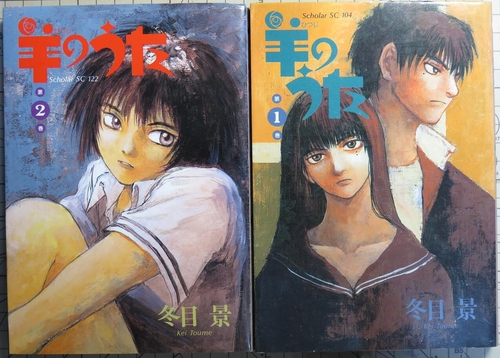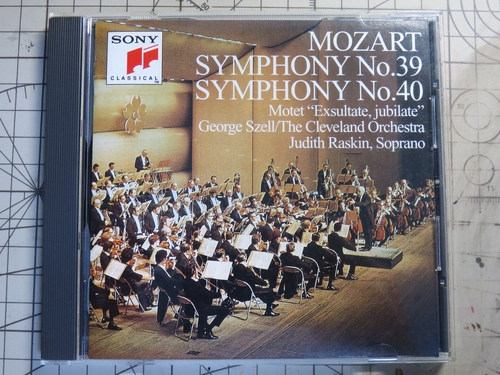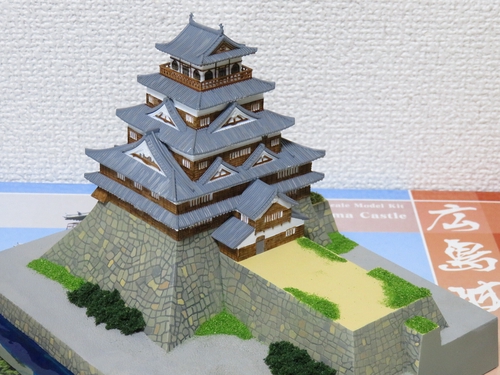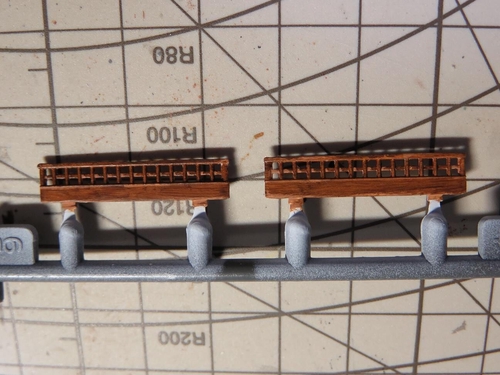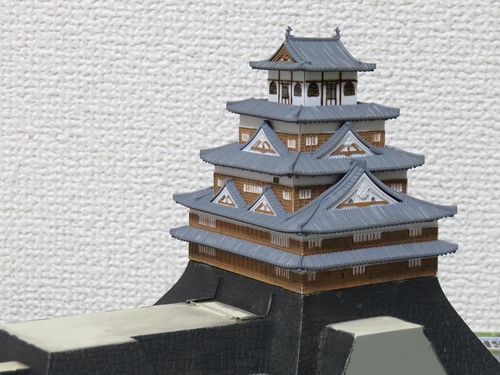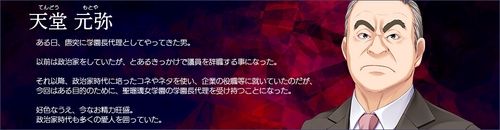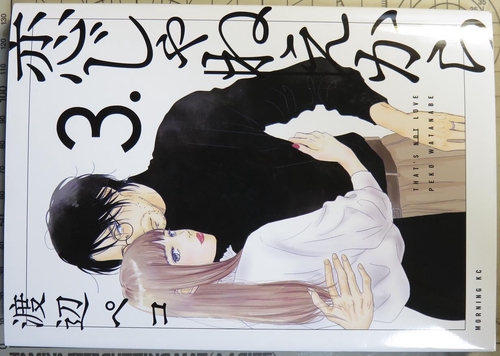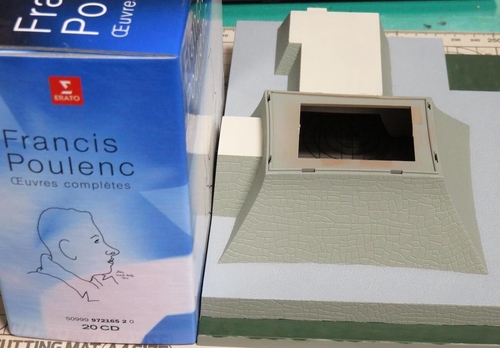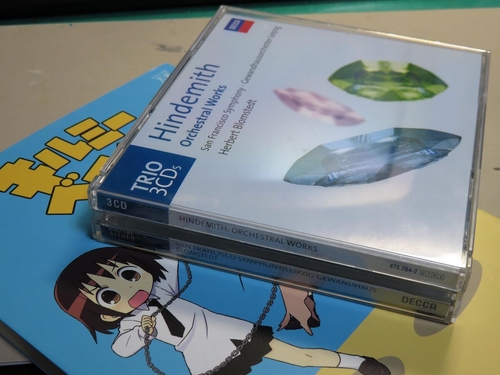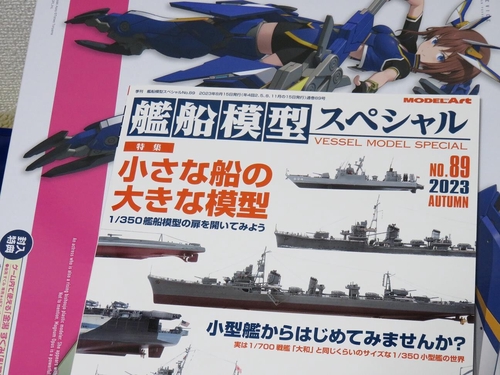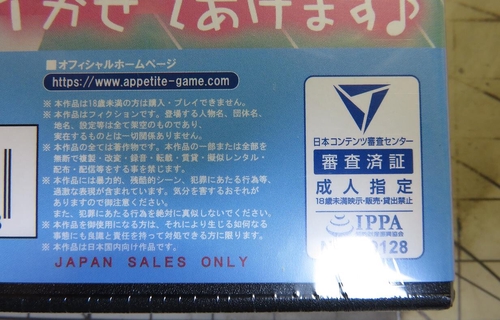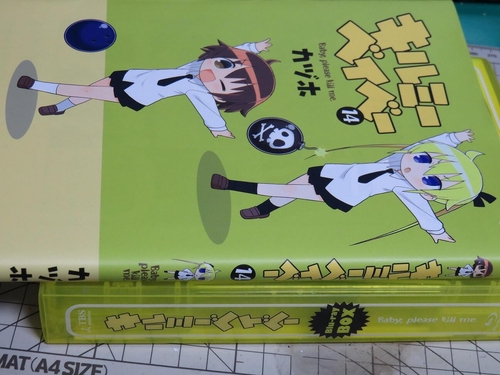単なるすれ違いとか不誠実な言及とかいった問題などではなくて、ある言及に伴った振舞いが相手(の活動やアイデンティティなどの大事な価値)を軽視するがごときものになってしまったこと。真剣な活動対象を持っていることを明示している人の前で、それを軽んじるかのような側面を含む発言をすることは、いかにSNSがその都度の発言のコンテクスト形成に関して緩いとはいえ、やはりけっしてイノセントとは言えない。
数日考えていろいろあって、ようやく腑に落ちてきたし、あらためてなんとも申し訳ない。
こちらの個人的な事情として言うと、好意的(肯定的)な言及を出そうとしつつも、あんまりストレートに反応することを躊躇ってしまうという中途半端なシャイさに胡座をかいてしまったことが裏目に出たということでもあり……私の心の余計な動きが愚かな帰結を招いてしまったことになる。申し開きのしようもない。HTLではBTが見えないので気づいていなかったんですと言っても、踏み躙られたと感じた側にとっては軽視と不知の間には何の違いも無いだろうし……。