かっこいいところに感嘆詞入ってんなぁと思ったら「は」の typo だったね
「分野での研究業績の仕方が違う?ならそちらで評価していいよ、と言われてはいるわけです。でもこれはただの分野内評価の話しで、結局ah人文系全体で査読有本数や国際的・地域的業績・社会的・文化的インパクトを問われるわけです。出てくるのは、しょぼい数字だけです」https://twitter.com/shinjike/status/1236249840155340800
かっこいいところに感嘆詞入ってんなぁと思ったら「は」の typo だったね
「分野での研究業績の仕方が違う?ならそちらで評価していいよ、と言われてはいるわけです。でもこれはただの分野内評価の話しで、結局ah人文系全体で査読有本数や国際的・地域的業績・社会的・文化的インパクトを問われるわけです。出てくるのは、しょぼい数字だけです」https://twitter.com/shinjike/status/1236249840155340800
新型コロナ予防めぐり、ギリシャ正教会と医師団体が衝突 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News https://www.afpbb.com/articles/-/3272188

ひぇ
「総人件費が減らされる中、若手・女性比率の数値目標を、それも新規採用数でなく現員数に対して無理に導入した結果、費用対効果の最も高い策が「女性限定公募で任期付き助教をとって40前に使い捨て」になってしまっていることにそろそろ気付いた方が良い」
https://twitter.com/togashi_tv/status/1236543486448394240
検索タグを組み合わせて作る検索文字列のことを「検索式」というのを知らずに唐突にこの単語を目にしたものだから,子どもたちが一堂に会して与えられた課題を一斉に検索する謎行事を思い浮かべた.
This account is not set to public on notestock.
This account is not set to public on notestock.
この本(『グーテンベルクからグーグルへ : 文学テキストのデジタル化と編集文献学』 https://iss.ndl.go.jp/sp/show/R100000002-I000010580737-00/ )の原題もFrom Gutenberg to Google: Electronic Representations of Literary Texts (https://www.cambridge.org/core/books/from-gutenberg-to-google/1937D2022BF708011D7F31818CC99317 )なのであって,例の界隈の人たちが「編集文献学」と読んでいるものの英語呼称がよくわからないんだよな.
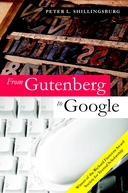
でも,文学研究に対する世間一般の理解を考慮すると(https://gnosia.info/@ncrt035/101434960280682983 ),「編集文献学」というのは――学問分野の呼称としてはともかく――一般読者への訴求の点では割と良いネーミングの気もしてきた.
月・火星での収穫にも道すじ。ISS産レタスと地上栽培レタスの栄養価に差異なし - Engadget 日本版 https://japanese.engadget.com/jp-2020-03-07-iss.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL3JEZDVxVE1ta2k_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAJgGHqZoqAyVBBddG4nm2L7PPK_3nwXCXquKktlcFMip6tiUegDJuyzZtrpeTYF-PnoSAB9qo2U1XM14aRqBtm2e2Ypr634AMUiRFLS746HWpn3Lae3_zDeX2KB0XNX5HEJLulpOdz2bJ53DLk5LMIzleCxGF8G8SCpBP68ULQJ_
This account is not set to public on notestock.
pixiv sketchに投稿したものをまとめてpixivに投稿し直せる機能があることをるいま知った人の顔をしている
https://sketch.pixiv.net/items/5638744684695773734

「怪文書」や「性癖」の誤用(「確信犯」などもそうか)は,辞書を引かずに字面を再解釈して生まれたっぽい?
「文字通りに読んだらまぁそう読めんこともない」ラインだと微妙だけど,もっと大きく意味がずれて,そのずれた意味の方が完全に定着した時点で,本源的な意味を蘇生させるとそれは reetymologize したと言えるのだろうか.
や,でも reetymologization は,もはや比喩として意識されなくなった比喩(死んだ比喩(dead metaphor))の蘇生と考えると,単なる誤用で意味が転じたのを元に戻すのは,あまり当てはまらなそう.勝手に定義を拡大すればかすらなくもない気はするが…
認知言語学の講義は学部生のときに受けたが,レイコフの本とか翻訳もあるのにあまりちゃんと読んだことがないな.愉快な先生で学生受けも良かったけど,自分のやりたいこととはちょっと違うなという感じだったので深入りはしなかった記憶がある.