このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
文化庁の世論調査(http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/r1393038_01.pdf )4ページ目では「、。」が圧倒的で,それはまあそうとして「、.」の方が「,.」より多いというのが信じられない(「、.」方式なんて見たことないぞ…)
この世論調査自体は「,。」方式で書かれている.
私は以前「,。」方式を使っており,要するに,目を下方へ引っ張る「、」を水平方向へ視線が運ばれる横書き時に用いるのが不適当であること,「,.」は印刷が不鮮明な文書で混乱が発生する恐れがあることがその理由だが,後者が問題になることはそうないだろうとの考えから今は基本「,.」方式を用いている.
句読点にあれこれこだわってるとニーカーノールのようにστιγματίαςとあだ名をつけられそう(偏見
https://lggi.stromateis.info/search.php?opt=start&fld=Word&kw=stigmatias&page=0
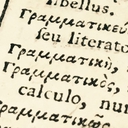
あと自分のよく書く種類の文書として和文横書き中に多くの欧文・欧語が入り,それらの直後に句読点を打たなくてはならない場合に「、。」では都合が悪いというのもある.ただしこれには「そもそもそういう事態にならないように文章を作為する」という回避手段もある(縦書き時には他に仕様がない).
『現代思想』5月号,阿部先生の「「読解力が危機だ!」論が迷走するのはなぜか?――「読めていない」の真相をさぐる」が面白かった.
新井先生の読解力テストから初めて,「読解力がない」とはどういう事態か,その原因を9つに分けて分析している.
「教科書の読めない子どもたち」というより「確かに言ったぞ」というアリバイ作りに傾く「子どもたちに読まれない教科書」の問題は全くその通りだよなーと思った.
http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3288
読解力の話題が面白く感じられるのは,私共にとってしばしば「写字生の読解力」が問題になるからかもしれない.
筆写するというのはただCtrl+Cするのとは違って書かれてあるものを読んで何らかの仕方で理解し記憶にとどめ手で書き直すということであるため,機械的に再生産されるのではなく,筆写者の個性(教養水準,明敏さ,集中力etc.)に大なり小なり依存し,その伝承プロセスで何が起こったかを適切に考察するには,「古代人・中世人の読解力」とでも呼ぶべきものを理解する必要がある.
ラテン語の口語・日常語についてはHofmann, J.B., Lateinische Umgangsspracheという本を見るのが常で,これは1951年に第3版まで出ているが,いま見ている注釈書はなぜかドイツ語原書ではなくL.Ricottilliによる2003年のイタリア語訳の方を文献表にあげている.こちらの方が良い何か特別な理由があるのだろうか(単なる翻訳ではなく内容が改まっているとか,優れた注や序文があるとか?)
ふむっ「CS6以降のアプリがいつでもすべて使える」という売り文句のAdobe CCが、事後報告すらなく過去のアプリが使えなくなった件 | Stocker.jp / diary https://stocker.jp/diary/adobe-cc/

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
目からうろこが落ちた「肩を露出させると肩の両側に服が広がるため相対的に肩が小さく見える」
https://under-bank.blue/@rk_asylum/102088237030331009

「実は九州大学には、世界的にも類を見ない450種類ものカイコがいて、「種の保存」だけを目的に、人知れずおよそ100年にわたって繁殖が続けられています……7年かかってようやく、希少なタンパク質を多く作り出す4種類のカイコを見つけ出すことに成功。いずれも病気に弱いなど、生糸の生産者などからは見向きもされてこなかった、いわば「役には立たない」種類のカイコでした」
“役立たず”から 豚1000頭分のワクチン | NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190513/k10011913981000.html
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
矛盾のない至言だ 「学校に行く必要なんかない(教育は受けろ)」
https://mstdn.maud.io/@cormojs/102088884100913219