このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
不快にさせないようにと行動したり何かと謝ったり、そういうのが裏目に出たり他人の癪に障ったりする人割といるような気がするので、気にせず好きにするのがいいんじゃないかなと。
ふむふむってなりながら読んだ.「入出力がファイルだから今の感覚で考えるとアクセスは遅い。でもメリットもあって、1回に1行しかメモリに乗せないからどんな巨大なデータでも時間さえかければ処理できる。それこそ国民ひとりひとりの年金データとかね」
COBOLってこんな言語
https://anond.hatelabo.jp/20190206222550
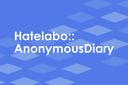
Murphy, T.(2004), Pliny the Elder’s natural History: The Empire in the Encyclopedia, Oxford University Press.
ローマ帝国の文化的産物としての大プリーニウス『博物誌』が,その内容と構造の点において帝国権力とどのように関連づいているかを論じた書物.第1章では,脱線の多く散漫な印象を与えがちなプリーニウスの記述の根底に「対比antithesis」と「連想association」という二つの原理がありそれが「多彩さ」をもたらしていると指摘する.第2章ではプリーニウスが描く世界それ自体が,ローマによる征服と組織化によって初めてその対象となりうるものであること(知識の限界と世界の限界の一致)が明らかにされる.3-4章は具体的に民族誌と地誌の描写を分析し,終章では「記念碑」としての『博物誌』が皇帝の権力に果たす寄与と微妙な緊張関係,また他の百科事典的著作や技術書との違いが扱われる.
第5章の要点を書き漏らした.周縁的存在としての「野蛮人・未開人」の描かれ方が問題として取り上げられている.
2月がもう1週間終わったとかフェイクニュースが流れているが今日は1月38日なのでそういうのには引っかからない
読んでる | オルタナ右翼を魅了する奇妙な音楽「ヴェイパーウェイブ」とは何か(木澤 佐登志) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59738

 の投稿
kumanotetu@mstdn.mini4wd-engineer.com
の投稿
kumanotetu@mstdn.mini4wd-engineer.comこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
考えてみると神話の中でも,ヘルメースは自身アポッローンの牛を盗んだ上,商売や賭博と並んで盗みを司る神だし,プロメーテウスによって人間に授けられた火ももとはこの神によって盗み出されたものだったし,いろんな場面に出てくるので「盗み」に興味が出てきた.
Murphy, T.(2004), Pliny the Elder’s natural History: The Empire in the Encyclopedia, Oxford University Press.
ローマ帝国の文化的産物としての大プリーニウス『博物誌』が,その内容と構造の点において帝国権力とどのように関連づいているかを論じた書物.第1章では,脱線の多く散漫な印象を与えがちなプリーニウスの記述の根底に「対比antithesis」と「連想association」という二つの原理がありそれが「多彩さ」をもたらしていると指摘する.第2章ではプリーニウスが描く世界それ自体が,ローマによる征服と組織化によって初めてその対象となりうるものであること(知識の限界と世界の限界の一致)が明らかにされる.3-4章は具体的に民族誌と地誌の描写を分析し,終章では「記念碑」としての『博物誌』が皇帝の権力に果たす寄与と微妙な緊張関係,また他の百科事典的著作や技術書との違いが扱われる.
そういえば大プリーニウスも序文の中で,古人の仕事に依拠していながら謝辞すら述べない著作家(今日なら剽窃と呼ばれる)を批判していて,彼自身は目次とともに典拠とした数多くの著作家たちの名前を列挙している.
その文脈でプリーニウスが借金を喩えに持ち出していることについて,昼に書いたMurphyさんの文献(https://gnosia.info/@ncrt035/101549130311609318 )が面白いことを指摘していて,つまりローマ人にとって貸し借りは金融上だけでなく道徳的にも意味があって,自己の利益のために金貸しをするとか守銭奴的な吝嗇とかはローマ的貴紳の精神とは相容れず,むしろ借金してでも他人のために使う「気前の良さ」こそが高貴とされたということがあるため,プリーニウスの不意に思える比喩は貸し借りに含まれる道徳的な意味合いを喚起し,その上で様々な知識を収集し公開する自らの活動をそうした美徳と重ね合わせる意図があるというお話(pp.62-67).