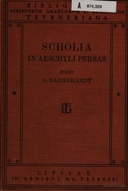ἐπιζευκτικός ------ 接続法の.
ἰστέον δὲ ὅτι τὰ ὑποτακτικὰ ἓξ ὀνομασίας, τρεῖς ἀπο τῆς σημασίας, καὶ δύο ἀπὸ τῆς συντάξεως, καὶ μίαν ἀπὸ τῆς φωνῆς ... ἀπὸ δὲ τῆς συντάξεως ὑποτακτικὰ καὶ ἐπιζευκτικὰ καλοῦνται· καὶ ὑποτακτικὰ μὲν καλοῦνται, καθὸ ὑποτάττονται τούτοις τοῖς συνδέσμοις, φημὶ δὴ τῷ ἵνα, τῷ ὄφρα, τῷ ὅπως, τῷ ἐάν· ἐπιζευκτικὰ δέ, ὅτι ἐπιζεύγνυνται τούτοις τοῖς συνδέσμοις. (Choerob. Theod. 2.275)
※ὑποτακτικάには名称が6つあって,3つは意味から,2つは構文から,1つは音声から由来するという話の中で,構文由来のもののひとつがこれ.