さいきんはやりたいことが多すぎて、それはそれで健全なんだろうけど、なにも進んでねーとなることが多い

さいきんはやりたいことが多すぎて、それはそれで健全なんだろうけど、なにも進んでねーとなることが多い
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。


「大学の自治」の定義は、歴史や国によって大きく変遷してきましたが、今日の東京大学における定義は、「大学の運営は、大学内部の『すべての構成員』の手によって、大学として自律的に行う」ということです。では、なぜ、大学内部の「すべての構成員」で「自律的に」大学の運営をしなければならないのでしょうか。それは、大学外の人が大学運営に参画すると、日本国憲法23条の保障する「学問の自由」が脅かされるからです。
では、大学の運営を担う「大学内部の『すべての構成員』」というと、どのような人たちが該当するのでしょうか。
昭和40年代の大学紛争以降は、学生についても固有の権利を持つ大学の不可欠の構成員として捉えることが、学説としても判例としても有力となっており、また特に東京大学においては、学生と総長とが昭和44年に結んだ「東大確認書」によって、大学の自治とは、教授会のみならず、学生によっても形成されていると解釈されています。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

実家から逃げ出したセクマイ学生から見た、東大の学費値上げ問題|mimosa #note https://note.com/ut_mimosa/n/na20453c6f305


芸術と客体性、だいぶ古いしそんな長くもないのに、なんとなくあそこに戻ることがあるのなんですかね
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

わかるofわかるだった
>わりとおれの根本的な関心は「なにが音から区別されて音楽になりうるのか/なにが日常的な言葉から区別されて詩・詞になるのか」というところで一貫していて、(...)この関心の根っこは実はグリーンバーグやフリード(芸術と客体性)を読んだことから来ていて
https://sizu.me/imdkm/posts/7wtvnwm17b8b
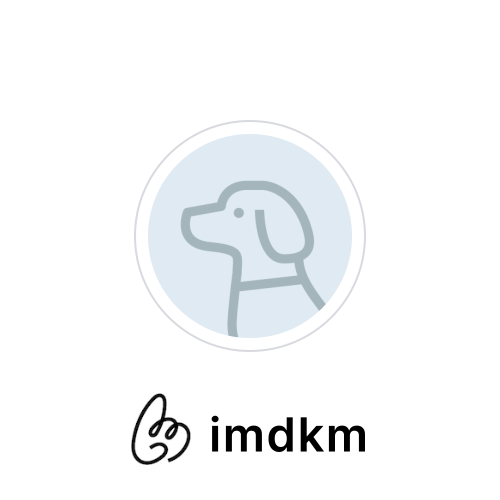

「モノがリテラルにそのものであることを超えているような状態」みたいな問題って、フリードを読むことによって与えられた問題であるのか、それとも、自分たちの時代や社会に固有の問題として取り出すことができるのかがよくわからない
フリードは、モノがリテラルにそのものである状態をリテラリズムと呼んで、それは感性の堕落であり、われわれは皆リテラリストなのだと言った、それはそれなりに時代状況に裏打ちされた批評だったけど、それはいまの自分たちの状況でも繰り返してよい問題設定の立て方なのか、どうなんだろう

自分がフリードについて再考を促されたのは、プログラミングのオブジェクト指向について考えていたときのことで、オブジェクトって関係のなかで、あるオブジェクトになるのであって、「それ自体」としてのオブジェクトというものはない(もともと、プログラムのうえに仮構された概念である)
具体論ないとわかりづらいだろうけど、書物にかんするソフトウェアをつくるとして、「本」というオブジェクトを定義するとしても、「本」という概念を内在的に定義することはできない。作られるソフトウェアが本棚に一覧されて、レビューやメモを投稿するアプリであれば、「本」というオブジェクトが抱えるのは背表紙とかメタデータとかであって、本の内容は不要。これが読書アプリであれば本のコンテンツそのものが必要になる。いずれにせよ、「本」はそのコンテキストが与えられなければ必要な情報を定義できないから、「内在的に」定義することはできない。
こういう文脈で参照されるのは、どうやらホワイトヘッドとからしいのだけど、ホワイトヘッドをまったく読んだことがない。かわりに自分はフリードとドナルド・ジャッドの観念の対立とかがなぜか参照項になるのだった。

ちょっと変な読み方すれば、芸術が芸術である状態を達成すること(あきらかにモノではない状態になること)とは、モノの相互作用によって秩序を生成する創発でもあるようにおもわれる。創発は、オブジェクト指向を提案したアラン・ケイがおそらく意識していたものとおもわれ(後付けかもしれないが)、モノがモノである状態というのは秩序を欠いた状態である。
これはフリードの視野に入っていなかった概念だとおもうけど、フリードの思考は創発特性についての記述であるとも振り返ることができるとあとから思っている。彼がカロの作品を賞賛するのは、その特性が鉄鋼だの台座だのといったモノのなかに内在するものではなく、それらの相互作用によって成立する秩序があるからだ。その秩序こそ、カロの配置するモノをモノではなくするものである。フリードはそれを「言語」だと言おうとしたけど、それはやっぱり創発という文脈で言われる秩序と近いとおもう。

グリーンバーグの重要性は、メディウムスペシフィシティとかフォーマリズムではなくて、当時のアメリカ美術の状況において、ただのモノとしか見えないものと美術の区別がつかなくなったことに対して、「美術と美術ではないものの区別はどのように可能になるか」を問うことができた唯一の人(たぶん)だったからである。グリーンバーグがダダの問題から出発しているからそういう問いになるんだとおもうけど、そこに「メディウムの固有性」とかいうフィクションを作りだしてしまったのは間違いだってフリードにも批判されている。
フリードはこの問いをより洗練させて、モノがモノではない状態を達成するための諸条件を検討することになり、これが近代芸術の真の特性だとするんだけど、それは秩序が成立する条件とはなにかという問いだと言いなおしてもいいとおもう。
この問いがアメリカ60〜70年代の美術状況において成立するのはわかるが、2000年代の日本の美術の状況で考えるのはやはりズレているようにはおもっており(つまり自分の感性はまるごとズレていたんだけど)、問いを変換したり洗練したりしないといけないという気はする。