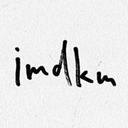親がスマホの機種変更したらLINE使えなくなったから設定してくれって言われて、それで「老人向けのスマホ」というものをはじめて触ったのだけど、使いもしないアプリを入れられまくったうえにデフォルト設定のままだと広告とニュースらしきものの通知が無限にくる。老人は設定の仕方なんてなにもわからない。端末の扱いがわからない人は、企業側の意図でクリックさせられる。スマホの通信と端末をセットで売る業者(auとか)と、インターネットメディア、LINEなどのプラットフォーム企業はけっこう邪悪なことをしているけど、わかったうえでやっているのか、それともいろいろな歯車が噛み合ってそうなっているのか。