柳宗悦についての論考が二本あったので読んだ。
https://www.artresearchonline.com/issue-14

柳宗悦についての論考が二本あったので読んだ。
https://www.artresearchonline.com/issue-14

近代の超克、亀井勝一郎の論考を仔細に検討してみると、ほんとうに「近代以前」なんだなってなる。下村寅太郎が座談会中でも論考でもかなり的確に批判している。
あと、気になるのはこれはほとんどクレメント・グリーンバーグじゃん、とかテクスト論じゃんみたいな概念の萌芽はありつつ、それが全く評価できていない、というのがなぜなんだろう。魂こそが重要で芸術はそれをやってるんだみたいな前近代的な概念になってしまう。
グリーンバーグなんかはマルクス主義の批判的な検討の果にモダニズム美学を取りだしてみせたけど、日本の当時の批評は、マルクス主義を批判しても、どうしてもロマン主義的な美意識・芸術観にとどまっている。それはなぜなんだろう。

ていうかロマン主義も近代的な運動なんだけど、それじたいが近代化に対する反動としてありつつ民族的な意識を形成することでunitedな国民になるみたいなめんどくささがある。そういうのひっくるめて近代化過程になっている。
仕方なく維新に投票するような人たちの受け皿もつくれずに、ブーだけ垂れてたって、次の選挙で次がないでしょ。いくら負けても自分が「正しい」ならそれでいいっていう未熟な市民には民主主義は向いてないんじゃない?

てかこの規模の集団の意思決定、選挙以外だとどういうのがあるんだろう。ダライ・ラマみたいにだれかが生まれかわるっていう仕組みもありでは。マンションの理事会とかランダムに選ばれていたりするし。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
それはさておき、「間違いが多分に含まれます」とその本の中に書いてあるならまだしも、そうでないなら「間違いだらけの本が出された」という歴史的事実と但し書きを込みでの価値になるわけで、いわゆる真っ当な本と同列に扱うべきかは疑問だし、それに加えて出版社がレピュテーションリスクをどう扱うかを考えれば自主回収になるのはごく自然だよなぁ
間違っている物理本を売ってしまったときに、最終的に手にした人へ確実に「間違っていますよ」と伝える手段がないからなぁ。

ゲームの歴史、けっきょく読んでいないしあまり読む気もないんだけど、そんな回収するほど有害な本になりうるか?問題ある本なんてもっとほかにある気がするのだけど。どこらへんが回収判断になったのかよくわかっていない。

レピュテーションリスクだけで出版社が自主的に回収しちゃうんだと、悪い評判たててしまえば口を封じることができてしまって今後が厄介になる気がするなぁ。ちゃんと議論を追いかけていないからそれだけではないのかもしれないけど。
つい最近も Web3 モノで回収騒ぎあったけど、まあ (こういう言い方でいいのかわからんが) 編集がザルで覚悟が足りてなかったから慌てて撤回、みたいな感じで出版社側があまり真剣に戦う気分になってないのだろうなという感じはする
書籍「いちばんやさしいWeb3の教本 人気講師が教えるNFT、DAO、DeFiが織りなす新世界」の回収について - インプレスブックス
https://book.impress.co.jp/info/20220725.html
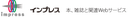
じゃあいざ本当に弾圧じみたムーヴメントが発生したとき戦えるんですか、というのは実際起きてみないとわからないし、ただ我々に見えていないだけでそういうのは日常茶飯事なのかもわからんけど

出版社の編集の質が落ちていて、覚悟もできていないっていうのは昔に比べたら本なんて売れていないんだからどうしてもあるはずなんだけど、今回みたいにけっこうどうでもいいように見える場所で(いやこれは関係者にとって必死の利害があるのかもしれないけど)、炎上から回収となると、今後出版社はますますリスクとらなくなりそうな。そうなると、書き手も主題も安牌で、確立されたジャンルの大学教授とかそういうのばかりに収斂していくとか、そういう懸念がある(けどもうたぶん避けようもない)。

サロン化もなにも、サロンでなかった時期のほうを知らない...。美術館が高くなったのは事実だけどそれはまた原因は別。
https://twitter.com/nagasek/status/1644592404954230784

@moriteppei 揶揄は通じています。リベラルに限りませんが、なぜか人を見下す言い方が常套句になってしまっていて、そういう言葉をごっそり取り替えていかないと厳しいなと最近感じているところです。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。