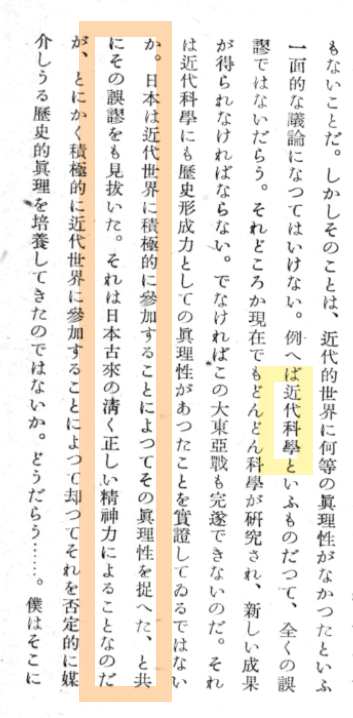京都学派、けっきょくヨーロッパ近代個人主義憎しで「総力戦」という観念のもとに、専門分化した各領域に統制的な介入をしていく国家というものを秩序だと考えていて、当時のイデオロギーそのものなんだけど、それはともかくとしても、なんというかそういう統制的な秩序しかイメージできなかったのはやはり彼らの限界だなと感じる。マイケル・ポランニーとかが彼らよりちょっと上の世代にいるけど、彼は生命の創発的な特性を社会に敷衍して考えていたわけで、京都学派の面々が新しい哲学が必要だって言っても、古いモデルしかもってこれていない。