平日はあんま仕事できてねーという自責,休日は休みなのに仕事してるという嫌悪にやられる.
なんか少し前に魚に痛覚があるのかとかそんな感じのタイトルの本が紀伊国屋書店あたりから出てなかったっけ
これだこれだ,2012年.【紀伊國屋書店出版部】2月新刊『魚は痛みを感じるか?』 | 本の「今」がわかる 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20120201145723.html

面白そう|印刷博物館:企画展示 > 天文学と印刷 新たな世界像を求めて http://www.printing-museum.org/exhibition/temporary/181020/index.html
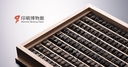
このところ別々の関心で見ていた文献に続けざまに「物言わぬ魚」という表現が出てきたので,魚類がどのような感覚を持っている存在としてイメージされてたのかが気になっている.
o mutis quoque piscibus | donatura cycni, si libeat, sonum
《おお,その気になれば物言わぬ魚たちにも白鳥の調べを授けられよう方…》(Hor. Carm. 4.3.19-20)
ἀναύδων...παίδων τᾶς ἀμιάντου《汚れなき海の物言わぬ子供たち…》(Aeschyl. Pers. 567-568)
mutaeque natantes | squamigerum pecudes《物言わず泳ぐ,鱗纏える獣ら》(Lucr. DRN 2.342-343)
verterit in tacitos iuvenalia corpora pisces《若者たちの身体を物言わぬ魚の姿に変えた…》(Ov. Met. 4.50)
キケローのCarmina Arateaには
ipse autem labens mutis Equus ille tenetur | Piscibus;《かたや他ならぬあの馬(=ペガスス座)は天をゆきつつ物言わぬ魚らに捉えられている》(Cic. Carmina Aratea, 55-56)
とあるが実は写本の読みは一致してmultis《多くの》になっており,ここでの「魚ら」とは魚座のことで魚座は2匹の魚からなるのとはいえ,それを《多くの》と言うのは好意的に取ろうにも厳しいものがあるためTurnebusの修正案を採用するのが妥当ということになる.
そういう場合も「魚にどんな形容詞がつきうるか」というのが修正を説得的にするために調査すべき課題になる.