カード番号はprefixが0ではないことによって辛うじて使えてるやつか?( https://twitter.com/lawliteqed/status/1160172750503215104
カード番号はprefixが0ではないことによって辛うじて使えてるやつか?( https://twitter.com/lawliteqed/status/1160172750503215104
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
そもそも最近のブラウザの input box って regex とか指定して validate できなかったっけ???
……と思ったけど、こういったサイトはクソザコレガシーブラウザも対応しないといけないのかもしれないしどうしようもなさそう
保全(conservation)と保存(preservation) - knsm.net
https://knsm.net/%E4%BF%9D%E5%85%A8-conservation-%E3%81%A8%E4%BF%9D%E5%AD%98-preservation-ec5a6c7ac7d6
#gentooinstallbattle ひとまず起動できる段階まで来たんだけど、 SSH はパスワードログインも root ログインも禁止してるし一般ユーザは作ってないし、そもそも root パスワードも設定していなかったので打つ手がなく、泣く泣く Ctrl+Alt+Del で再起動した
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
gcc の LTO 、ためしに -j2 してみたらクソザコ仮想4コア CPU と 4GB メモリでも十分いけたので、よわよわ環境でもちゃんと調整してやるといけるよ
次ビルドする機会があったら -j3 で試してみる予定 (メモリや CPU を観察してた限りではいけそう)
さて、そろそろ本格的に dotfiles の git 管理をしていかないといけないな
ちょっとまって、良くないことに気付いてしまったんだけど
もしかして来年の5月のコミケ時期ってまだ初任給振り込まれてなくない???
Google Chrome EV表示の終焉 - ぼちぼち日記
https://jovi0608.hatenablog.com/entry/2019/08/12/095854

www. を省略するのとか、むしろ URL の「強調」にあたるのではと思うわけですが
ブラウザが加工後の値ばかり見せてくるとユーザが自分の目や判断を信用できなくなるみたいな一面はあるのではという感想がある
taint analysis のあるローレベル言語を使って「汚染ブリ言語!!w」とか言いたい #適当

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
EV 表示がある
→ DV では信用が不十分になってしまうような重要な処理を提供している (たとえば決済)
→ 重要なので当然確認する
という思考を経てクリックしているので、 EV 表示の妥当性を確認するのは文脈を併せて考えると不思議なことは何もなく当然といえる
むしろカード情報とか入れるとき EV 表示なかったらそっちの方が不穏でしょ (少なくとも Let's Encrypt とかでないことは確認するでしょ)
eRONDOオフィシャルショップ
http://e-rondo.browse.jp/shop/index.php
ところでこれは本当にいい話なのですが、カード番号入れる通販サイトなのに HTTP 使ってて HTTPS の証明書はドメイン名不一致になってるタイプのサイトです (白目)
これ随分前にツイットしたら偉い人に捕捉されたことがあって、認識はしているらしいんだけど手が回っていないとか何とか
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
エスケープがうまくいってない系のトラブルを目撃すると、 †††バグ††† を感じてつらくなってくる
12:00 とかにサークル回ってもやっぱり大部分の中小サークルは頒布しきってないし、おそらく徹夜組してた人に売ってすらないんだろうなという感じだし🙄
もう少しは、転売屋への怒りの矛先を運営だけではなく転売屋が買いたがっている品を提供しているサークルにも向けてほしいなという感想でした。(改善は難しそうだが)
昼前に頒布完了してこのくらいが良かった〜などと言ってる出展者のツイットを目撃してしまい、いや本人の勝手だけどそれはつらい……という気持ちになった
体育の跳び箱で下半身不随に 校長は謝罪もなく「公表しないで」 - ライブドアニュース
https://news.livedoor.com/article/detail/15306210/

転売ヤーを殺すの、マジで受注生産とか十分な委託とかするべきだけど、二次創作の一部文化圏では二次創作を商業的サービスに委託するのはよろしくない的な風潮が存在し (これもまあ一理ある話ではあるのだが)、結局のところ法整備なり著作権者によるガイドラインなどが整備されないとどうしようもない
いいかげん「二次創作は日陰者で立場が非常に弱く、細々とやっていかねばならない」という圧力をなくしていかないといけないんだよな。文化的にも法的にも。
二次創作が (何故か) 一級市民扱いされていないという事実から目を背けるべきでないと思いました
創作行為に優劣つけるの、そのうち「守られるべき創作」と「守られないべき創作」の区別を生み出し、最終的に表現規制の言い訳に使われるようになるんじゃねえの (適当) (適当でもない)
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
https://under-bank.blue/@rk_asylum/102602969633302648
こういうの、たとえば OSS 文化圏だと (WIndows プロプライエタリフリーミアムソフト圏と違って) いちいちオレオレライセンスを作らず既存のよくできたライセンスを使っているわけで、そういう「よくできた許諾セット」がいくつか流通してほしいのよね
そういった試みのニュースは何度か見たことがあるんだけど、普及しているという実感はないので、まあ文化としてライセンスというものへの認識がまだ甘いのだろうなと思っている
あと、オレオレライセンス作るとき「○○は認める、××は駄目」まではいいとして「それ以外は認めない」とか迂闊なこと書いて禁止ゾーンを無闇に広げてしまうのとか本当によくないので、「○○は明示的に許可する (それ以外は従来通りグレー)」という安全側に倒した仕組みでやってほしい。
判断を完全自動化したいのでもなければ、全てにはっきり白黒付ける理由はない
@prime CC 系のライセンスは作品単位で効いてしまうので、たとえばキャラクター単位での制約みたいなものが甘くてそのままでは二次創作の許可に使いづらいみたいな話を聞いたことがあります
VRMファイルに設定できるライセンスデータについて – VRoid ヘルプ
https://vroid.pixiv.help/hc/ja/articles/360014193033-VRM%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
たとえば「アバターに人格を与えることの許諾範囲」とかってたぶん CC でうまく制約かけるには厳しいのよね
「キャラクターや設定(=アイデア)を丸ごと借り『筋書き』がオリジナルな作品」について - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
https://m-dojo.hatenadiary.com/entry/20121218/p2

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
これは本当にそうで、なのでどちらかというと無限の著作権者がいちいちガイドラインを用意するよりは法律でまとめて保護してくれと思うわけだけど、一方それ本当に権利守れているのかという判断はやはり難しく
端的には「エロは禁止!」と言ってなんでも禁止してしまう姿勢がアレなのでこればかりはどうしようもないんだけど、気持ちはわからんでもないので難しい
一般的なソフトウェアくらい “コンテンツ性” が弱いと、「用途は何でもいいが責任は負わんぞ」ができるんだけど、一般的なコンテンツは著作者の人間性の関係もあって難しいのよなぁ
頭を空っぽにしてうっかり「違法行為への使用を禁ずる」とか書いてしまわない、無闇に制約を加えないことが大事であるというのは、自由ソフトウェア界隈ではよく知られている
happy bunny license と PHP の json ライセンスの話をしようか
たとえば自由ソフトウェア文化圏では
「ユーザの自由を守る」とか
「ソフトウェアに詰まった知見は人類全体の資産で、ソフトウェアの発展は人類の発展で、ソフトウェアは独占より共有した方がよい」とか、
そういう思想が普及しているからこそ貢献とか開発が進むわけね。
で、コンテンツ創作界隈で
「コンテンツを享受する権利を守る」とか
「多くの人が自由に多様なコンテンツに触れることで人類の文化は発展する」とか
「コンテンツは共有した方が良い」とか、
そういう方向性に文化を持っていけるものだろうかというのはちょっと難しそうな問題なので、少なくとも啓蒙活動は必須だろうと思っているわけです
たとえば「コンテンツを享受する権利を守るべし」という思想があったら、邪悪な DRM を付けてコンテンツをユーザの手に渡さないみたいなことはしたくないわけですよ。
そういう、制作者や権利者の利益と、それを鑑賞する人や文化全体としての利益、どこまでうまくバランスを取るかという視点が大事だと思うわけです
そのためにはもちろん、権利侵害をする人々に対して強烈なディスアドを与えてやらないといけないし、ちゃんとした法整備が伴ってほしいけど、単純に法律だけの問題というわけでもない。
(ただまあ、たとえばソフトウェアはその応用だとかメンテナンスにもコストがかかるのでビジネスとして成立しやすいけど、コンテンツはその点でだいぶソフトウェアと違うということは認識しておくべきではある)
ansible ちょっくら弄ってみて、なんとなく私の求める方向性で環境を作る方法はわかってきたんだけど、ちょっと問題が。
playbook とかから環境を弄るのは問題ないんだけど、逆に「環境側に適用された変更を playbook のあるリポジトリ側に還元する」というのが素朴な方法ではちょっと難しそう?
まあそもそもそういう使い方するものじゃないんだろうけど。
dotfiles などをシュッとデプロイしたいんだけど、システムのローカルで変更した設定を playbook のリポジトリ側に反映させたいのよね。
ソフトウェアは著作者人格権の保護法益であるところの「著作者の人格的利益」の意識が薄い(と思う)から好き勝手にやって困ることは少ないけど、コンテンツの場合は解決すべき課題が多そう
ストーリーとかキャラクターとかイベントとか世界観とか、そもそもコンテンツを構成する要素がどう分解できるかが非自明すぎて (分解できるのかも知らんけど)、バランスのとれた扱いを考えるのが難しい
メロンブックスのDL配信同人誌を買う前に知っておきたかったこと - Stellar
http://squeuei.hatenablog.com/entry/2018/04/19/190000

メロンブックス電子書籍について - DLチャンネル みんなで作る二次元情報サイト!
https://ch.dlsite.com/matome/1515

基本的に全体的に同意で「それはそう><」なんだけど、コンピュータソフトウェアのライセンス云々の現状はどうなのかと言うと、例えばマストドンでgabが来た時にオイゲン氏と周囲の方々が(A)GPLを理解していない寝ぼけた事を言い出したのもそうだし、RMSですらLLVMサポート云々の話でGPLを理解していないとぼけたことを言い出したり・・・
つまり、何が言いたいかと言うと、おそらく自分のコードのライセンスをGPLにしてる人がそれがどういう事なのか理解してないっぽいという現状があるわけです・・・><
https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/102603457757992832
まあ逆説的に「自分が何をしているかわかっていない著者からも、鑑賞者としての権利を守れる」ということであって、メリットともとれると思います。
たとえばこれは「DRM 付きコンテンツを買うのは本を買うのと根本的に違う」ということをサービスが潰れたり BAN されてからでないと理解できないような人々からの間接的な被害を防げる
複雑な問題に対して細かく分析する余裕や知能がない場合などについても、よく振る舞いの知られたパッケージを使えるというのはとても大きなメリットであるわけで、これはライセンスに限らず一般の問題で言えることなので、コンテンツやソフトウェアの著作者がアホだからといって良いライセンスを広めない理由にはならない
既に十分長文であれだけど、cloudflareの8chan追い出しの形態の問題も微妙に関係あって、あれはそんなものを『置くな(置かせるな)』だからまだシンプルだけど、(百数十文字省略しました><;)
エキサイトすれば例えば2次創作で「エロもおk」なライセンスな時に猥褻問題になった時に「そんなもの許可するな!」という圧力にさらされるリスクがあるわけです><
マストドンのコードをgabが使うのも同様><
第零の自由にはそれを潰そうとする社会的・政治的圧力という自由の敵、場合によっては世間の大半が敵になる、そういった自由の敵との戦いでもあるわけです!><
出版社とかがクレームに対して異様に弱腰だったりするのも状況を悪くしていて、オメー表現者側として本当にそれでええんか? という気持ちになってしまう
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
つまり、オイゲン氏がgab等の色々で「人種差別主義者の手引きをしてる!」みたいな批判を受けるリスクみたいな感じで、コンテンツの2次創作のライセンスも「悪いやつが悪い2次創作したのは許可したやつが悪い」って批判を受けるリスクも考えられて、
(ここからが超重要)その時あなたは、(この場合は特に第零の)自由を尊重することができますか?><
Creative Commons — 表示 4.0 国際 — CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
「許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。 」の部分な
この辺り、徹底的に「アホとの闘い」になってくるので、とにかく作品の二次利用が著作者による支持を意味しないということを社会通念として広める必要があるし、また警察や裁判所とかがそういう判断をさっさと下せるよう司法側も調整してほしい
プレゼン資料やアイコンやLGTMに、漫画・アニメを無許可で使うと日本では著作権侵害です - Qiita
https://qiita.com/mishimay/items/b44cdefa5d2f95521fc8
いつものやつ貼っときます #文化庁はフェアユースを認めろJP
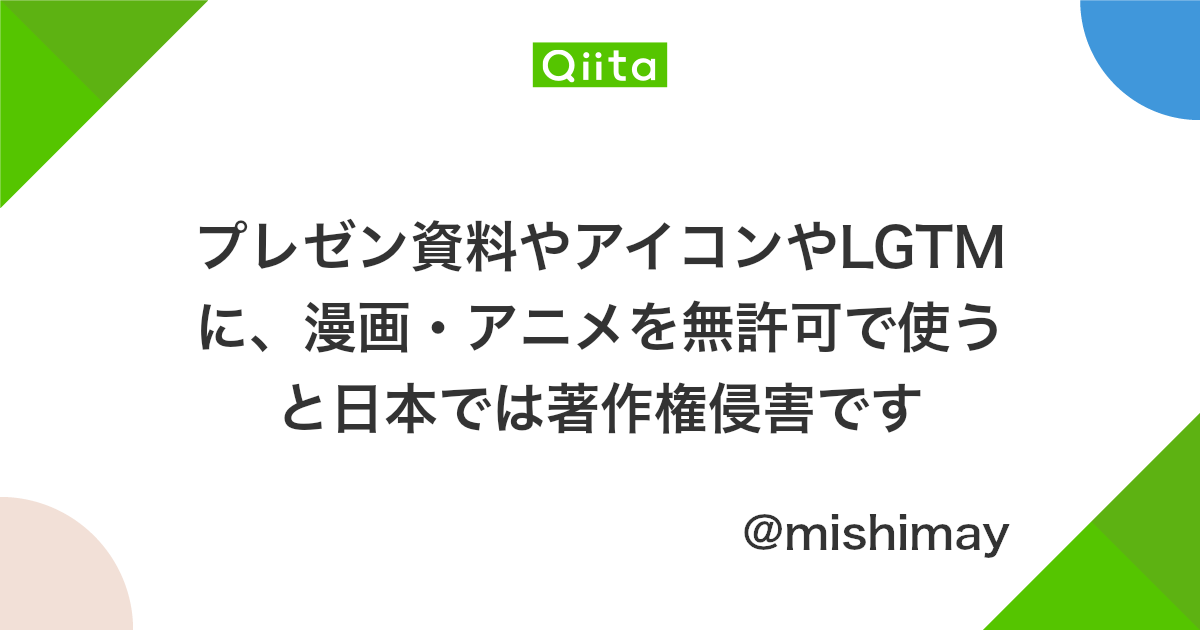
最大の問題は、その文脈上の意味での"アホ"が、人類の大半なわけで、自由を優先!ってよほどの奇人しかいない><(そういう奇人(?)の団体のひとつがACLU)
日本のコンテンツ界隈は消費者側の圧力団体がないという話があって、その辺りも関係ある話かな
まあ何らかの面を選んできたとき人類がその面で愚かというのは大半のケースで当て嵌まり、表現の自由についての問題もまた然りなんだけど、ポイントは政治は必ずしも数で動かすものではないというところで、数が揃わないなら声の大きな団体や組織とか別のやりかたで圧をかけていく方法もある。
アホが大半だからといって状況を変えられないという話にはならない (難しくはあるだろうけど)
発端の話題に限って言うと、「必ず第零の自由を認めろ!」ってことじゃなく、認める気がないのに第零の自由があるライセンスにするのは健全ではないという話><
オレンジだってGPLが嫌いなので(BSDL派!><;)、あえてある程度自由だけどGPL非互換のライセンスにすることもある><;
https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/102603601497215193
これは著作者がいちいち厳密に考えていると人生が終わるパターンなので、それこそ複数の候補から選べるパッケージ化されたライセンスの必要性を示しているといえるのでは
少なくとも、「著作者が独自に考えたオレオレライセンスは著作者の意図を正確に表明している」というのは否定できて、それは何とは言わない 3D モデル界隈などのゴタゴタを見るとよくわかる
大抵の著作者は自身の意図を正確に表明できないし現実は著作者の想定を越えていく、だからこそ性質のよく知られたパッケージが必要になるというわけです
CCみたいな仕組みが必要なのは同意で、たぶんさらに、そのライセンスをもっと具体的に説明すること、言い換えると「ライセンス」とか「自由」とかの教育が必要なのかも><(言うは易しだけど><;)
https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/102603638447465373
↑ほんとこれで、結局私のようなパンピーができることといえば胡散臭い人みたいに自由自由と叫び続けることくらいなんですよね: https://mastodon.cardina1.red/@lo48576/102603141013867974
まあ真面目にどこかで時間とってちゃんとその辺りの話を文字に落としたいとは思ってるんですが
########## GL ERROR ##########
@ Post render
1282: Invalid operation
って言われてもわからん
アリーナで正月ユイの後衛とミヤコの前衛を組み合わせられると絶対防御になってしまい貫通できたことがほとんどないし、そこにムイミなんかが入ってきたら負け確なのでつらい #プリコネR