小泉談話でさえ植民地支配の主体はあきらかに日本なのに、安倍談話の後退っぷりはやっぱり急激すぎる
https://news.shoninsha.co.jp/strategy/43280

小泉談話でさえ植民地支配の主体はあきらかに日本なのに、安倍談話の後退っぷりはやっぱり急激すぎる
https://news.shoninsha.co.jp/strategy/43280

23区のほうが石丸が強くて蓮舫が弱く、市部だと石丸と蓮舫は接近するけど、同時に小池の得票率も市部のほうが圧倒的に高くて、そうすると単純に居住者の年齢を反映しているんじゃないかという気はする。
https://www3.nhk.or.jp/senkyo2/shutoken/20336/skh54664.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

蓮舫さん良かったとおもうけど、やっぱり最初に反自民の構図で小池を語ったというか、政権交替選挙の前哨戦みたいな性格づけしてしまったのがなぁ。

萩生田百合子みたいな揶揄してたのが出てきたのとか、ああいうのどう考えてもいらないでしょ。あんなハイコンテクストな批判誰に伝わるの。あれが蓮舫の名に紐付けられたのとか、蓮舫が最初に反自民という性格づけしたからではあり、国政選挙を持ち込んでいると受け取られたとおりだとおもう。
事実上石丸の選対が自民系みたいだから、国政選挙をもちこんでいるのは自民党なんだけど。そんなの相手にする必要なかったじゃん。

蓮舫の声が若い世代に届かなかったのって、若い世代が理解できなかったからなんじゃなくて、そのチャンネルがなかった(乏しかった)からですよね。

中田敦彦のYoutubeに出たときのコメント、わざわざネガティブコメント書くのもいたけど、印象が変わったというのめちゃくちゃありましたよ。その同じ番組の石丸の登場回は蓮舫の3倍見られている。中田氏が公平な扱いをしていたのも疑いようがない。
YouTubeにもっと出ればよかったとかいうことではなくて、もっと前から、石丸はYouTubeでの露出を作っている。選挙戦でだけ伝えたいことを伝えているわけではない。視聴者が内容を吟味しているかといえば話は別。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

これ古市氏も小栗氏も悪意あるけど厳しい質問してるな〜とおもい、答えられないというか答える気がない石丸氏の印象かなりよくないけど、これで「マスゴミ」とか「テレビのレベルは低い」みたいなあつかいになるんだな。どういうコミュニケーションが求められているのかはよくわかる。
https://www.youtube.com/watch?v=i8S-62f_htE

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

おもしろそうとおもったけど、値段...
映画館に鳴り響いた音 - 春秋社 ―考える愉しさを、いつまでも https://www.shunjusha.co.jp/book/9784393930496.html

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

YouTube大学、今回の都知事選でいちばん感心したコンテンツだったな。三候補にじっくり話聞いて、それぞれを丁寧に掘り下げてて、まじすごいなとおもった。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

選挙活動にYouTubeつかうかどうかって、こういう話で、YouTube内でウケがいいコンテンツつくるとかなんとかじゃなくて、あるコンテンツを出したときのユーザーからのフィードバックを確かめながら、どんなレスポンスを作っていくか、そういう探っていくサイクルってどうやっても必要で、選挙期間だけでこういうのやるのが可能なわけがない。
"巷間では、営業プロセスやマーケティング手法が魔法の槌であるかのように語られがちだ。しかし、営業が強いと評判のキーエンスさんに関する本など読んでみると、いわゆる「営業力」で売っているというより、営業からのフィードバックで製品を良くして売っておられるように見える。"
https://x.com/sugimoto_kei/status/1810249405943222632

@imdkm 安芸高田市の動画は本人があるていど口出ししてまとめていたとおもいます。切り取られかたも考えているんだとおもいます。

この記事のことを考えていて、こういう活動モデルが政治的には無力すぎるんじゃないかということを考えている https://gendai.media/articles/-/130062
何らかの組織が集団的かつ統一的なプログラムに基づいて活動を展開したというよりも、むしろ、(…)臨機応変に可変的かつ可塑的な連繫のもとに同じ課題を共有したということ以外の何ものでもない。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

デジタル庁もそうだけど、IT業界で多様性と包摂はここ数年重要なトピックであるけど、マイナンバーカードの使われかたとか見ても「包摂」の党利的な利用はあり、これはパレスチナのピンクウォッシュ的なものにも通じるところがある気はする。
https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/
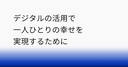

「俺らチームじゃねえし友達でもねえ。合言葉はたったひとつだけ。FreePalestine」というのはまさにシングルイシューにおける連帯のことだけど、たぶん「Free Palestine」を政治的成果として設定すると、いくつも複雑な問題にでくわしてしまってシングルイシューとして扱うことがだんだん難しくなってくる

めんどくさい話をするけど、パレスチナ解放のためにイスラエル製の自律型ドローンの輸入を止めようという話をすると、じゃあ日本の国防はどうするのというめんどくさい議論が待っている。この時点で議論自体が割れてしまう。「命の選別をするのか」っていうトロッコ問題的な問題設定は疑似問題だと言われるけど、ここで問われるのはまさにそれで、そこに対してどういう解を与えるかは、議論が割れることがある場合にどう人と連帯するかという現実的な問題でもあるとおもう。
ていうか自分がいま松方幸次郎の伝記読んでるのはこれが理由なんだな...。

話し逸れるけど、松方幸次郎の伝記読んでいてやっぱり一筋縄ではいかないなと思っている。川崎重工は労組との対決のなかで幸次郎の決裁で八時間労働を導入していて、また、不景気においても従業員の首は切らないぞと不退転の決意を持っていた。これが結果的には借金経営の常態化につながって銀行を巻き込んで破綻となるのだけど、破綻は結果論としても、幸次郎の8時間労働とか「従業員を首にしない」という決意はわりと社会包摂的な行動である。この幸次郎が宛にしていたのが、海軍による軍艦の製造需要で、軍艦の製造は当時、半公共事業的な性格もあった。ワシントン軍縮会議とロンドン軍縮会議でこの希望が潰えてしまうのだけど、川重による「包摂」は他の視点から見ればかなりエゴイスティックなものでもある。幸次郎のなかには「日本」というものがつよくあって、他の国との協働とかはあまり考えていなかったのは間違いない。それが川重社史における日露戦争肯定史観(植民地主義軽視)を導きだしている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

IT業界、サヨク的なものとめっちゃ相性悪い気がするけどなんで?と思ったけどそういえばリーナス・トーバルズって左翼じゃなかったっけ
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。