江戸期の古地図を見ていたときに穢多村が載っていて、軽く調べていたら「あれ、これってヤマト系住民が征服後に先住民族を囲い込んだのがいわゆる穢多非人なのでは」とおもったけど、大正12年(1923)にそういう研究があるんだな。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1869846/1/3

江戸期の古地図を見ていたときに穢多村が載っていて、軽く調べていたら「あれ、これってヤマト系住民が征服後に先住民族を囲い込んだのがいわゆる穢多非人なのでは」とおもったけど、大正12年(1923)にそういう研究があるんだな。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1869846/1/3


中学校の頃の歴史の教師が、「身分制において農工商という下位に置かれた存在が、自分より下位の存在を必要としていたのでそういう差別をつくった」みたいなこと言ってたけど、意味がわからないとおもったんだよな。封建的身分制度がなくなっても部落問題というものが継続するのも、先生の説明が意味がわからない理由だったとはおもう。これは封建制の問題ではなくアパルトヘイトだという説明には筋が通っているようにおもう。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

思い直してみると、もののけ姫って完全にこの構図で描かれた物語で、宮崎駿は読んでそう。

災害派遣される自衛隊員、重要装備は自腹なのか...
https://friday.kodansha.co.jp/article/353045

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

KADOKAWAの本もう買えないなとおもったけどそもそも自分が買いそうな本あまりなかった。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「SNSに思考をアウトソーシングして」というのは、かなりKADOKAWAっぽい。ほかの大手版元ではむしろそういう動き方できない(一部の編集者除く)。

こういうマーケットインみたいなやりかたはかなりIT企業っぽいけど、良くも悪くもKADOKAWAくらいしかやっていないはず。
https://www.youtube.com/watch?v=_2X7tn04ZYQ


自分で考えるんじゃなくてマーケットに判断させる、そういう動きはいろんな理由があって他の出版社はできていないとおもう。データベース消費っていうことでもあるし、ある意味でこれはドメインエンジニアリングみたいなものになってもいる。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

他の出版社とKADOKAWAが違うのは、取次通さない取引を増やしているという点で、以下は古い記事だけど、やりたいことはニーズにたいしてジャストな量の本を配本する、みたいなトヨタ方式。
https://biz-journal.jp/2015/06/post_10427.html
本の製造はニーズに対応するものとして配布しているだけで、市場を写しだす鏡になっている。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

海外に注文してた古書、しばらく反応ないから諦めてたら来たんだけど、 "Have a good christmas, xxx" って書いてあるな。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

江戸期がわからないと明治初期から中期にかけて、わからないところがしばしばでてくるな
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

「原本」という概念、たぶん明治初期ころから登場したんじゃないかとおもうんだけど、それがいまデジタル化でなくなろうとしているのであれば、この期間は「複製技術の時代」と呼べそう。

明治期を通して「版画」概念の登場をざっと追ってみたけど、明治初期には銅版画とか石版画とかそういう具体的な技術名はあるけど「版画」という言葉はない(ちなみに「木版画」という言葉もでてくるのは明治20年代後半、それまでは色摺であれば錦絵とか呼ばれている)。「版」という抽象的な概念が受容されるのはおおむね明治10年代後半から20年代を通じてといってよくて、これはおそらく「出版」の概念が法整備されたことによるとおもわれる。明治30年代の後半にようやく「版画」という言葉がでてくる。銅版とか石版とか技術固有の語ではなく「版」をもった「画」があるという概念に組替えられた。
新しい技術が社会の概念を変化させるにはどういう過程が踏まれるのかというのはけっこう興味ある話で、この「版画」概念の成立過程はもっと検証してみたい。

ちなみに「版画」という言葉自体は明治初期に print の訳語として採用されていて(「版畵」とかいて「ハンエ」と読む、明治10年ころの英和辞書にも見える)、つまり翻訳語だったんだけど、この時点では特殊な用語にすぎない。「ハンエ」が「ハンガ」に読みが変わっているのがやはり明治20年代後半だとおもわれ、それも法律用語の確立によるのではないかと考えられる。

詳細な資料をあつめればあつめるほど、伝記は矛盾してくる。藪の中みたいだ。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

【共産党 志位委員長交代 新委員長に田村智子政策委員長を起用へ】
共産党は、志位委員長が議長になり、新しい委員長に田村智子・政策委員長を起用することを決めました。共産党の委員長に女性が就任するのは100年を超える党の歴史で初めてのことになります。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20240118/k10014325601000.html


大塚英志さんですらこのへん漁ってるのが最近ならやっぱりこの方向全然可能性あるな
https://twitter.com/MiraiMangaLabo/status/1687421101247459328
「国立国会図書館デジタルコレクション」の全文検索対象資料を順次拡大します║国立国会図書館―National Diet Library
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2023/240118_03.html
https://mainichi.jp/articles/20240116/k00/00m/030/064000c
> 我が国の民族の歴史から『統一』『和解』『同族』という概念自体を完全に除かなければならない
もう南側の人たちは同胞と見なさないってこと? セルビアとクロアチア、あるいはルーマニアとモルドバのような関係に(一方的にできるものではないだろうけど)したいってこと? なんか凄いなあ。



このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

韓国野党議員「尹大統領こそが『コリアディスカウント』の真の原因」
https://japan.hani.co.kr/arti/politics/48940.html


「芳年伝備考」、月岡芳年と周辺画人についてのどうでもいいエピソード満載でおもしろかった

いつの間にこんなのが。
村上隆、YouTubeチャンネル始めます
https://youtube.com/watch?v=Wu-IvpUruTI&feature=shared
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

高校くらいのころにクラスの誰かがAKIRAを読んでて、ロックにはまっているやつがいた、それが当時出てきたばかりの椎名林檎を推していた。地方の「サブカル」はそんくらいの解像度だったな。ハイカルチャーはなかった。

賢い人でもTwitter上で自分が正しさに凝り固まっていることに気付かなくなる現象、何度も見てきたな。他人の正しさを批判する人も、自分の正しさに確信があるからそうするんだけど、それもおおくの場合は自分の正しさを証ししたいというだけになっていて、見るのも悲しい。

これはすごいものを復刻してくるな
平凡社創業110周年記念出版[復刻保存版 FRONT]シリーズ刊行 - 平凡社
https://www.heibonsha.co.jp/smp/news/n55778.html
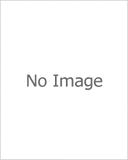
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

『近代日本版画の諸相』という本を読んでいるけど、かなりおもしろい。日本の近代出版の歴史についての議論としても読める。