昨日のNHKでやってた京都番組で「目垢がつく」と言っていて,これは「多くの人に見られることで物の価値が下がる」という面白い考え方なのですが,露出と拡散こそ正義が正義の世界に生きる人には著しく理解が困難そうではある.
昨日のNHKでやってた京都番組で「目垢がつく」と言っていて,これは「多くの人に見られることで物の価値が下がる」という面白い考え方なのですが,露出と拡散こそ正義が正義の世界に生きる人には著しく理解が困難そうではある.
藤原先生の『戦争と農業』を読んでいたらフォイエルバッハの「人は食べるものであるDer Mensch ist, was er isst」(「人とは,その人が食べるところのもので成り立っている」意味)が出てきた.
ドイツ語の《存在するsein》と《食べるessen》の直説法現在3人称単数がそれぞれist, isst(ißt)で同じ音になるのを活かした表現だ.
実はラテン語でも《存在するsum》と《食べるedo》は一部の活用(es, est etc.)や不定詞(esse)で同形になって,ペトローニウスがこれを活かして
eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est!
sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.
ergo vivamus, dum licet esse bene. (Petr. Sat. 34.10)
《ああ,わしらはなんと哀れな奴か.人は皆空の空.死神オルクスがわしらをさらっていくと,みなこうなるのさ.されば,元気なうちに楽しもうではないか》(國原訳)
と言っていて,最後のesseは両方の意味が含意されているのでそれを思い出した.
フォイエルバッハはどこかしらでジャガイモばかり食べていてはいけないというような趣旨のことも言っていた気がするがちょっと調べる手がかりが乏しい(記憶も怪しい)
学部生の時,昼食を全てライスSSと豚汁のみにした結果しかるべき報いを受けたのでDer Mensch ist, was er isstであるなぁと身をもって知った記憶があります(とは
しかし学部生の頃は食堂で500円以上食べるとなると相当頑張らないといけなかった記憶があるが,今はご飯と主菜に小鉢をいくつか取ると500~600円になったりするから物の価格が上がったんだなと思う.
ギリシアではなくローマ古典から話が始まっているのが意外な感がある
「国家が「愛国」の対象となったのは歴史的偶然にすぎず,人は国を愛さないこともできる.愛の対象の実相を追って,キケロ,アウグスティヌス,ヴェイユ,ミュラー,福沢諭吉,清水幾太郎など古典古代から現代までの多様な愛国論を渉猟し,愛国の構造を追究した野心作.無自覚な国家信仰を掘り崩すために」
愛国の構造 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b457227.html
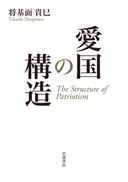
普段使っているコースターがどこにも穴が開いていないのに冷たい飲み物を入れた容器を載せているとだんだん下に水がしみるというはてなの茶碗状態になっている
ふむっ
「先日の参院選で当否が問われた野党共闘も、ようは「共産党と組んでもよいのか」が最大の論点ですから、イタリアでは終戦前後に提出ずみの「宿題」をいまだに解いているようなものですね」
イタリア化できない日本?〜参院選の自民党現状維持は、希望か絶望か https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66076?page=4

FALとFive-sevenが獅子舞をやっている公式絵があるらしいとの情報を得たがたどり着けなかった