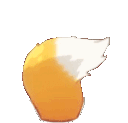論文毎日読むぞ232日目。万葉集の旅の歌(羈旅歌)について。
従来なぜ旅先で歌を詠むのかという点についてフレイザーの『金枝篇』を下敷きにした説明が試みられてきたのだけど、著者はフレイザーを前提にするのは不適当だとして、モースの『贈与論』で羈旅歌の心性を説明しようとしていた。少し古い論文だけど、現在の通説的な理解と方法はともかく方向性は一致しているように思った。
ところで、古代文学を説明するときに西洋の文化人類学的な見地は積極的に使うのに、文学理論を用いようとすると拒否反応を示す人が多いのはなぜだろう…。