社会主義者であってなおかつ古典学者であることは可能か考えていたが,月曜の朝から考えることではないな.
社会主義者であってなおかつ古典学者であることは可能か考えていたが,月曜の朝から考えることではないな.
小中高大生にプログラミング教育をしてきて分かったこと - Qiita
https://qiita.com/Kyome/items/138b6c897f191c0e95a5
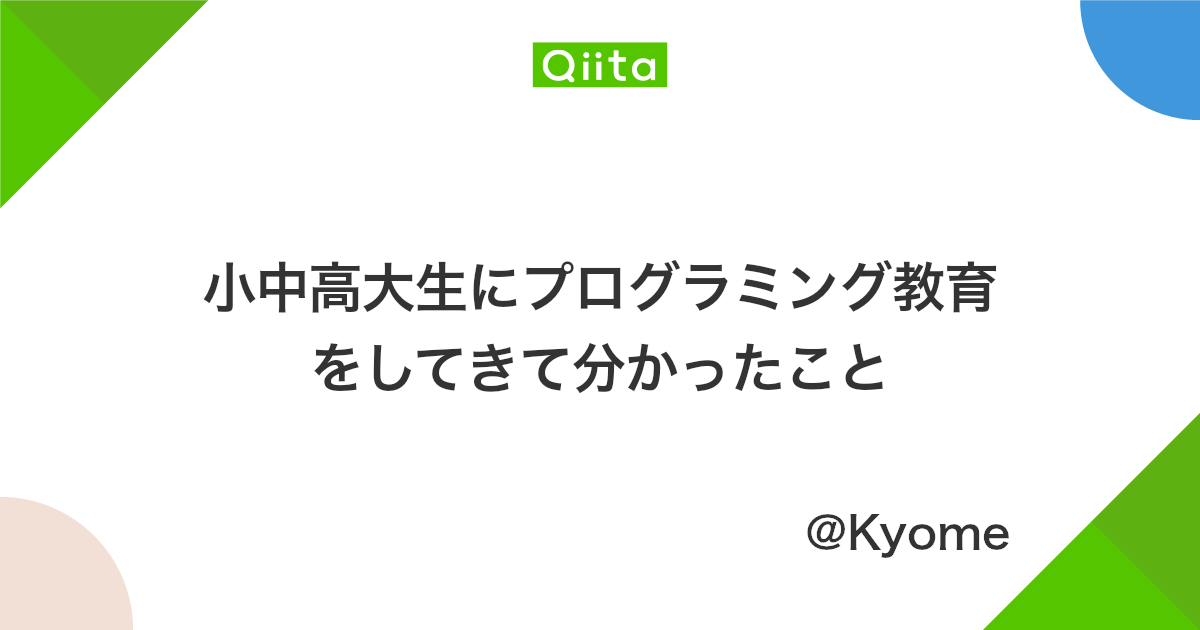
「すでに世を去った友人たちを思い起こすのは喜ばしい.ちょうどある種の果実が苦くも甘いものであるように,また非常に古い葡萄酒の辛さそれ自体が我々を楽しませるように.実際時間が経つと,胸を絞めつけていたものは全て消え去り,純粋な喜びが我々に訪れるのだ」(sic amicorum defunctorum memoria iucunda est quomodo poma quaedam sunt suaviter aspera, quomodo in vino nimis veteri ipsa nos amaritudo delectat; cum vero intervenit spatium, omne quod angebat extinguitur et pura ad nos voluptas venit)セネカ『倫理書簡集』63.5からアッタロスの言葉.
客観的な出来事それ自体は変わらないけれども,「間に時間が介在することで」(cum intervenit spatium)その事柄に対する人の評価が変わる,という考え方ともとれる.
この63番は友人フラックスを亡くしたルーキーリウスを慰める手紙で,前半の,過度に悲しみに身を窶すべきではないという趣旨の説諭はそれだけだと何か人の心に思いを致さない説教臭さを感じてしまうが,後半で,「こうしたことを君に書き送る私も,なにより大切なアンナエウス・セレーヌスのことを度を弁えず悼み,ために――これは全く私の望まざるところだが――悲しみに打ち負かされた人々の一例となってしまっているほどだ」(haec tibi scribo, is qui Annaeum Serenum carissimum mihi tam inmodice flevi ut, quod minime velim, inter exempla sim eorum quos dolor vicit)と我が事を交えて過去の自分との比較を通し,「だから我々自身も我々の愛する人々も死すべきものであることに絶えず思いをいたそう」(itaque adsidue cogitemus tam de nostraquam omnium quos diligimus mortalitate)と持っていく巧みな構成になっている.
10月に岩波新書でフーコーが出ていたので今度本屋行ったら買おう
ミシェル・フーコー - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b480364.html

オストホフの法則を調べるつもりでキルヒホフの法則をググってしまったので電気回路の話が出てきて困惑した
反出生主義に対して覚える違和感は,ある生が生きるに値するものであるか否かを,その生を生きる当事者が時間の中で形成しまた変化させる主観的な評価を離れて,絶対的な「良さ」と「悪さ」という尺度で見積もることはできない,という点にありそう.
「人間死ぬまでは,幸運な人とは呼んでも幸福な人と申すのは差控えねばなりません」(松平訳)というヘーロドトス(『歴史』1.32.7)の言葉を思い出したが,「幸福な」はὄλβιοςで「幸運な」はεὐτυχήςなんだね.
ὄλβιοςは「幸せ,富(物質的・現世的な幸福)」(ὄλβος)から来るのに対して,εὐτυχήςは偶々その時に「巡り合わせ」(τύχη)が良いというに過ぎず,運は絶えず動くものだから一時的・流動的な幸運を意味している.

This account is not set to public on notestock.