hogeとかならいいけどfugaだと「何から逃げるんだ…」と一瞬なる
なるほど「変化させて違和感ありそうなら、元から違和感たっぷりの曲にしとけば演出上の変化も違和感ない」|
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのサントラを買う人が知らないゼルダBGMの裏側|じーくどらむす|note
https://note.mu/geekdrums/n/naeac6465b1a5
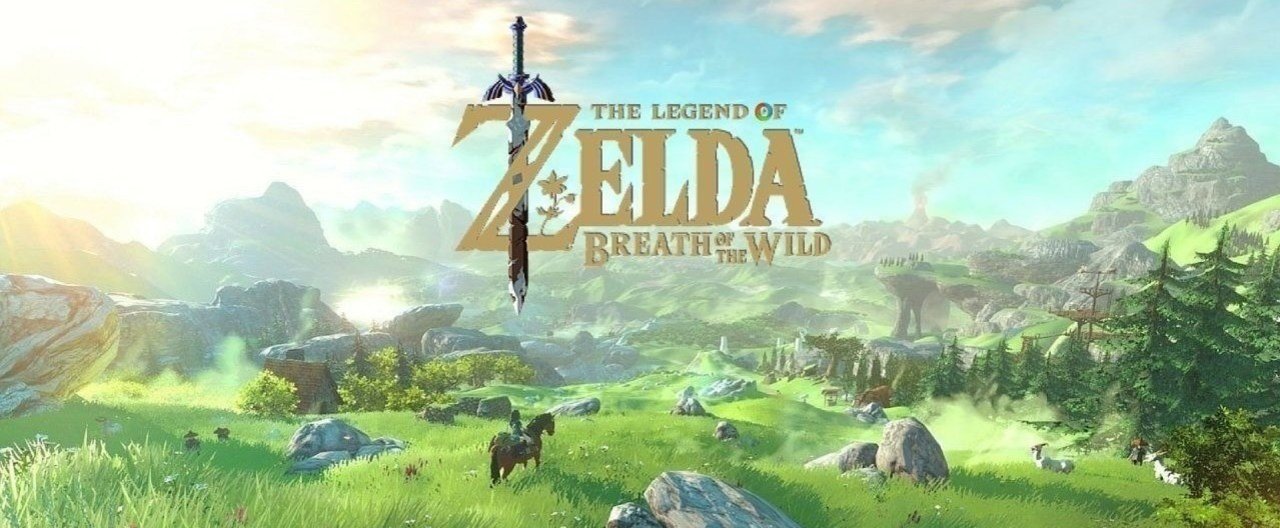
現状の説明では何が何やらな感じなのでἀνυπόκριτοςの修正案.
ザックリしたところではὑποστιγμὴ ἐνυπόκριτοςがprotasisとapodosisを句切るのに対して,こちらは挿入句を句切るためのものということのように思われる.
https://github.com/ncrt035/lexiconGrammaticum/issues/18
Stoppelli, P.(2008), Filologia della letteratura italiana, Roma: Carocci.
写本によって伝承されるものから手稿が残されているもの,印刷出版時代に入ってからのものまでイタリア語文学全般の文献学への入門・概説書.
基礎的な概念をはじめ,文献学とりわけ本文批判に関わる議論を的確にカバーした上で多くの具体例と図をまじえて書かれており非常に便利.要点や重要語が欄外にも書いてあるので教科書風でとても見やすい.
このStoppelliの本(https://gnosia.info/@ncrt035/99743707183439979 )からcritica degli scartafacciについての説明を見てみよう.
「ジャンフランコ・コンティーニに負うこの表現は原著者の文献学(※写本の筆写などで伝わる作品の文献学と対照して)の目的を上首尾に言い表している.草稿を再整理し,ある作品の生成過程を再構成することで理念的に著作者の製作現場へと入っていき,生き生きとした形で創造的メカニズムの動きを観察し,テクストとの最も近い接触を確立することができるようになる.」
Questa formula, dovuta a Gianfranco Contini, esprime felicemente le finalità della filologia d’autore. Riordinare le carte, ricostruire il percorso genetico di un’opera permette di entrare idealmente nell’officina dello scrittore, di osservare dal vivo l’andamento del meccanismi creativi, di stabilire col testo un contatto ravvicinatissimo. (p. 118)