『哲学探究』の新訳が出るようです
哲学探究 ルートウィッヒ・ウィトゲンシュタイン(著/文) - 講談社 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784062199445
『哲学探究』の新訳が出るようです
哲学探究 ルートウィッヒ・ウィトゲンシュタイン(著/文) - 講談社 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784062199445

これは来年出る本(買おう)
「農業の工業化に引きずられるかのように、農学の工学化がとどまることのない今、果たして工学に従属しない「農学」はどのようにして存在可能なのか、という問いから書き起こす、今までにない農学思想書。」
農の原理の史的研究 藤原 辰史(著/文) - 創元社 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784422202952
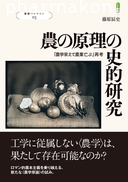
@kamiyajing 既訳との差別化は悩ましいですね(色々考えた結果同じ訳文になることは珍しくないですし,無理に差をつけるのもどうかとは思いますけども…).
専門家でないのでわかりませんが,新しいエディションに基づくということらしいので,『哲学探究』は死後出版であるぶん遺稿や草稿,他の著作との相互関係がややこしそうなのでその辺りの研究成果が反映されるのではないかと思います.
ただ,第4版というのはこれ(https://www.wiley.com/en-us/Philosophical+Investigations,+4th+Edition-p-9781405159289 )だと思いますが,この刊行が2009年で,最後の邦訳が2013年ですから,この2013年に岩波から出た翻訳の底本はなんだったかしらというのが今ふと気になったところです.

逆に「京都から世界を守ろう」で「世界を守るための行動を京都から起こそう」の意味が無理なく理解できてしまうのはなぜだろうという気がしてきた
4月だったか3月だったかに流会になったやつの続報が来たよ
「人文学の方法論」第一回研究会開催のお知らせ(日程変更) « 京都大学大学院文学研究科・文学部 https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/ceschi/seminar20201213/
人文学と計量的研究手法
「本研究会は、京都大学文学研究科の教員の分野横断的な研究の試みとして始められたもので、哲学、歴史学、文学などの人文学内部での分野の垣根を横断して人文学の方法論について認識を共有していくことを目的としています。第一回の今回は、社会学の分野でテキストデータを対象に計量的研究手法で研究されている樋口さんをお招きし、そうした研究の考え方について紹介いただくとともに、社会学における質的研究と量的研究の関わりについて太郎丸さんにお話いただきます。総合討論では、そうした紹介を踏まえて、これまであまり計量的な手法を取り入れてこなかった人文学の諸分野で計量的な研究手法にどのくらいの可能性があるのか、分野横断的にディスカッションしたいと考えています。文系・理系問わず、研究の方法論に関心のある方の参加をお待ちしますが、とりわけ人文系の諸分野の研究者の方たちに参加していただけましたら幸いです。」
後期ストアの中でもセネカやマールクス・アウレーリウスに比べて本邦ではやや扱いが小さい傾向があったが,ようやく新しい翻訳がでるね.
「「君は私の足を縛るだろう。だが、私の意志はゼウスだって支配することはできない」。ローマ帝国に生きた奴隷出身の哲人エピクテトスは、精神の自由を求め、何ものにも動じない強い生き方を貫いた。幸福に生きる条件を真摯に探るストア派哲学者の姿が、弟子による筆録から浮かび上がる。上巻は『語録』第一・二巻を収録。(全二冊)」
エピクテトス 人生談義 國方 栄二(翻訳) - 岩波書店 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784003360835

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
「カルターゴーを蘇らせるのにどれほどの悲しみを味わわなくてはならないか」みたいなのって出典は何だったかしら
ベンヤミン『歴史の概念について』第7テーゼに出てくるフローベールからの引用だった.もとはフローベールの書簡集かららしい.「カルターゴーを蘇らせるためにどれだけ悲しみを味わわなくてはならなかったかに思いをいたす人は少ないだろう」(Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage).
読み直してたら第2テーゼの冒頭にはロッツェの『ミクロコスモス』が引用されているんだ.「人間の気質のもっとも注目すべき特性のひとつに……個々人においては非常に深い我欲をもちながら,どの現在も未来に対してはおしなべて羨望を覚えない,という特性がある」(『ベンヤミン・コレクション1』から).
ルクレーティウス研究の関連で必要があってH. LotzeのQuaestiones Lucretianae(1852年にPhilologus誌上に発表されたラテン語論文)を見ることになったのだが,「このLotzeって哲学者のロッツェか?」となったので調べたところ,ルドルフ・ヘルマン・ロッツェ(Rudolf Hermann Lotze, 1817-1881)で間違いなかった.
実証的自然科学の知見と形而上学的価値の調和を目指した自然科学的観念論の哲学者が文献学的な形でルクレーティウス研究に寄与していたというのは面白い.