寒いなと思ったら窓開けてた
多分水曜くらいからずっと窓が開けっ放しだった
(風邪引かなかった私偉い)

 VS
VS 
 に500ダメージ
に500ダメージ のこうげき!
のこうげき! に50ダメージ
に50ダメージ に200ダメージ
に200ダメージ




やるって言っていたけど、本当にやれるとは思われていなかったというか。人材に恵まれていると当時から言われていたから、素地はあったと思いますけどね。
RE: https://mstdn.maud.io/users/orumin/statuses/111389896317582769
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

https://integers.hatenablog.com/entry/2023/11/10/025330
何か、普通でない、非自明な技をやっていれば「お、これは何かを証明しているに違いない」という気がしてきます。そうそう、私には理解できないから、きっと何かを証明しているに違いない
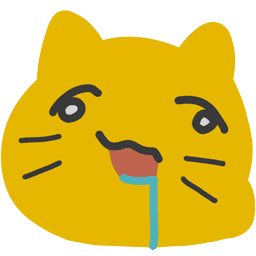


「思う」と「考える」の違いについての、英語話者向けの解説記事
日本語額の論文も参考にしたうえでの記事なので面白い
https://www.tofugu.com/japanese/omou-kangaeru/
最後に開設されている、「これからはじめようと思います」の「思います」の用法は面白いですね。書かれていることを敷衍すると、「始めていいのかどうか、参加者の事情をすべて把握していないので、私には確実にわからないが、私の気持ちとしては、今まさに始めるという方向へ向かっているので、同意してくれますか。」という丁寧さを伝えるために、「と思います」を付け加えているのでしょうね。


こういう、本来とはちょっと違った向きに言葉を投げかけることで、意味を伝えようというコミュニケーションはいろんな言語にそれぞれ特有な形であって、おもしろいですね。

「「これを言っておけばいい」というようなお題目を言うとか、定義できない言葉を「知ってる」と言うようなことは、絶対に許さない」ということ自体は、ソクラテス的姿勢であると思います。(許さない、というのが、暴力によって拒絶する、という意味ではなく、議論として有効であると認めない、という意味であると仮定します。)学校が学問によって人格を構成し、作り替える場所であるならば、議論能力を無理やり養う試みは、学校という制度そのものが持つ理念ともいえると思います。いくらかの教師は、そういった理想に忠実であろうとすると思います。
とはいえ、具体的な教育のシーンを想像すると、学問の方法論として内省よりも形式的検証を極端に重視していたのではないかと思います。これは確かに望ましくないかもしれません。
一方で、経験論的というか、分析的・還元的なアプローチが常に良いわけではありませんが、それを知るためにはやはり分析的な見方を身につけなければならないと思います。一人の教師として伝えられる立場には限りがあるので、こうした偏りもいい意味で働くこともあるかとは思いますが、どうでしょうか。

@kalvstranger@trismegiste.life そうなのですね。ただ、そういう憎悪をぶつける人が、完全な無教養というのではなく、むしろ、日本人にたいする失望のようなものが転化した形というのが、難しいところですね。(迷惑といえば、大いに迷惑であるおと思いますが。)

@kalvstranger@trismegiste.life 批判に憧れる心性までは持つに至ったが、批判に耐えうる学を自身に確立するほどの知的体力を持ちえなかったというような、中途半端な印象がありますね。妙にopinionatedな教師というのは、ありがちではありますが。

@kalvstranger@trismegiste.life なるほど。まあ、そうだろうな、そういうことを言いそうだな、と思います。
今から見れば、学生運動の後の虚無感ですら忘却され、歴史からはぎ取られたような異常な感覚が、大いなる負の遺産として、今日まで引き継がれていると感じます。中庸を逸していた時代だったと思います。