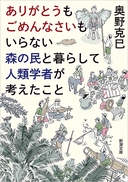【全体公開】
毎週木曜日更新 FANBOXぅ〜!
今週は、ヨドコウ迎賓館の見学記でございます。
フランク・ロイド・ライトの名建築について、語らせてください!
【全体公開】
毎週木曜日更新 FANBOXぅ〜!
今週は、ヨドコウ迎賓館の見学記でございます。
フランク・ロイド・ライトの名建築について、語らせてください!

読了メモ:奥野克己『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』亜紀書房
https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=856
*こんな人にオススメ*
・身の回りで「あたりまえ」とされる価値観に、うっすら疑問を覚える……
・自分が属するのとは違う文化のことを知るのが楽しい
・そもそも「反省」とはなんだろう? みたいなことを考えるのが好き
前々から気になっていた本ですが、昨今の読書力の衰えもあり、まったく手が出せていなかったんですよね……。
その本が、先日の旅行で泊まった LAMP LIGHT BOOKS HOTEL nagoya ――宿泊者が本を選んで借りられるタイプの、いわゆる、ブック・ホテルです――に置いてあったのですよ。
https://www.lamplightbookshotel.com/nagoya/
これ幸いと手にとって読みはじめたら、これがほんとに面白くて!
読み切ってしまいました……いやぁ、早く寝なきゃと思うのに読んじゃうんですよね……低下していた読書力が急激に上昇し、ブック・ホテルという形式のヤバさを感じました。

もちろん、本書が純粋に面白かった! のも大きいです。
本のタイトルでいわれている「森の民」は、プナンの民。ボルネオ島の北西部に住み、西プナンというカテゴリに属する人々。東プナンの民もいて、西プナンと東プナンではずいぶん違うようです。
まぁ違うといえば、現代日本人の暮らしとの違いは、相当なものですが。
かれらの暮らし、価値観、文化、いろいろなものに驚きを感じます。
とにかく違う。
たとえば、同じ日本人であっても、現代を生きる我々と、近代や近世などの日本人とは価値観が違うと思うんですよ。それでもやはり、ここまでの差はないでしょう。
わたし、ここに入ってやっていけるかな? 無理な気がするな〜!(現代日本でも「やっていけている」といえるのか……若干の疑念がないでもありませんが、この場は措いておくとします)
気候風土や、ここまで積み重ねてきたものの差――プナンは歴史を記録したりはしないのですが、それでも世代を超えて受け継がれるものは当然あります――それが、同じ人間なのに違う社会のいとなみを当たり前にさせていることを、じわじわと理解させられる感じです。
ただ違う違うといっていてもなんなので具体的に書いた方がいいですね。
表題の謝意や謝罪・反省の概念がそれはもう、表題にとりあげられるくらいだから当然なんですけど、違う。プナンの中でヨシとされるふるまいを日本でやったら、信用を失うなんてものじゃないでしょう。
でも、それがプナンのあいだでは当然のことなんですよね……。
かれらの社会の根幹をなしているのは「共同体優先」という揺らがない指針です。
その確固たる一体感があるからこそ、感謝も必要ないんだろうな、と思います。
物惜しみせず分け与える人こそがビッグ・マンとされるのも、そういう共同体だからなんだなぁ……。
そもそも、ものを所有するのは「なにかに備えるため」であり、人はものや金を所有することの奴隷になっていく、という考察も、なるほどなー! と、思いました。
わたし、よく思うんですよね……大金持ちのひとたちって、なんであんなにお金を増やそうとするのかなって。
もう、十分に持ってるでしょ? なんだって買えるくらい貯めてない? と。
だけど、違うんですね。
貯蓄それ自体が目的になっちゃってるから、やめられないんですね。
贈与の問題に話を戻すと、個人の所有を忌避して贈り物が回っていく現象も、面白いですね。
なんとなくホビットのマゾムを連想しますが、本質的にはぜんぜん違うんでしょうね。
一応注記しておきますと、ここでいうホビットはトールキンが書いた『指輪物語』などに登場する種族のことです。かれらの風習で捨てるに捨てられないものをマゾムと呼び、それをお互いに贈りあったり、あるいは共同体の博物館に流れ着いたりする、という説明があるのです。
贈り物が移動していく点は近しいのですが、ホビットたちはそれを「捨てられない」あまり、最終的には博物館で保存してしまうので、うち捨ててしまうプナンとは違う、としかいえないでしょう。
ほかに興味深かったのは、近親者が死ぬと名前が変わること、とか。
このデス・ネームは、死者との関係によってあらかじめ決まっているので、配偶者を亡くした人は皆同じ名前になる……あらたに配偶者を得ると、元の名前に戻る、といったシステムです。
死者の持ち物なども破棄し、死者について語ることも忌避されるという徹底ぶりで、これは死者を積極的に忘れることで、遺された者の心のケアをしているのかな……死者は共同体の一員としてカウントされないどころか、ほぼ「いなかったこと」に近い勢いで消されてしまう。これも、日本人からしたら、びっくりですよね。
日本人は(仏教徒であれば)、死者に名前を付ける(戒名)し、誰かが亡くなったら追悼する――すなわち、生前を偲んじゃうわけですよ。もう、まったく真逆です。
これについて本書では、名付け、墓所を作り祀ることで、死者は祖先神という新たな生(存在のありよう)を得ると書いてあり、なるほどなー! と、思いました。
とにかく、いろんな「えっほんとに?」「なるほど、こう考えれば理解できるのか」の実例が詰まっていて、常識がぐらぐらするので、とても面白かったです。
この感想を書くにあたって調べてみたところ、新潮社から文庫版も出ているようです。
https://www.shinchosha.co.jp/book/104571/