ファイルマネージャ、GNOMEのやつが一番好きだった。たしか名前ノーチラスだったはずと思ったら「ファイル(GNOME)」になっていたのか…贅沢な名だねされた感すごい
ファイルマネージャ、GNOMEのやつが一番好きだった。たしか名前ノーチラスだったはずと思ったら「ファイル(GNOME)」になっていたのか…贅沢な名だねされた感すごい
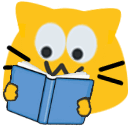 の投稿
tomnyancat@fedibird.com
の投稿
tomnyancat@fedibird.comこのアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
世界探検全集4冊目。筆者の1962年ニューギニア探検時の記録。
題名にあるように、ニューギニア原住民は石器のみで暮らしており、そのつくりかたの一部始終をつきとめた2章がとくにおもしろかった。
岩塊にむかって足場をかけ、火で燃やして岩を剥がし青や緑の鋭い石(グラウコファンだったらしい)を砕きとる姿に、そうやって作るんだ、となった。
その採石場までの道中、筆者が谷川に落ちて大怪我をするのだが、そのときの現地住民の献身的な姿が泣けた。なんやかんやでこういうところがあるから人類長いこと生きているんだろうなと感じた。
あと世界探検全集、いつも現地ポーターのすごさを大きく感じる。ものすごい濁流に橋を作ってかけてしまうとか、一瞬で筏作ってしまうとか、みんな現地ポーターの業。
ちなみに当時現地では金属製のものはなく、土器もなかったらしい。土器って意外とないところあるけど、土地の土の種類にもよるのかな。
高山登頂の話では、ブリキ缶に入っていた25年前の探検隊のメモにたまたま遭遇するくだりがあり、リアル宝箱だなあと思った。
はじめて氷を見たダニ族が、持って帰ろうと缶やビンに詰めるくだりもよかった。村にもどったら当然溶けてしまうわけだが、魔力として語られるんだろうという筆者の文がまたよかった。
味の素食文化サイトでつい先日読んだパンダナス、まったく同じ調理法が書かれていた。ハラーは青くなるくらい合わない味だったらしく、豚の脂っぽいと書いていた。この記事ではオイリーと書かれているが、なんかそんな味なんだろうな。
https://www.syokubunka.or.jp/publication/productions/vesta-columns/post010.html
言霊ってどの文化もだいたいあるよなと思ったところ。
>三人のダニのうち一番年をとったのが私のところへやってきて、火を燃やしてくれと頼んだ。つまるところ、私はイエ・トゥアン(石斧の旦那)という名前を持つ身だから、霊も私に加護を与えるだろう、と考えた。
『アフリカの日々』のここ思い出した。
>アフリカ人の神話的才能は、知りあってまもない白人につける名前のたくみさからも、つとに明きらかである。(中略) あるとき、定年退官した植民地官吏とロンドン動物園で再会した。この人はアフリカでブワナ・テンボ──象の旦那──と呼ばれていた。彼はひとりで象舎の前に立ち、象に思いをこらしていた。おそらく度々そこへ出かけているものと見えた。かつてこの人に仕えたアフリカ人の使用人たちなら、彼が象に会いに行くのを自然の理だとするだろう。だが、たまたま数日間の滞在中彼に出会った私をのぞいては、ロンドンじゅうの誰ひとりとして、彼のこの行動を理解する人はいないだろう。
『野性の思考』かなにかで、中心に「男の家」がある南米民族の集落構造が書かれていたが、高地パプア族も「男の家」があるらしい。基本的に男は日中そこで過ごし、女は入れない。女は母系で家を持つ感じで、夫婦は妻問い。人間が定住しはじめたときって、「男の家/女(もしくは母系)の家」形式と、「夫婦を中心とした家」どちらが多かったんだろう。
宣教師が入っている地域で、現地住民の彫ったキリストが女性だった話がおもしろかった。男性は裸でいるもので、腰蓑をつけているのは女性なので、十字架のキリストは女性だろうと思って彫ったのではないかという話。
あとがきの、ここが非常によかった。
>私は、彼らとちがう文明の証拠の一つとして、鉄製の斧を彼らのところにもっていった。けれども進歩という進行でこり固まっているわれわれが想像するほど、その結果は圧倒的な衝撃を彼らに与えなかった。なるほど、パプア人は鉄製の斧の鋭さや刃のかがやきにおどろきもしたし、これを所有することを誇りにも思った。けれども、鉄製の斧を使えば石の斧の半分の時間で仕事をすることができるとわれわれは思いたがるが、(このことはわれわれの観念にとってたしかに大きな特徴である)、こういった考えは、パプア人の場合、全然不可解なのだ。なぜ石斧よりも鉄斧の方が早いのか。それがどういうことなのか、パプア人には全然分らないのだ。私はかつてチベット人にジェット機は、ふつうの飛行機よりもずっと早く、海を二十分位で横断してしまうということを話したことがあるが、こういったことにたいし、彼らは不可解な、当惑したような沈黙を示した。そしてチベット人の一人は「早いことがどんな意味があるのか」とたずねた。なるほど〈どんな意味があるのか〉と私も考えざるを得ない。わたしはそれを彼にどうしても説明してやれなかった。
#読書