このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
京都大学学術出版会:カティリナ戦記/ユグルタ戦記 https://www.kyoto-up.or.jp/books/9784814003488.html

へー知らなかった
「もう一つの問題は、白話文学作品の一般的な例に漏れず、『水滸伝』も版本により本文がかなり異なることである。それらの異同の多くは単なるミスではなく、編集者・刊行者の意図が強く反映されたものである。従って、『水滸伝』の全体像を把握しようとすれば、各版本における異同の状況をも知る必要がある。幸い、『水滸伝』の本文異同はおびただしい量に上るものの、『三国志演義』のように異同が多すぎて校勘記を作ることが不可能という水準には達していない。」
詳注全訳水滸伝 - 株式会社汲古書院 古典・学術図書出版 http://www.kyuko.asia/book/b587093.html
「日本列島の鳥食の歴史から、さまざまな鳥料理のレシピ、江戸に鳥を送っていた村のフィールドワークまで、今まで語られなかった初めての「江戸の鳥のガストロノミー(美食学)」。」
鷹将軍と鶴の味噌汁 江戸の鳥の美食学 菅 豊(著/文) - 講談社 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784065245873

ホーン ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論 千葉 雅也(著/文) - 星海社 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784065243275
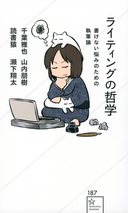
commentator と auctor の境界がときに淡くなるという話をしたが,これは,この分野では注釈が単に注釈対象を「客観的に」分析するものではなく,その釈義を通して注釈者自身の思想や学問を表明する働きを持つことによるということだろう.そういう意味では,自己の学風というか大局観のようなものを欠いて編まれた注釈は,工具としては便利であるとしても,何か二流の仕事にとどまらざるを得ないようにも思える.
「同じ事柄の,異なる言葉による敷衍」が持つ個性と新しさを認めないないし評価しないという昨今の風潮は人文学が順調に「サイエンス化」している印でもあるだろう.
「キャンセル・カルチャー」はなぜ問題なのか…? ネット時代特有の「意外な悪影響」(ベンジャミン・クリッツァー) | 現代ビジネス | 講談社(1/7) https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84505
↑この手の記事を見るたびに「(1/7)じゃねぇんだよ,(1/1)にしろ」としか思わん

「自分の書いたものに意図しない広告を挿入されることが美意識として許せない」という考えがあって自前の発信手段を持つ人は少数派
このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。
絵を描く用のノーパソに刺してるマウスは右クリックとホイールが9割くらい死んでいるのでめっちゃ縛りプレイなんすよ
何も描けずに時間を無に費やすのではないかという惧れがあったけど案外何とかなることが分かってよかった