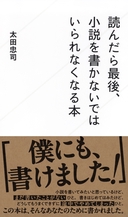読了メモ:斎木久美子『かげきしょうじょ!! 15』白泉社
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/72020/
*こんな人にオススメ*
・15巻……待ってたぁぁ!
・女子にしか出せないカッコよさってあるよね
・タイムトラベルもの、せつなくて最高か!(※番外編)
文化祭で上演する劇の指導は、原則として、その演目を作った人。しかし、予定されている『リプリング』の作者はすでに鬼籍に入っている。では誰が? 演出家としてあらわれたのは、作者の娘だった。なかなか発表されないキャスティングに焦らされる紅華乙女たちだったが――
というわけで、新刊が出てたので読みました。
日付としては……たしか4日だった気が。『忘却バッテリー』の新刊と同じ日に読んだんじゃなかったかなぁ、なんだろうこの盆と正月が一気に来た感!
シリーズなので、未読のかたにもアレしないように感想を書くのが難しいのですが、そういうの配慮しなくていいとしたら、いや配慮したいので一部伏せると、君どちの名台詞を●●(伏せた文字数は実際の文字数と一致しません)はどう演じるの〜〜〜! ●●のヒロインも気になる! 早く! 早く次!