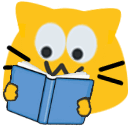表紙がかっこいいから読んだ本だが、わりと有名作だったようだ。
農作・定住は狩猟採集・遊牧よりすぐれた生き方!バンザイ!→国家誕生みたいな流れで考えられがちだが、どう考えても農作の方がつらいし国家がなくても農作も定住もふつうに行われていたので、この流れって疑っていったほうがいいかもしれない、というような内容だった。
"文字として残っている歴史"では、意識的にか無意識にか農作・定住からの国家を正当化したいからそういう説明になっているのだろうというのはそうかもなと思った。
ただ逆に"文字として残っていない歴史"は想像に頼らざるを得ないので、手放しで受け入れられる内容でもなさそうだった。
国家において麦や米が推奨されたのは、税を取りやすいから(収穫期が決まっており地上に生えるため査定がしやすく、保存がきく)ではないか?というのは、ありそうだな…となった。
紀元前の初期国家は崩壊しやすく、国が崩壊してもべつにイコール不幸というわけでもなく、単に分散地域のつながりに戻っただけという話は、まあそんなものかもしれないと思った。なんなら国家に飼い慣らされない人のほうが自由度も賢さも高かったであろうと。
"自ら語ってくれる(誇張して語りがちな)"国家に比べ、分散して生きる人々については"なにが起こっているのかを知りたければ、周縁部へ出向いて小さな町や村、遊牧民の野営地を探し回らなければならない"という話に、巨大SNSと を思い出したりした。
を思い出したりした。
お互い「イーロンに振り回されて疲弊したくない」「レターパックネタ意味不明」「ゾンビだらけやん(実際、疫病で滅亡した国家は多い)」「人いないじゃん」などと思いながら別に断絶しているわけでもなく、紀元前もみんなどちらかというと好きなほうで生きたり、生活せざるを得なかったりだったのかもしれない。