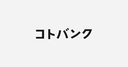『社会分業論』の流れで読んだ。訳のおかげかこれはすごいおもしろかった。フランスの文化人類学・社会学系でこんなに読みやすい本があるなんてすごい。他は全部読みにくい。(風説の流布)
贈り物をすること・受け取ること・もらった以上のお返しをすることが義務として組みこまれている文化がかなりあり、貨幣なんかよりずっと前から経済の仕組みとして成り立っていたというのが目からウロコだった。なんとなくは知っていたが、ならわしとかじゃなくこんなにガッツリ制度だったのかとなった。
>部族生活の全体は恒常的な「与えることと受け取ること」にほかならない。およそあらゆる儀式も、あらゆる法的・慣習的な行為も、物を与えたりお返しをしたりということをともなっており、それなしにはなされない。富を与え、また受け取ることは、社会が組織され首長が権力を維持し、血族どうしの絆が保たれ、姻族どうしの絆が保たれるための主要な手段の一つである。
ことばにも表れていて、あげることともらうことはひとつの単語の場合も多く、かわりに誰の何に対する贈与なのかがめちゃくちゃ細かく分類され名付けられたりしているらしい。ネイティブアメリカンとかポリネシアだけでなくゲルマン辺りでも。
>ホルムズ(Holmes)氏の明敏な指摘によれば、フィンケ川の河口において氏が出会った二つの部族(トアリピとナマウ)の言語では、ともに、「購入と売却、貸与と借用を示すのにただ一つの単語しかない」。やりとりとしては「互いに逆向きなのに、同一の単語で表現されている」。この人たちは、売るという観念も、貸すという観念ももっていないのに、にもかかわらず、売るとか貸すとかというのと同じ機能を有した法的・経済的な諸々のやりとりをおこなっているのである。
贈与し合いで友好関係を築くのはもちろんのこと、逆に争いを表すこともあるそう。贈り合い合戦で相手がそれ以上のものを贈れないほど贈れた方がマウントを取れる。マウントを取るためなら大宴会を催したり家を燃やしたり人の首を切ったりもする。
ポトラッチ
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%81-133769
このポトラッチ、最近なんかで読んだなと思ったらマンガの『望郷太郎』だ。まさにこれが出てくる。
文字がない文化においては公の場で贈与をすることで周囲が債務の証人になり、子どもが幼いうちに親が死んだ場合お返しが保険にもなるという話が、すげ〜〜考えた人天才か?ってなった。
お返しはより良いものでなければならないというのも、首切るまでいくとあれだけどストレッチゴールみたいで進歩・成長を促しているような気もする。ちなみに利率は年30〜100%らしい。高い。消費者金融以上闇金未満くらいか。
ヨーロッパにおける「手付金」も元は誓約の保証として神に献納する金だったらしい。贈与も交換も債務も保険も儀式もごった煮だったのを、あとから分割したわけだ。
>ラテン人の法も倫理も経済も、このような形態をとっていたはずであるけれども、そうした形態は、ラテン人の諸制度が歴史時代に入ったときに忘れ去られてしまったのであった。それというのも、まさしくローマ人と、そしてギリシア人とが、おそらくは北部および西部のセム語系の人々に続いて、対人関係にかかわる法と対物関係にかかわる法との区分を創案したのだし、贈与や交換から売却を区別したのだし、倫理的な義務と契約とを切り離したのだし、そして何よりも、儀式的関係と法的関係と利害関係とのあいだには違いがあることに思いいたったからである。
まあ分けはしたかもしれないが、未開文化では物々交換しかない→高度になると貨幣を使い→さらに信用取引が出てくる、みたいな進み方では別にないぞ、という所が本当すごいと感じる。『野生の思考』にしても、最近読んだ『反穀物の人類史』にしても、昔の人は頭が悪いから現代の都市型のような生き方をしなかったわけではないというのを解き明かしていくのがおもしろいんだよな。
ポトラッチに近い文化は日本にはあったのかな?ポトラッチではないが、スカンジナビアの『エッダ』の一節で人身御供を思い出した。
>度を過ぎるほどたくさんの生贄を神々に捧げるくらいなら、お祈りなど(願い事など)しないほうがよい。贈り物をあげるのは、いつだってお返しの贈り物を期待しているから。供物に度を過ぎた出費をするくらいなら、供物など捧げないほうがよい。
#読書