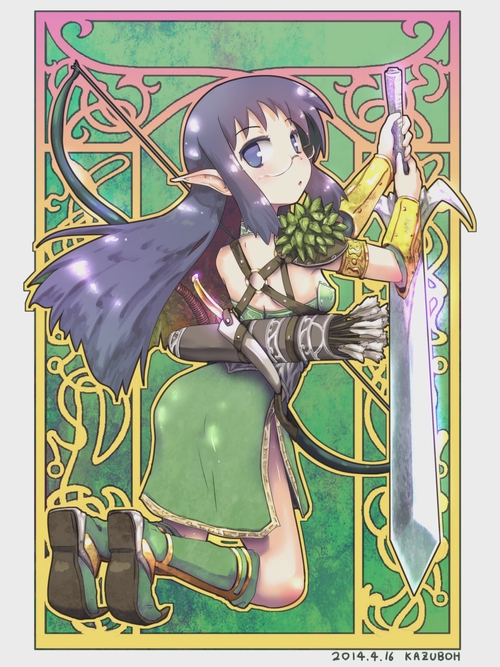人それぞれ個性があるように特性の出方も人それぞれだから一概には言えないが、少なくともオイラと息子のASD特性に関しては、メタ認知を繰り返して解像度を上げまくったことで説明が出来る状態になりつつある。
なので、「おいらの特性がもたらす一次障害の例」を書いてみることにした。
先日息子が、マイナスドライバーを探していた。
息子も自分も、玄関にある下駄箱の、下の段に片づけてあるものと思い込んで探していたところ、見つからない。
それを見かねたカミさんが「上だよ」と助け舟を出してくれた。
すると、事もあろうか自分と息子、揃いも揃って「2階か」と勘違いして階段へと向かったのである。
「ちがーう!」とのカミさんの声によって自分はやっと違和感を得て、「玄関の上の棚」にあるのだと気づくことになる。
息子は「上の棚」と明示されるまで、終ぞや気づかなかった。
この場合、定型発達の人、あるいは別の特性を持つ人ならば、「着眼点から相対的に見た方向である上=上の棚」である、という事に気が付き、直ぐに上の棚に手が届く。
あるいは、「どの位置から見ての上なのか?」という疑問が湧き、直ぐに相手に質問が出来る。
が、少なくとも自分と息子は、これが一切できない。
他者の介入によりそれまでの思考が中断したところで、自ら示していた「着眼点の座標」を瞬間的に失念してしまうのである。
まるで思考の座標軸が原点に初期化されるように。……故に、自分を軸として無意識化に思考せざるを得なくなるのだ。
「生まれつきそうなのだから」
位置関係に関する「認知のズレ」として上記例を挙げた形になるが、これが全てではない。あくまで「着眼点の座標」が「リセットされる」事が問題なので、実際の位置関係だけにとどまらない。
例えば人と人、陣営すなわち敵か味方か、自社か先方か、といった、事を解釈する上での軸が二つ以上存在すれば、どのような場面においても発生する。
「あの人が」と言えば、それは相手方のことを指しているのか、また別の人を指しているのか……1/2の確率で「間違える」ことになる。
これの何がタチ悪いか……きわめて発生確率が高く、メタ認知を繰り出して連日振り返ったら、気が狂いそうになった、それくらいに「ズレ」が頻発するのだ。
この「認知のズレ」が複数回連続発生したらどうなるか、仕事の過程で発生したらどうなるか……コミュニケーションそのものが破綻し、関係が悪化するのは明白である。
それらが斜め上の発言や行動に繋がり、「人の話を聞かず自分ルールで動く」とされる、ASD特有の特徴を形作ることになってしまう。
一旦振り返るとこんな感じである。
スタンドか何かの能力かと言いたくなるくらい「えげつない」。
少なくとも自分と息子の場合での話であり、他の人の機序がどうなっているかは知る術がない。
また違ったところでこのような「認知のズレ」を持っていたりするのだろうか……。また違う何かがあるのだろうか。
原因は恐らく、ワーキングメモリと呼ばれる記憶に関する脳の領域が、生まれつきの非定型発達に至っているものと思われる。端的に言えば、ネジが足りていない。学生時代に友人から「天然ボケやなwww」と言われたことを振り返っても例えとしては的確だろう。
この特性、治療は不可能。一生続くまさに「障害」とも言える。
ただ、解決策はあると感じている。
それは「違和感」に気づくということ。違和感が得られれば比較的「気づき」は速い。
やるべきは、その訓練である。
例として。
発言の中で得た情報だけで解釈しない。まず疑う。
次に、自分なりに筋道を整理する。そこで違和感に気づけば良し。
気付かなければ過去の例を探る。そこで違和感に気づけば良し。
そして筋道整理をしたら、発言者やメンター、上司に確認を取る。そこで「違う」と言われれば良し。
そうして是正したうえで、「認識を合わせた」状態を作ってから、発言するなり行動を起こす。
それでも間違ったら、頭を下げる。それはもうしょうがない、と割り切る。
これらを徹底すれば、大きな問題はほぼほぼ解消できる。
ただ、速度が求められるミッションなどではこの方法は無理が生じるので、他の出来る人に委託するなど、別の手段をとるべきである。
そこは「特性に対しての対策を行使する」以前に「ミッションを遂行する」ことに重きを置くべきなので、対策をたてることへの「こだわりを捨てる」事が重要になる。
最後に、何よりこれらは愛敬が伴って成立する。
特性を恐れて引っ込み思案なままでは、上手くいかないというのも、実体験より感じているところである。なので相手を信用し、かつ自分も信用してもらえるように、間違っていても、明るく、誠実であることが重要になってくる。
……といった事を連日遂行している次第。
どうだい、まどろっこしいだろう