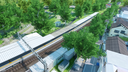逃げるように、僕は夜汽車に飛び乗った。
彼女との思い出はこの街に置いていこう、そう決心した。そんな僕は彼女といっしょに住んでいた杉並のアパートを引き払って、北に帰ることにしたのだ。
薄暗い上野駅の十三番線ホームには、北へ行く夜汽車を待つ客で溢れていた。ふと耳に入る子供の声が騒がしく聞こえる。騒がしいと思ったのは、僕にはありえない未来だと思っているからだろうか。おそらく、僕はこうして所帯を持つこと無しに一生を終えるんだろうなと思ったからだ。彼女はあまりにも一途で、あまりにも優しい人だった。聖母のような彼女は、無軌道で頽廃的な僕にはふさわしくないのだ。僕は、一人でやっていく。君なら、君にふさわしい男性が見つかるだろうと書き置きを残して、僕は彼女との思い出に満ち溢れた東京を棄てる決心をしたのだ。
半地下のホームに放送が響き渡る。北に向かう夜汽車がまもなくこのホームに入ってくるのだと。機関車を最後尾にホームに入ってきた紺青の車体には修繕された後が生々しく残る。今は、飛行機や新幹線でもっと早く目的地に行くこともできるのだが、あえて夜汽車を選んだのは滅び行くものヘの哀愁なのだろうか。この夜汽車も、あと何年かすれば無くなってしまうのだ。新幹線の工事で、夜汽車は北へ走れなくなってしまうのだから。
紺青の車体のドアが開く。僕は切符を頼りに今宵の宿へと向かった。ドアを開け、小脇に抱えていたボストンバッグをベッドに降ろす。そして背負っていたバックパックもエキナカのコンビニで買ったお弁当とお茶、レモンサワー缶とビール、おつまみも。僕は肘掛けを出してベッドに腰掛けると、ビニール袋から取り出したレモンサワー缶を開ける。ぷしゅりという音が室内に響き渡る。レモンサワーを飲みながら、僕は発車のベルを聞いていた。いろいろあったこの街ともおさらばかと思うと、私の心にはなにか一ピースが欠けているような気がしたのだった。